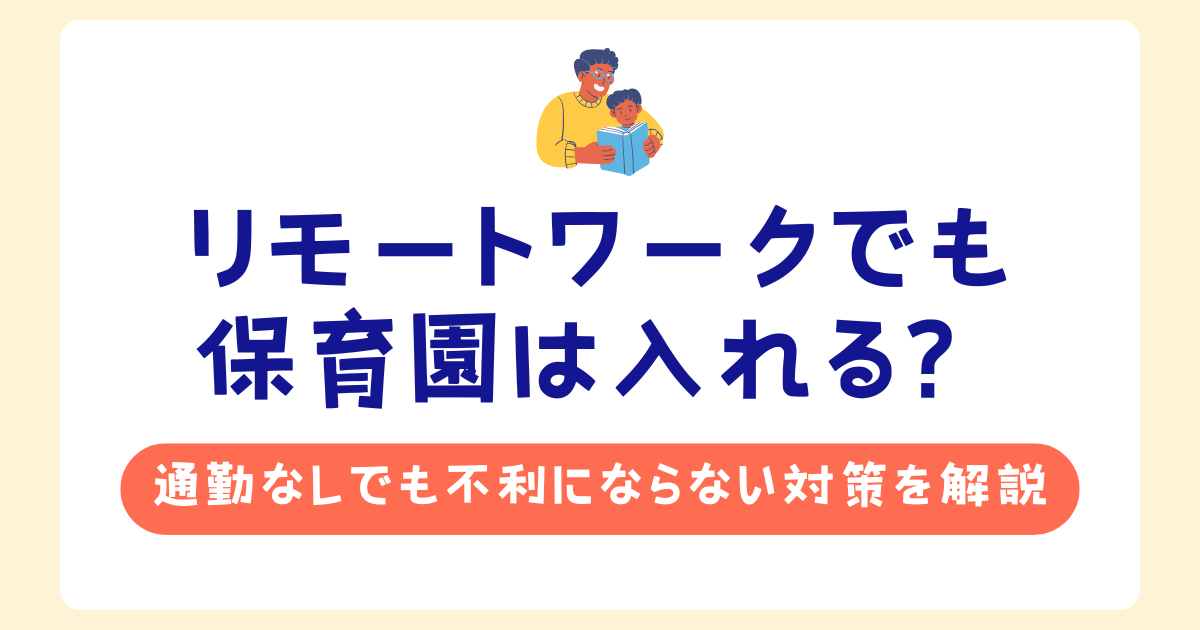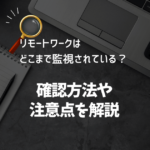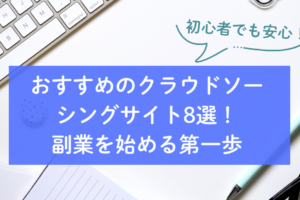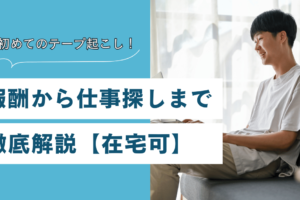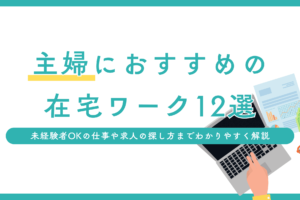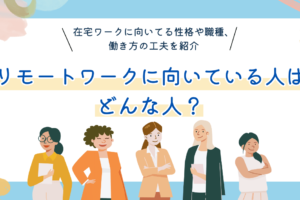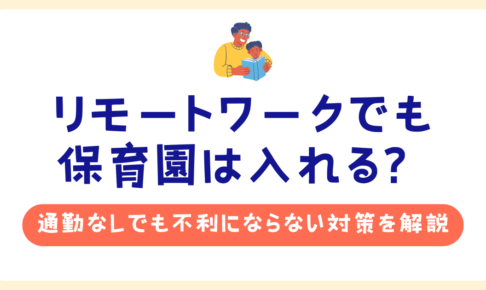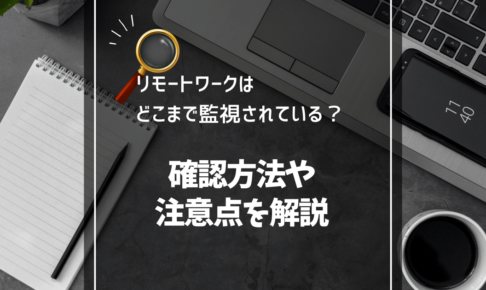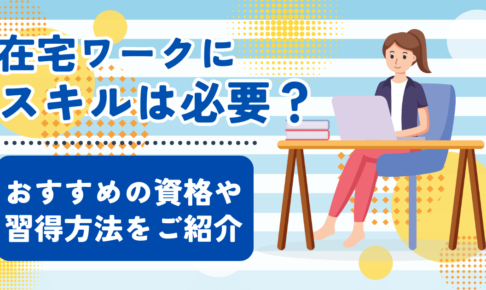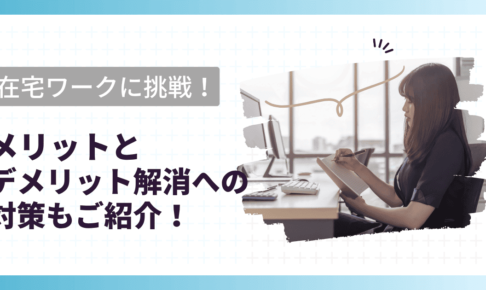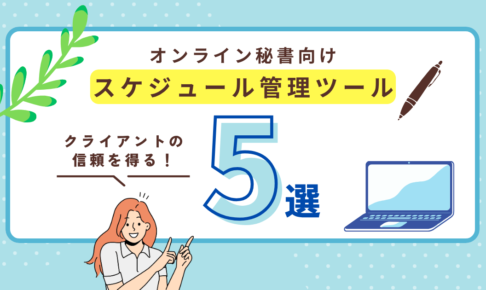「在宅勤務だと保育園に入りにくいのでは…?」という不安を感じている方は多いと思います。
たしかに、以前は“出勤している人”の方が保育園の優先順位が高い自治体もありました。
しかし今では、厚生労働省が「在宅勤務も自宅外勤務と同じ“就労”とする」と明確化しており、多くの自治体が平等に扱うようになっています。
本記事では、「在宅勤務でも保育園に入れる」ことを前提に、通勤時間の扱い方・就労証明のコツ・点数対策・成功事例をわかりやすくご紹介します。
リモートワークでも保育園に入れる?保活の基本と制度の変化

リモートワークが一般的になった今、保育園の入園条件や選考基準も時代に合わせて変化しています
ここではまず、「保育園の選考はどのように行われるのか」という基本から整理し、在宅勤務家庭が押さえておきたい制度のポイントを確認していきましょう。
保育園の選考は「指数(点数)」順。基本をおさらい
保育園の選考は「利用調整指数」と呼ばれる点数制で行われます。基本的には、就労状況や家庭環境によって点数が決まり、点数が高い家庭から順に入園が決まっていく仕組みです。
これらの指数は、
- 就労時間(フルタイム・時短など)
- ひとり親、兄弟同時申込
- 疾病・障害の有無
などで加点されます。
なお、基準は自治体ごとに異なります。例えば、世帯の合計指数を、父母それぞれの基準指数に調整指数を加えて計算する自治体もあります。
そのため、詳しくはお住まいの自治体での確認が必要です。ホームページで確認できる自治体もありますので、まずは検索してみてはいかがでしょうか。
厚生労働省も明言「フリーランス・在宅勤務も“就労”として認められる」
以前は「外で働く人が優先されやすい」と言われていました。実際、フリーランス・在宅勤務の親に対して一律に点数に差異を設けて、優先度を下げている自治体もありました。
しかし、厚生労働省は「自営業、在宅勤務と通勤勤務の間で差をつけるべきではない」と公式に発表。それぞれの就労状況をしっかり把握した上で判断することが重要としています。
各自治体もこの方針を受けて見直しを進め、在宅勤務者の保活環境は改善されつつあるのです。
【参考】
「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」(厚生労働省)
「多様な働き方に応じた保育所等の利用調整等に係る取扱いについて」(厚生労働省)
ただし“通勤時間がないと不利?”自治体ごとに違うルールに注意

通勤時間を就労時間に含めるかどうかは、自治体ごとに対応が異なります。
就労時間のみで判断する自治体もあれば、通勤・休憩時間を含めて認定する自治体もあります。お住まいの地域の基準を事前に確認しておくことが大切です。
【例】
- 世田谷区:通勤時間を含まない → 純粋な就労時間で判断
- 川崎市:通勤時間を含む → フルタイム相当なら標準時間認定されやすい
在宅勤務の場合、通勤時間がないため就労時間が短く見えやすく、短時間認定になってしまうケースもあります。そのため、就労証明書の記載内容や勤務実態の説明方法を工夫することがポイントです。
就労証明書の提出が必須|2024年度から様式統一!
保育園の入園申請時には、「保護者が実際に働いていること」を証明する書類として就労証明書の提出が必要です。
2024年度からは、こども家庭庁が全国共通の標準様式を策定し、すべての自治体でこの様式に対応しています。
また、マイナポータルを活用した「ぴったりサービス」を通じて、オンラインで保育所等の申請や就労証明書の提出ができる自治体も増えています。もちろん、これまで通り自治体の窓口や保育園から用紙を入手して手書きで提出することも可能です。
フリーランスや自営業など、勤務先がない方はご自身で就労証明書を記入できます。自治体によっては公式サイトから様式をダウンロードできる場合もありますので、確認しておきましょう。
ただし、「就労状況申告書」や「開業届」「確定申告書(控)」などの添付書類が求められる自治体もあります。提出前に、必要書類を自治体のホームページまたは窓口で確認しておくと安心です。
在宅・時短でも「標準時間認定(フルタイム)」で預けたい!3つのポイント

「標準時間認定(フルタイム)」で子どもを預けたいと考えている方も多いのではないでしょうか。ここでは、在宅勤務や短時間勤務でも標準時間認定を受けやすくするための3つのポイントを紹介します。
① リモート勤務でも、フルタイム勤務なら問題なし
在宅勤務であっても、所定労働時間がフルタイム(1日8時間程度)であれば、多くの自治体で標準時間認定の対象です。
認定基準は自治体ごとに異なりますが、おおむね月64時間以上の就労が要件とされています。
短時間勤務(時短勤務)の場合は、この就労時間を下回る可能性があるため、勤務時間の証明方法に注意しましょう。
② 「週1出社」や「コワーキング利用」を上手に活用
在宅勤務中心でも、週に1回程度の出社やコワーキングスペースの利用を行っている場合、その移動を通勤時間として算入できる自治体もあります。
「完全在宅よりも勤務実態が明確に伝わる」ため、勤務状況の説明資料としてプラスに働くケースがあります。申請前に自治体の取扱いを確認しておきましょう。
③ 勤務時間+休憩・移動を含めて「8時間程度」を意識
自治体によっては、休憩時間や通勤時間も含めて就労時間として認定する場合があります。
実際の勤務実態として、1日8時間程度の勤務が継続していることを示せれば、標準時間認定となるケースが多いです。勤務スケジュールや業務報告の記録を残しておくと、証明書の作成がスムーズになります。
リモートワークで点数を上げるための具体策

在宅勤務が一般化したとはいえ、自治体によっては在宅勤務世帯がわずかに不利になる場合もあります。
そのため、申請時には点数を補うための工夫や、保育の必要性を明確に示す対策をセットで進めることが重要です。
一時的に認可外保育園に預ける
認可外保育施設を利用していると、保育の必要性が高いと判断され、加点対象となる自治体もあります。
希望する認可保育園に入れなかった場合でも、まずは一時的に認可外保育園を利用し、その実績をもとに再申請することで入園の可能性が高まるケースも。手間はかかりますが、長期的には希望する認可保育園への道が開ける場合があります。
ベビーシッターを日常的に利用する
自治体によっては、ベビーシッターを定期的に利用している実績が評価される場合があります。
利用事業者から発行される「受託証明書」を提出することで、加点対象または参考資料として扱われるケースもあります。自治体によっては専用のフォーマットがあり、シッター側に記入を依頼する形です。
また、ベビーシッター利用費を一部補助している自治体もあります。補助申請には専用の書類が必要なため、事前に自治体のホームページや窓口で要件を確認しておきましょう。
新設園・小規模園を希望する
新設園や小規模保育園は、在園児がいない・定員に余裕があるといった理由から、比較的入園しやすい傾向があります。
ただし、新設園は見学が難しいこともあり、園の雰囲気や保育方針が分かりづらい面もあります。また、小規模園は満3歳で卒園するため、次の園探しが必要になる点にも注意が必要です。
これらの特徴を理解した上で、「入りやすさ」と「今後の保育環境」のバランスを見ながら希望園を選びましょう。
それでも保育園に落ちてしまったら?次の一手とリモートワークの両立術
認可保育園の倍率は依然として高く、工夫をしても入園できないことがあります。
そんなときは、認可外保育園・企業主導型保育園・ベビーシッター・ファミリーサポートなど、他の保育手段を組み合わせて乗り切ることが現実的です。
それぞれの費用感とメリットを整理しました。
| 項目 | 費用感 | 特徴・メリット |
|---|---|---|
| 認可外保育園 | 費用は施設によって設定されている。認可保育園より高めの傾向がある。 | 入園理由の制限がなく、空きが見つかりやすい。教育方針や保育内容が多様。 |
| 企業主導型保育園 | 認可保育園と同じくらいの費用。助成金あり。 | 自治体の枠にとらわれず利用可能。夜間・休日保育や一時預かり対応施設も多い。 |
| ベビーシッター | サービスにより異なる。入会費・年会費・オプション料などがある場合も。 | 予約が取りやすく、突発的な予定や家庭の事情にあわせて利用できる。 |
| 自治体のファミリーサポート | 施設により異なるが、費用は抑えめ。 | 短時間から利用でき、地域の支援者に子どもを預けられる。 |
上記以外にも、病児保育(お子さんの体調不良時に看護師等が対応)や、 訪問型保育サービス(保育士・ベビーシッターが自宅に来るタイプ)を活用する方法もあります。
リモートワーク中であっても、こうした支援をうまく組み合わせることで、仕事に集中しながら安心して子育てを続けることができます。
各ご家庭の状況やお子さんの年齢にあわせて、無理のない保育体制を整えていきましょう。
オンラインアシスタントフジ子さんではフルリモートのスタッフ募集中

フジ子さんでは、完全在宅で仕事ができるオンラインアシスタントを募集しています。
ご自身の都合にあわせてフレキシブルに働く時間を調整可能。フルリモートでも孤独じゃない、チーム制による働き方です。将来的に社員へのキャリアアップも目指せます。
実際に保育園に預けながら、フジ子さんで働いているパパママも多数。お子さんの突然の体調不良や行事など、柔軟にスケジュール調整しながらキャリアを築いています。
先輩パパママと一緒に、あなたもオンラインアシスタントとして働いてみませんか?
まとめ
在宅勤務でも、条件を満たせば保育園に入園できる可能性は十分あります。
厚生労働省の方針により、在宅勤務やフリーランスも就労として認められるようになりました。
通勤時間の扱いや就労証明書の書き方を工夫し、必要に応じてベビーシッターなどを活用すれば、標準時間認定や加点につながるケースもあります。
制度を理解し上手に活用することで、仕事と子育てを両立できるリモートワーク保活を実現していきましょう。