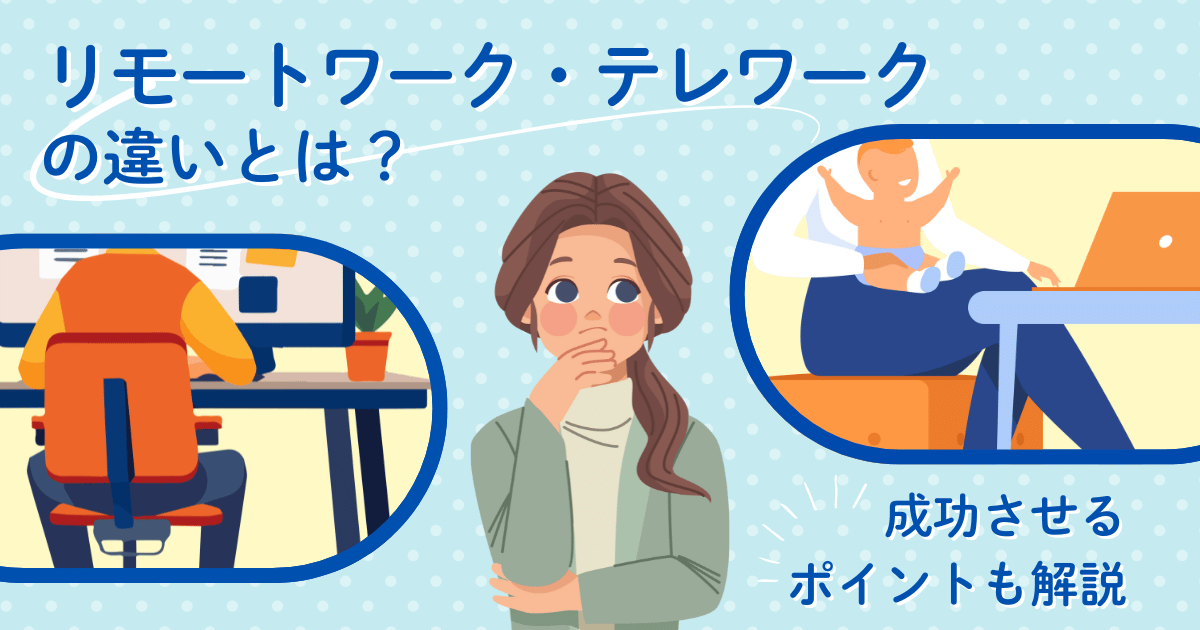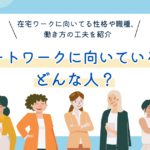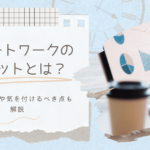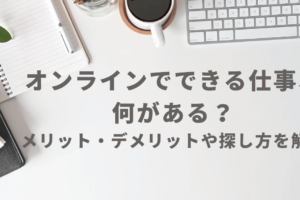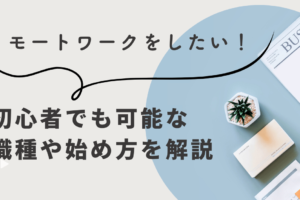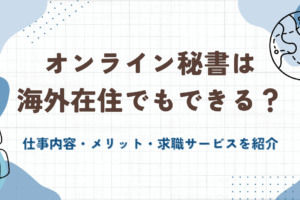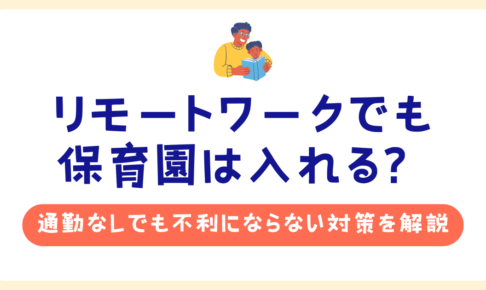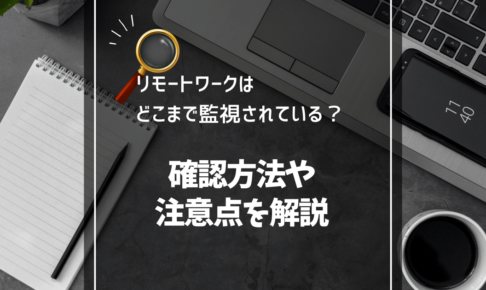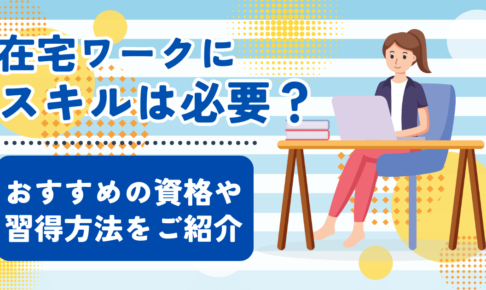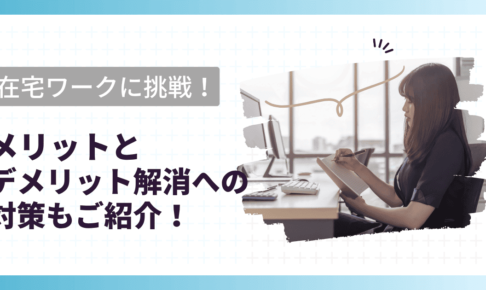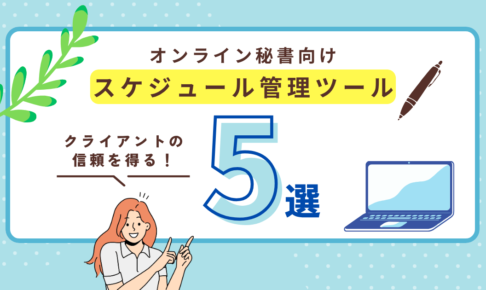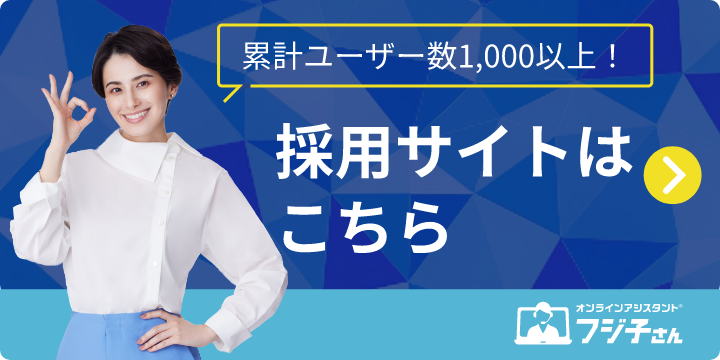リモートワークやテレワークといった働き方が広まりつつある現代、これらの違いや特徴を正しく理解することは、柔軟な働き方を求めるビジネスパーソンにとって重要です。
本記事では、リモートワークとテレワークの定義の違いや、各働き方が企業や従業員に与える影響を解説します。
リモートワークとテレワークの定義と違い

「リモートワーク」と「テレワーク」は、いずれもオフィス以外の場所で働くスタイルを指しますが、厳密には意味が異なります。
- リモートワーク:物理的な「働く場所」に焦点を当て、会社以外の任意の場所で働くことを指します。主に実践的な業務において使われる表現です。
- テレワーク:情報通信技術を活用し、時間や場所に縛られず働く柔軟な働き方を意味します。制度としての導入も含めた広義の概念です。
テレワークは1970年代のアメリカで概念が生まれ、日本では1980年代に政府主導の推進により導入されました。インターネットの普及や新型コロナウイルス感染症の影響により、どちらの働き方も急速に広まりました。
企業にとってはオフィスコストの削減や、全国どこからでも優秀な人材を確保できるといったメリットがあり、従業員にとっても通勤時間の削減やワークライフバランスの向上など多くの利点があります。
テレワークとは
テレワークは主に以下の3つの形態に分類されます。
- 在宅勤務:自宅で業務を行うスタイルで、最も多く導入されている形態。集中しやすく、家庭の事情に合わせやすいという利点があります。
- モバイルワーク:外出先や移動中の電車、カフェ、出張先など、場所を選ばず働ける柔軟性がある形。営業職やフィールドワークを伴う職種に適しています。
- サテライトオフィス勤務:企業が設置した本社以外の小規模オフィスで勤務するスタイル。通勤時間の短縮とオフィスの機能を両立できます。
総務省の調査によると、2021年時点でテレワーク導入企業は全体の51.9%にのぼりました。導入目的としては「非常時の業務継続」「人材確保」「生産性向上」が挙げられており、今後も継続的に活用されることが見込まれます。(参考:令和3年通信利用動向調査の結果/総務省)
リモートワークとは
リモートワークは、在宅勤務やコワーキングスペース、カフェなどオフィス以外の場所で働くスタイルです。テレワークとほぼ同義で使われることもありますが、特に「物理的な場所」に注目した表現であり、実務ベースで使われる傾向です。
デジタルツールの発展により、リモートワークが可能な職種は広がりを見せています。特に以下のような職種では導入が進んでいます。
- ITエンジニア:システム開発や運用をオンラインで進められるため、高い適合性があります。
- グラフィック・UI/UXデザイナー:FigmaやAdobe XDなどのツールを活用し、リモートでの共同作業が可能です。
- ライター・翻訳者:文章や翻訳業務は個人作業が多く、場所に縛られずに作業できるのが特長です。
クラウドベースのプロジェクト管理ツールやチャットツールの普及により、チームとの連携もスムーズになってきました。Zoom、Slack、Google Meet、Notion、Asanaといったツールの活用が、業務の効率化に貢献しています。
両者の違い
| 項目 | リモートワーク | テレワーク |
| 焦点 | 働く場所 | ICT活用・働く方法 |
| 範囲 | 実務的・実践ベース | 制度・概念を含む広義 |
| 起源 | インターネット普及以降 | 1970年代アメリカ |
| 適用職種 | デジタル業務が中心 | 幅広い職種に対応 |
リモートワークを廃止する企業も
リモートワークは柔軟な働き方を実現しますが、すべての企業にとって最適とは限りません。一部の企業ではリモートワークを廃止する動きも…。その背景には以下のような理由があります。
- コミュニケーションの難しさ:オンラインでは対面よりも微妙なニュアンスが伝わりにくく、チームワークに支障が出ることがあります。
- 生産性のばらつき:自己管理能力に差があり、社員によって生産性に差が出るケースがあります。
- 企業文化の希薄化:社員間の交流が減ることで、会社としての一体感や理念の浸透が弱まる懸念もあります。
実際にある大手企業では、リモートワークによる業務遅延や情報の非対称性が課題となり、出社体制に戻す決断をしました。ただし、全体を一律に出社に戻すのではなく、ハイブリッド型の導入に移行する企業も多く見られます。
リモートワークとテレワークのメリット

これから在宅勤務を始めたい方や柔軟な働き方を目指す方にとって、リモートワークやテレワークは大きな魅力があるもの。ここでは、求職者・働く個人の視点からメリットを整理してご紹介します。
- 通勤が不要になり、時間と体力を節約できる
- 育児・介護との両立がしやすく、生活スタイルに合わせやすい
- 自宅やカフェなど、集中しやすい環境で働ける
- 地方や海外に住みながら都市部の仕事に応募できる
- 自己裁量が高まり、生産性や満足度が上がるケースも多い
※さらに詳しいメリットを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
リモートワークのメリットとは?デメリットや気を付けるべき点も解説
リモートワークとテレワークのデメリット
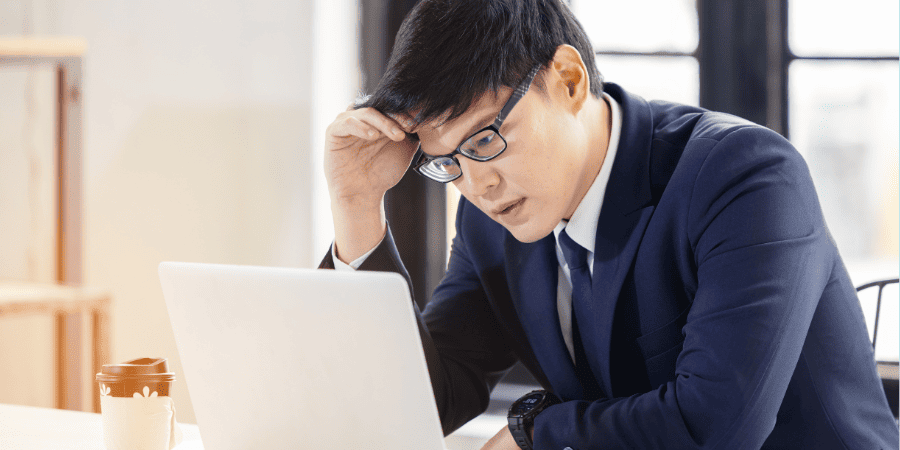
自由な働き方にはメリットだけでなく、向き・不向きもあります。実際に働き始める前に、デメリットや注意点も把握しておきましょう。
- 孤独感を感じやすく、人とのつながりが薄れがち
- 仕事とプライベートの境界が曖昧になり、オンオフの切り替えが難しい
- 自己管理能力が必要で、だらけやすい人には不向きな面も
- 評価や成果が見えにくく、正当な評価が得にくいこともある
※さらに詳しいメリット・デメリットを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】
リモートワークのメリットとは?デメリットや気を付けるべき点も解説
リモートワークに向いている職種

リモートワークに適した職種は多岐にわたり、それぞれの業務特性や必要なスキルセットに応じて柔軟に対応できるものが多く存在します。
ここでは、オンラインアシスタント、ITエンジニア、デザイナー、ライター、翻訳者など、具体的な職種を取り上げ、それぞれがリモートワークに向いている理由や成功のポイントについて詳しくご紹介します。
オンラインアシスタント
オンラインアシスタントは、企業のスケジュール管理や資料作成、メール対応などをオンラインでサポートする職種です。
業務にはGoogle WorkspaceやSlack、Zoomなどのツールを使うため、基本的なITスキルが求められます。マルチタスク対応力や自己管理能力、丁寧なやりとりができる方がぴったりです。
ITエンジニア/プログラマー
システム開発やプログラミングはクラウド環境で進めやすく、リモートワークと相性の良い職種です。GitHubやタスク管理ツールを活用し、場所に縛られずにチームでの開発が可能です。フリーランスや副業でも働きやすい分野といえます。
グラフィック・Webデザイナー
デザインツールがあればどこでも業務が行えるため、在宅でもスムーズに働ける職種です。FigmaやPhotoshop、Illustratorなどを活用し、オンライン上でクライアントとのやり取りやデザインを共有します。
ライター・翻訳者
文章や翻訳の仕事は一人で完結できる業務が多く、リモートに適しています。成果物ベースで評価されやすく、自分のペースで働きたい人や静かな環境で集中したい人に向いているでしょう。
【関連記事】
【徹底解説】リモートワークの探し方&安全に仕事を見つけるポイント
リモートワークを成功させるポイント3つ

リモートワークを快適かつ効率的に続けるには「情報共有の徹底」「プライベートと仕事の切り分け」「適切なツールの導入」という3つの基本が欠かせません。ここでは、それぞれのポイントを実践的な視点から解説します。
ポイント1:情報共有を徹底する
リモート環境では、対面での雑談や偶発的な情報交換がないため、意識的な情報共有が重要です。まずは、SlackやMicrosoft Teamsなどのコミュニケーションツール、TrelloやAsanaなどのタスク管理ツールを適切に選び、運用ルールを整えることが必要です。
定期的なオンラインミーティングや進捗報告の場を設けると業務の透明性が高まり、チーム間の認識ずれを防げます。また、ドキュメントやレポートの共有にはGoogleドライブやNotionなどが役立つでしょう。こうした工夫により、リモートでも一体感のあるチーム運営が可能です。
ポイント2:プライベートと切り分ける
リモートワークでは、自宅が職場となるため、仕事と私生活の境界が曖昧になりがちです。そのため、自宅内に専用の作業スペースを設けたり、毎日同じ時間に仕事を開始・終了したりといったルーティンを整える必要があります。
また、1〜2時間に1回程度の休憩を挟み、集中力をリセットする習慣も有効です。こうした時間管理は、パフォーマンスの安定化に加えて、ストレス軽減やメンタルヘルスの維持にもつながるでしょう。オンとオフを意識的に切り替えることで、リモートワーク特有の「常に仕事モード」になりがちな状態を避けられます。
ポイント3:適切なツールを導入する
生産性の高いリモートワークを実現するには、業務に合ったツールの導入が不可欠。業務内容やチーム体制に応じて、チャット、ビデオ会議、ファイル共有、プロジェクト管理など、それぞれの目的に合ったツールを使い分けましょう。
導入時には、ツールの操作性や既存システムとの互換性、セキュリティ対策、コストなどを基準に検討すると失敗を防げます。また、ツールを使いこなすためには、従業員へのレクチャーや使い方のガイド整備も重要です。
導入後も定期的に使い方を見直し、必要に応じて改善・アップデートを行うことで、継続的なパフォーマンス向上につながります。
リモートワークとテレワークに関連する質問3選

リモートワークに興味はあっても、不安や疑問を持つ方は多いでしょう。ここでは、よくある3つの質問に簡潔にお答えします。
本当にリモートワークできている人はどのくらいいる?
2023年時点で、日本国内の労働者のおよそ30%がリモートワークを実施しているとされています。特にIT業界やデザイン・金融などでは普及が進んでおり、完全リモートで働いている人も少なくありません。今後は出社と在宅を組み合わせた「ハイブリッド型」の働き方が主流になると予想されています。
リモートワークの孤独感やストレスを解消する方法は?
在宅勤務では、人との交流が減ることで孤独やストレスを感じやすくなります。その対策としては、以下のような工夫が有効です。
- 定期的なオンラインミーティングで交流を持つ
- 作業時間と休憩時間を明確に分ける
- 雑談の場や社内チャットを活用する
- 企業側のメンタルヘルス支援制度を利用する
簡単な仕組みづくりで、心理的な負担を軽減できます。
フルリモートで働ける仕事は実際にある?
結論から言うと、フルリモートで働ける仕事はあります。たとえばITエンジニア、Webデザイナー、ライター、翻訳者、デジタルマーケターなどは、フルリモートに適した職種です。こうした仕事では、オンライン上での業務管理やチーム連携がしやすく、オフィスに通う必要がありません。
自己管理能力と安定した通信環境があれば、フルリモートでも高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。実際に多くの企業がフルリモート対応の求人を出しており、選択肢は広がっているのが現状です。
【関連記事】
フジ子さんのオンラインアシスタントとして働くのもおすすめ!

在宅ワークを検討している方にとって「フジ子さん」のオンラインアシスタントという働き方は有力な選択肢の一つです。ここでは、フジ子さんが提供する仕事内容や環境、サポート体制についてご紹介します。
フジ子さんとは
「フジ子さん」は、企業のバックオフィス業務をオンラインで支援するサービスです。多様な業界のクライアントを対象に、業務の効率化や負担軽減を目的としたアシスタントサービスを展開しています。
仕事内容
オンラインアシスタントとしての業務は多岐にわたります。一例として以下のような業務があります。
- スケジュール管理・会議の調整
- メール対応・文書作成
- 資料整理・データ入力
- リサーチ業務 など
業務を円滑に進めるために、基本的なITリテラシーに加え、コミュニケーション能力や時間管理スキルが求められます。
フジ子さんで働くメリット
フジ子さんで働く魅力は、柔軟な働き方ができるだけでなく成長できる環境が整っている点です。
- 柔軟な業務時間
家庭との両立や副業・兼業(条件あり)も可能など、ライフスタイルにあわせて働けます。詳しくは採用サイトをご覧ください。 - 働きやすい環境
チーム制でほかのアシスタントと一緒に業務を行うため、相談がしやすい環境です。業務ができない日は、ほかのアシスタントに代わりに対応してもらうなどお互いに協力しあっています。
充実したサポート体制
初めてリモートワークする方にも安心のサポートがあります。業務の中では先輩スタッフからのサポートを受けながらスムーズに業務に慣れることができるでしょう。
また、テレワーク環境下においても、心と体の健康に十分配慮した環境を整備してきたこと等が評価され、「健康優良企業」として認定されています。
オンラインアシスタント®「フジ子さん」、健康優良企業「銀の認定」を取得
リモートであっても「一人で抱え込まない」体制が整っており、長期的に働ける環境が築かれています。
まとめ

リモートワークとテレワークは似て非なる概念であり、違いを理解することが重要です。それぞれの特性、メリット・デメリットを把握し、自分に合った働き方を見つけることが、これからのキャリア形成において欠かせません。
また、リモートワークに向いている職種や成功のためのポイントも踏まえて、自身の適性や希望と照らし合わせながら仕事を探すことが大切です。
そして、リモートワークを始めたい方には「フジ子さん」のようなオンラインアシスタントの仕事も選択肢の一つとして検討する価値があります。柔軟な働き方を実現し、自分らしいキャリアを築いてみてはいかがでしょうか。