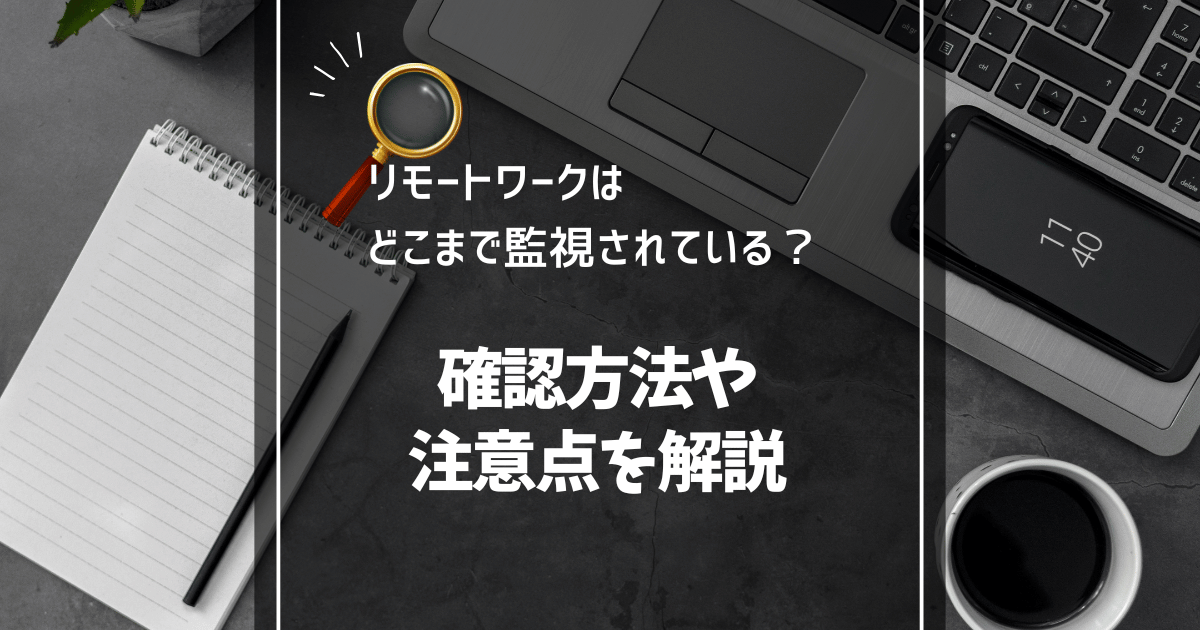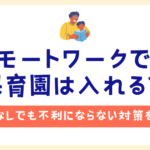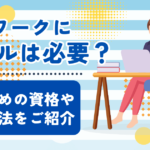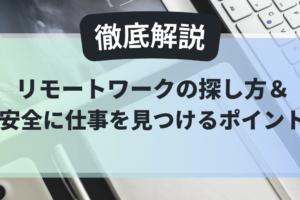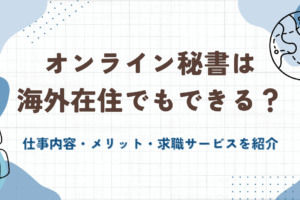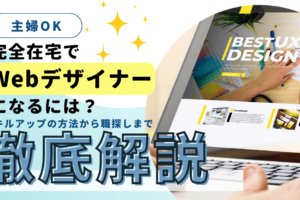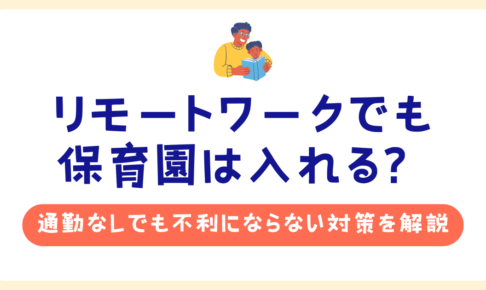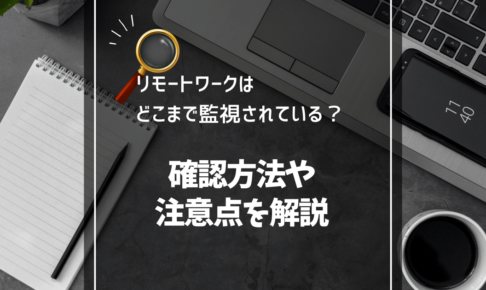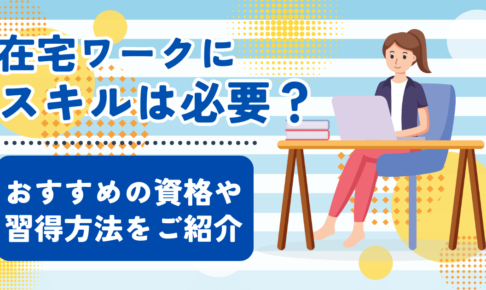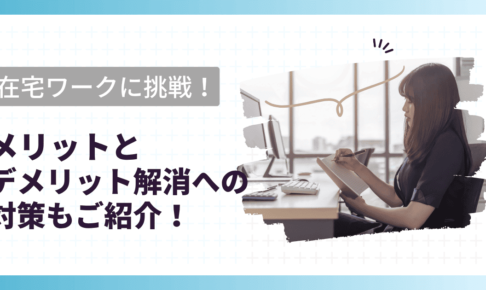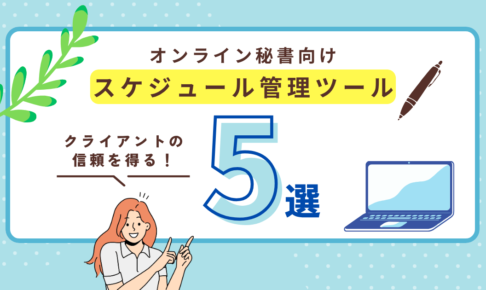リモートワークを希望しているものの、会社から貸与されたPCを使用する場合、「監視されていることがある」と聞いて不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、リモートワーク中に会社からどの程度の監視が行われているのか、そしてそれは法的に問題がないのかについて解説します。安心してリモートワークを行うために、ぜひチェックしておきましょう。
なぜ企業はリモートワークを監視するの?

リモートワークの普及に伴い、企業が社員の勤務状況を把握するために「監視ツール」や「ログ管理システム」を導入するケースが増えています。
一見すると「監視」と聞くと抵抗を感じるかもしれませんが、その目的は社員を疑うためではなく、業務の効率化や安全性の確保など、組織運営上の必要性に基づくものです。
ここでは、企業がリモートワークを監視する主な理由を解説します。
業務や稼働状況をきちんと把握するため
オフィス勤務とは異なり、リモート環境では上司やチームメンバーが直接状況を確認できません。
そのため、業務ログやPCの使用状況を可視化することで、仕事の進捗や稼働状況を正確に把握する狙いがあります。これにより、業務の偏りやサポートが必要な社員を早期に把握できるメリットもあります。
セキュリティ対策や情報漏えいを防ぐため
社外から社内システムにアクセスする機会が増えるリモートワークでは、情報漏えいや不正アクセスのリスクが高まります。
企業はセキュリティソフトや監視ツールを用いて、アクセス履歴やファイル操作を管理することで、機密情報を守る体制を整えています。
労働時間を見える化して長時間労働を防止するため
リモートワークでは「つい働きすぎてしまう」ケースも少なくありません。
そこで、企業はPCの稼働ログや勤務時間の自動記録を通して、労働時間を適正に管理し、長時間労働を防ぐ仕組みを導入しています。これは社員の健康を守る目的も兼ねています。
人事評価をより公平にするため
オフィスにいないと「どれだけ働いているのか」が見えづらくなりがちです。
そのため、勤務データや成果物のログを活用し、客観的な評価基準に基づいて人事評価を行う企業も増えています。これにより、リモート勤務でも不公平感のない評価が実現しやすくなります。
従業員の体調やメンタルの変化に気づくため
勤務ログやチャットの反応などから、従業員のコンディションの変化を早期に察知することも監視の目的のひとつです。
業務の遅れや連絡頻度の変化などを分析し、メンタル不調の兆しをつかむことで、早めのサポートにつなげられます。
リモートワークの監視は法律的に問題ないの?
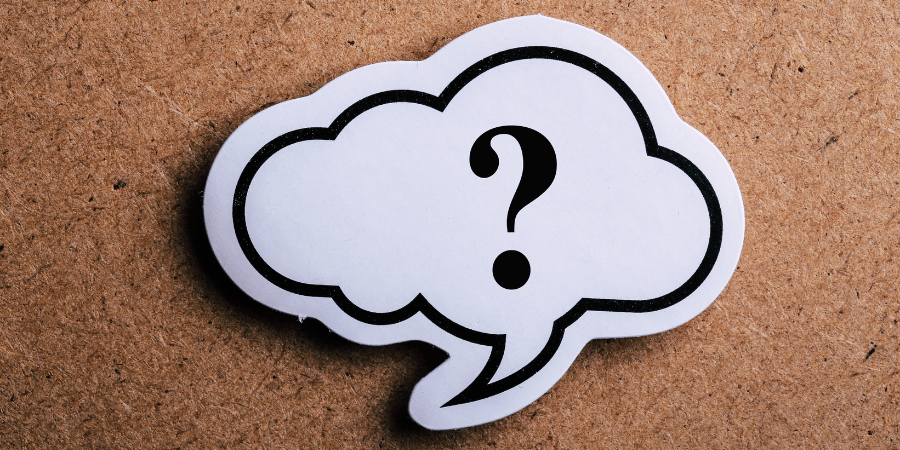
「会社に監視されているのでは?」と感じたとき、まず気になるのが法的な問題がないのかという点ではないでしょうか。
結論から言えば、一定の目的とルールに基づいた監視であれば、法律上問題はありません。企業は労働者の労働時間を正確に把握し、適切な労務管理を行う義務があるためです。
ただし、過剰な監視やプライバシーを侵害するような行為は、法的にも倫理的にも問題となる可能性があります。
法律では労働時間の把握が必須
リモートワークであっても、労働基準法の対象となる労働者には、通常の職場勤務と同じように労働時間の管理義務が発生します。
つまり、企業は「いつからいつまで働いたのか」を正確に把握しなければならず、そのための手段としてパソコンのログや通信記録などの客観的データを活用することが認められています。
厚生労働省の『テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン』では、次のように明記されています。
使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること (1) 原則的な方法 ・使用者が、自ら現認することにより確認すること ・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること
一方で、業務の性質上どうしても客観的な把握が難しい場合には、自己申告制も認められています。ただしその際は、企業側が定期的に申告内容を確認し、不自然な点があれば修正を求めるなど、適正な運用を行うことが条件です。
つまり、企業によるリモートワーク中のログ取得や勤務時間管理は、法律に基づいた正当な行為であるといえます。
倫理的にはお互いの信頼と節度ある対応が大切
とはいえ、法的に認められているからといって、過剰な監視が許されるわけではありません。
たとえば、勤務中に常時カメラをオンにして社員を映し続けるような行為は、プライバシー権の侵害にあたる可能性があります。
また、心理的なストレスや緊張状態を引き起こし、生産性の低下やメンタル不調につながるリスクも指摘されています。
企業に求められるのは、「監視」ではなく「見守り」の姿勢です。つまり、社員を疑うのではなく、安全で安心して働ける環境を整えるための管理にとどめることが理想的とされています。
企業はリモートワークをどうやって監視しているの?

企業がリモートワーク中の社員を監視するといっても、必ずしも「常に監視カメラで見張っている」というようなものではありません。
多くの場合は、業務の進捗管理や労務管理、セキュリティ対策の一環として、適切な範囲で勤務状況を把握する仕組みが導入されています。
ここでは、実際に企業がどのような方法でリモートワーク中の状況を確認しているのかを見ていきましょう。
業務用ツールでパソコンの操作をチェック
もっとも一般的なのは、業務用の管理ツールやソフトウェアを使ってパソコンの稼働状況を記録・分析する方法です。
たとえば、ログイン・ログアウトの時間、アプリの使用履歴、ファイルの操作履歴などを自動で記録することで、勤務時間や作業状況を客観的に把握できます。
こうしたデータは、労働時間の記録やセキュリティ対策のために活用されることが多く、社員のプライベートを監視することが目的ではありません。
企業によっては、キーボードやマウスの操作が一定時間なかった場合にアラートを出すなど、業務効率やサポートの必要性を判断するための仕組みを整えている場合もあります。
定例ミーティングや1on1で進捗や様子を確認
ツールだけでなく、定期的なコミュニケーションを通じて状況を把握する方法も多くの企業で取り入れられています。
週次ミーティングや1on1(ワン・オン・ワン)面談などで、仕事の進捗や課題、体調などを共有し合うことで、リモート環境でもチームのつながりを維持しています。
このような取り組みは「監視」というよりも、信頼関係を保ちながら円滑に仕事を進めるためのサポート体制といえるでしょう。
特に近年では、成果だけでなくプロセスやメンタル面のフォローを重視する企業も増えており、過度な監視よりも“見守り型”の管理が主流になりつつあります。
監視ツールでどこまでバレる?

企業が導入する監視ツールは、業務効率やセキュリティを確保するためにさまざまな機能を備えています。
しかし、「どこまで見られているのか?」「プライベートな操作まで把握されるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。
実際のところ、ツールによって取得できる情報の範囲は異なりますが、監視の目的はあくまで業務上の安全と管理のためです。ここでは、一般的に確認・記録される項目を紹介します。
出勤・退勤や在席・離席のタイミング
もっとも基本的なのが、勤務時間の把握です。
PCのログイン・ログオフや、操作があった時間帯などをもとに、出勤・退勤・休憩・離席のタイミングを自動的に記録します。これにより、自己申告よりも正確に労働時間を管理でき、長時間労働の防止にもつながります。
どんなアプリを使っていたかの操作ログ
監視ツールの多くは、どのアプリケーションをどのくらいの時間使用していたかを記録する機能を持っています。
たとえば、業務用ツール(Excel、Teams、Slackなど)の使用時間や、非業務的なアプリ(SNSや動画サイトなど)を開いていた時間が可視化される場合も。これにより、業務の進捗や作業効率を客観的に確認できるようになります。
使用ソフトやWebのアクセス履歴
さらに詳細なツールでは、どのWebサイトやソフトウェアにアクセスしたかといった履歴を収集することもできます。
これは、業務に関係のないサイトの閲覧を制限したり、外部との不正な通信や情報漏えいを防止したりすることが目的です。
ただし、個人情報や私的利用の詳細まで企業がチェックするケースは少なく、目的外の監視は基本的に行われません。
画面のスクリーンショット(画面キャプチャ)
一部の監視システムでは、定期的にPC画面をキャプチャして保存する機能も搭載されています。業務中にどのような作業を行っていたかを確認できるほか、不正アクセスやデータ流出時の証拠保全にも役立つ機能です。
ただし、スクリーンショットの取得はプライバシーへの影響が大きいため、導入時には社員への明確な説明と同意が求められます。
情報漏えいや不正な操作のチェック
セキュリティを重視する企業では、USBメモリの接続や外部送信、社外メールの添付ファイルなどを監視し、情報漏えいのリスクを防いでいます。
また、社内システムへの不正アクセスやデータ持ち出しを検知する機能を備えたツールも。こうした監視は、社員を疑うためではなく、会社全体の情報資産を守るために行われています。
キーログ(キーボードの入力履歴)
一部の高機能ツールには、キーボードの入力内容(キーログ)を記録する機能も存在します。これは、内部不正の抑止やセキュリティリスクの調査を目的としたもので、通常は厳重なルールのもとで運用されます。
ただし、キーログの取得は非常にセンシティブな監視方法であり、一般的な企業で常時導入されているケースは多くありません。
自分のPCが監視されているかを確認する方法
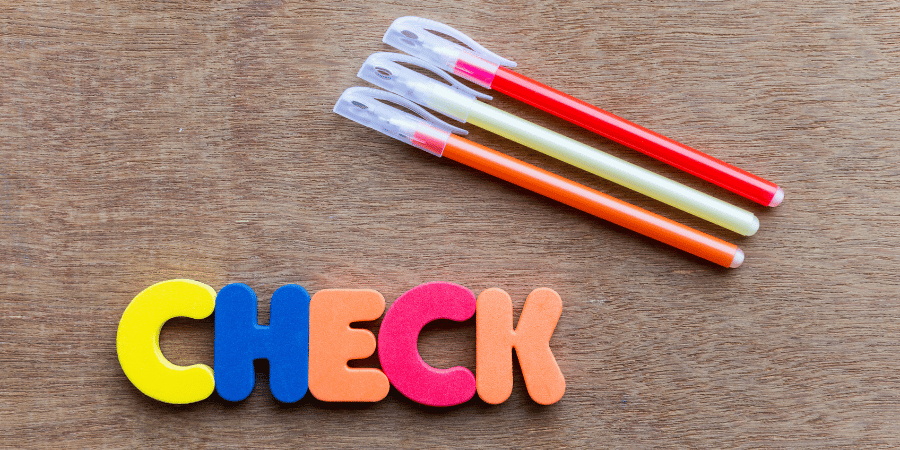
「もしかして、自分のパソコンも監視されているのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。
実際、会社によってはセキュリティや労務管理の一環としてツールを導入している場合がありますが、すべての操作が見られているわけではありません。
ここでは、自分のPCがどの程度監視されているのかを確認するための主な方法を紹介します。
社内ルールやITポリシーをしっかり確認
まず確認すべきは、社内のルールやITポリシーです。
多くの企業では、セキュリティやプライバシーに関する取り決めを明文化しており、監視の範囲や目的についても明記されています。
社内ポータルや入社時の誓約書、情報セキュリティハンドブックなどを見返すことで、どこまでが会社の管理対象なのかを知ることができます。
情報システム部などの担当部署に聞いてみる
もし明確な情報が見つからない場合は、情報システム部や人事部などの担当部署に直接確認するのが確実です。
「業務で使っているPCにはどのような管理が行われているのか」「ログはどのように活用されているのか」など、具体的に質問してみましょう。
不安をそのままにせず、会社側の意図や目的を理解することが、安心して働くための第一歩です。
タスクマネージャーで裏で動いているアプリをチェック
Windowsの場合、タスクマネージャーを開くと、現在PC上で動作しているアプリやプロセスを確認できます。
ここに見慣れないソフトや常駐プログラムがある場合、それが監視ツールである可能性もあります。
ただし、業務用セキュリティソフトや通信ツールなど、監視目的ではないプログラムも多く存在するため、安易に削除したり停止したりしないよう注意しましょう。
インストールされているアプリ一覧から探す
「設定」や「コントロールパネル」から、インストール済みのアプリ一覧をチェックするのも一つの方法です。
たとえば「RemoteView」「ActivTrak」「Teramind」など、一般的な管理ツール名が確認できる場合は、会社側で監視または管理を行っている可能性があります。
ただし、企業貸与のPCであれば、これらはセキュリティ管理の一環として正当に導入されているケースがほとんどです。
自分の私物PCなら監視の範囲は限定的に
例えばこのブログを運営するフジ子さんであれば、基本的に自分の私物PCを使用して業務を行うスタイルです。
そのため、会社がパソコンに直接監視ツールをインストールすることはなく、ガイドラインの周知徹底や独自システムによる業務管理を行っています。
こうした運用であれば、業務の透明性を保ちながらも、プライバシーを尊重した働き方が可能です。
貸与PCを使用する場合に比べて、私物PCを用いる環境では監視の範囲が限定され、より安心して業務に専念できると言えるでしょう。
PCのカメラやマイクって監視に使われているの?

リモートワーク中、「もしかしてパソコンのカメラやマイクで見張られているのでは…?」と不安に感じる方もいるでしょう。
実際、一部の監視ツールにはカメラやマイクへのアクセス機能を持つものも存在します。
しかし、常時監視しているケースはごくまれであり、企業が勝手に映像や音声を取得することは、法的にも倫理的にも問題となる可能性があるのです。
ここでは、カメラやマイクが監視に使われる場合と、その対策方法を紹介します。
カメラやマイクを通じて監視されるケースもある
カメラやマイクが利用されるケースとしては、オンライン会議やセキュリティ確認のために一時的にアクセスする場合がほとんどです。
たとえば、社員証の代わりに顔認証でログインするシステムを導入している企業では、本人確認のためにカメラが起動することがあります。
また、不正アクセスや端末の乗っ取りなどが疑われる場合に、IT部門が一時的に端末の映像・音声情報を確認することもあります。
ただし、こうした操作は明確な社内規定と本人の同意のもとで行われるのが原則です。無断で常時カメラやマイクを起動して監視する行為は、プライバシー侵害や不正アクセス禁止法違反にあたるおそれがあり、企業としてもリスクが高い行為といえます。
対策①:カメラは専用カバーや付箋でふさぐ
不安な場合は、カメラカバーや簡易的な付箋などでレンズ部分を物理的にふさぐのがもっとも手軽で確実な方法です。
オンライン会議のときだけカバーをスライドさせて開けるタイプの製品も多く、ノートPCや外付けカメラに簡単に装着できます。
また、カメラが自動で起動した際にはランプが点灯する機種が多いため、不審な動作を早期に察知する目安にもなります。
対策②:マイクにはダミープラグで対処する方法も
マイクからの盗聴や無断録音が心配な場合は、ダミープラグ(フェイクのイヤホンジャック)を差し込むことで、物理的にマイクを遮断する方法があります。
これは、外部マイク端子が常に使用中の状態となり、内蔵マイクが自動的に無効化される仕組みです。また、設定画面から「マイクアクセスを制限」することで、特定のアプリのみ使用を許可するといったソフト面での制御も可能です。
いずれにしても、過度に不安になる必要はありませんが、自衛のための基本的な対策をとっておくことで安心感が増すでしょう。
監視ツールを回避する方法はある?※注意点あり
「監視されるのはイヤだから、ツールを止めたい」と思う人もいるかもしれません。しかし、監視ツールを自分で削除・無効化するのは避けるべきです。
多くのツールは利用者が勝手に操作できない仕組みになっており、削除には管理者パスワードが必要だったり、操作履歴が管理側に通知されたりする場合も。無理に停止すると、社内システムにアクセスできなくなるなど、業務に支障が出るリスクもあります。
また、ツールを無断で削除してトラブルが起きた場合、責任を問われる可能性もあります。監視ツールは社員を疑うためのものではなく、情報漏えいやセキュリティ事故を防ぐための仕組みです。
通常どおり業務を行っていれば問題になることはほとんどありませんので、過度に心配する必要はありません。
まとめ
リモートワークでの監視は、社員を監視するためというより、業務の安全性や情報保護のための仕組みとして導入されているケースが多くあります。
たしかにパソコンの操作ログやアクセス履歴を取得されると不安を感じますが、通常どおり業務を行っていれば問題になることはほとんどありません。
大切なのは、監視の目的や社内ルールを正しく理解し、会社と従業員の信頼関係を保つことです。不安な点があれば、担当部署に確認することで安心して仕事に取り組めるでしょう。
また、すでに紹介したように、当ブログを運営するフジ子さんのように私物PCを使用して働くスタイルであれば、会社が直接監視ツールを導入するのではなく、ガイドラインの周知や独自システムによる管理を通じて、安全性と自由度の両立を図っています。
自分の働き方に合った環境づくりを意識しながら、信頼をベースにしたリモートワークを実現していきましょう。