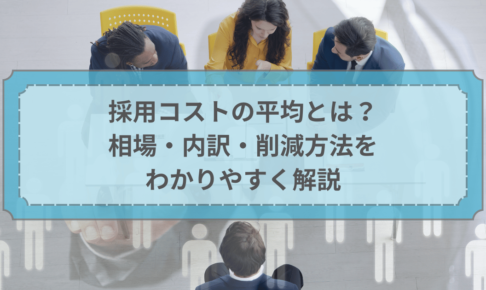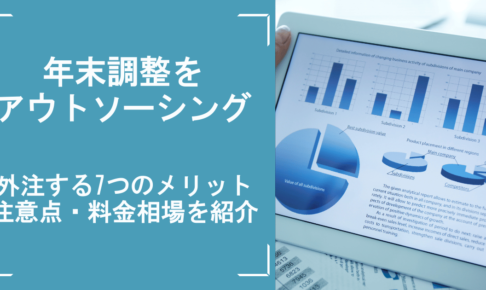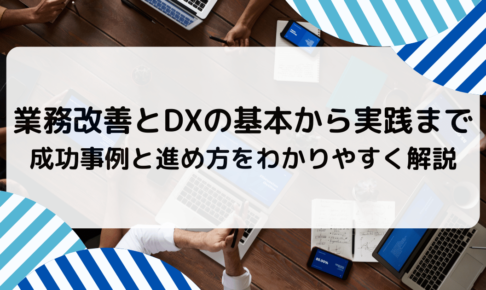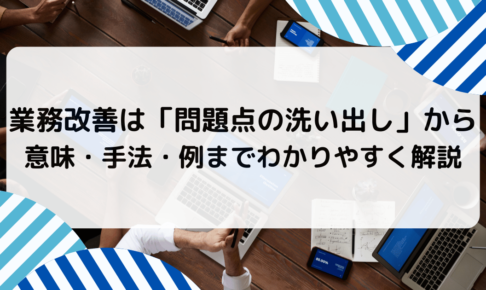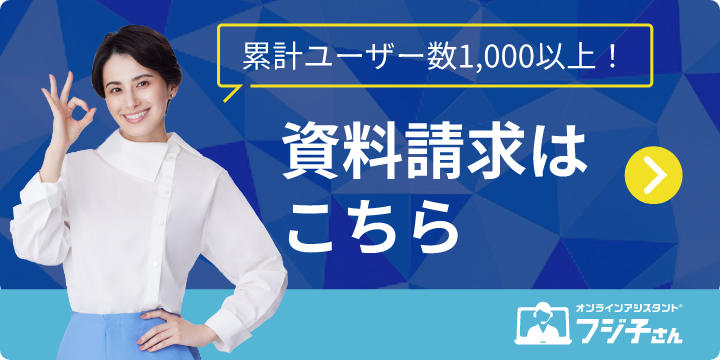プレスリリースは、企業や団体が自社の活動を社会に伝えるための重要な手段です。うまく活用すれば、広告に頼らずともメディアを通じて多くの人に情報を届けられます。
とはいえ、「プレスリリースを発信したいけれど、どこから手をつければいいのか分からない」といった悩みを抱える方は少なくありません。
特に中小企業やスタートアップでは、広報専任の担当者がいないことも多く、「内容のまとめ方や書き方に自信が持てない」と感じるケースもあります。
本記事では、プレスリリース初心者向けに、目的・メリット・書き方・注意点などをわかりやすく解説。さらに、「忙しくて自分たちでは対応が難しい」という方に向けて、外注を活用するという選択肢についてもご紹介します。
目次
プレスリリースとは?

プレスリリースは、広報活動のなかでも基本となる手法の1つです。まずはプレスリリースの基礎と、似た言葉との違いを整理しておきましょう。
プレスリリースの基礎知識
プレスリリースとは、企業や団体が自分たちの活動やニュースを社会に知らせるために出す「公式のお知らせ文」です。
新聞・テレビ・雑誌・Webメディアなどの記者に向けて発信し、ニュースや記事として取り上げてもらうことを目的としています。
プレスリリースは広告ではありません。宣伝のように商品やサービスを強くアピールするのではなく、「新しい取り組み」や「社会的に意義のある情報」を、事実に基づいて正しく伝えることが大切です。
ニュースリリース・広告・PRとの違い
プレスリリースとよく混同されやすい言葉を整理しておきましょう。
- ニュースリリース
プレスリリースとほぼ同じ意味で使われることが多く、呼び方の違い程度と考えてOKです。
- 広告
お金を払って枠を買い、内容を自由にコントロールできる発信手段。宣伝色が強く、必ず掲載されるのが特徴です。プレスリリースは無料で出せる代わりに「ニュースとして価値があるか」を記者に判断されます。
- PR(広報活動)
企業と社会の信頼関係を築くための活動全般を指す言葉。その一部に「プレスリリース」という手法が含まれるイメージです。
プレスリリースの目的・役割

プレスリリースを出す一番の目的は、自社の活動やニュースを社会に広く伝え、正しく知ってもらうことです。
「新商品を発売した」「イベントを開催する」「新しい取り組みを始めた」といった情報を、新聞やWebメディアなどを通じて発信することで、より多くの人に自社の動向を広められます。
さらに、新聞やWebメディアに取り上げてもらえば、情報がより認知され、世間一般に信頼感をもって受け止めてもらいやすくなります。
プレスリリースは、企業や団体の活動を社会に伝え、信頼を積み重ねていく広報ツールという役割をもっているのです。
プレスリリースのメリット・効果

プレスリリースを活用する効果は、単なる「お知らせ」を超えて企業に大きなメリットをもたらします。ここでは代表的なポイントを解説します。
メディアに掲載されることで大きな宣伝効果が得られる
新聞やテレビ、Webニュースなどで記事として取り上げられると、広告を出した場合と同じくらい、あるいはそれ以上の宣伝効果を得られることがあります。
加えてプレスリリースは「ニュース記事」として扱われるため、宣伝よりも信頼性が高く、読者にも受け入れられやすいのが特徴です。
低コストで多くの人に情報を届けられる
広告を出すには高額な費用がかかりますが、プレスリリースは自社サイトに掲載したり、配信サービスを使ったりするだけで、低コストで広く情報を届けられます。スタートアップや小規模な会社でも始めやすく、コストパフォーマンスの高い広報手段です。
信頼性やブランドイメージが高まる
メディアに取り上げてもらった場合、企業の発表が「第三者によって紹介された情報」として伝わります。その結果、「信頼できる会社」「注目されている企業」という印象を与えやすくなり、ブランドイメージの向上にもつながります。
採用や資金調達の面でもプラスに働く
プレスリリースで企業の活動が広く知られると、「この会社で働きたい」「この企業に投資してみたい」と感じる人が増えることも。採用活動や資金調達など、ビジネスを成長させる場面でもプレスリリースは効果的に働きます。
プレスリリースの書き方・基本構成

プレスリリースには、読み手(記者や編集者)が知りたい情報を整理して伝えるための「型」があります。この基本の型を押さえることで、相手にとって読みやすく、記事として取り上げやすい文書になります。
プレスリリースの基本構成
- タイトル/サブタイトル:内容をひと目で伝える見出し部分
- リード文:本文の要約。ニュースのポイントを簡潔にまとめる部分
- 本文:詳細説明(背景・目的・特徴など)
- 会社概要:企業の基本情報と問い合わせ先
それぞれの項目について、順番にみていきましょう。
タイトル/サブタイトル
タイトルは、読者が最初に目にする部分であり、記事の見出しとしてそのまま使われることもあります。ひと目で内容が分かる具体的な表現を意識しましょう。
サブタイトルは、タイトルを補足する短い説明文です。 タイトルだけでは伝えきれない背景や特徴を補足し、読み手の理解を深めます。タイトルとサブタイトルで「違うアピールポイント」を盛り込むと効果的です。
キャッチコピーのように誇張しすぎると新聞やWebメディアで紹介されにくいため、事実をベースにしたシンプルな補足を心がけましょう。
リード文
リード文は本文の冒頭に置かれる「要約部分」です。「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ」 を簡潔にまとめます。
ここを読むだけで、プレスリリース全体の概要が理解できるようにするのが理想。記者は多くのプレスリリースに目を通すため、冒頭で関心を引けるかどうかが勝負です。
長すぎると要点がぼやけて最後まで読んでもらえないので、2〜3文でまとめるのがおすすめです。
本文
本文では、リード文で触れた内容をさらに詳しく説明します。
- 新商品の場合:開発の背景、特徴、ターゲット層、利用シーンなど。
- イベントの場合:開催の目的、日程や場所、見どころなど。
見出しや箇条書きを入れると読みやすくなります。また、写真や図を入れると内容がぐっと伝わりやすくなるでしょう。
会社概要
本文の最後には、会社に関する基本情報を記載します。
記載する項目の例
- 会社名
- 所在地
- 代表者
- 設立年
- 事業内容
- 公式サイトURL
あわせて、問い合わせ先(広報担当者名、電話番号、メールアドレス)を載せておくと安心です。
会社概要を省略すると、本当に信頼できる情報源なのか信憑性が問われる可能性があります。必ず抜け漏れなく記載しましょう。
【関連記事】
プレスリリースの書き方┃基本の構成とメディアに取り上げられるコツを解説!!
効果的なプレスリリースを書くコツ

プレスリリースは、ただ事実を並べるだけでは記事になりにくいものです。読みやすく、そして「これは取り上げたい」と思ってもらえるように工夫することが大切です。ここでは、初心者の方でも意識しやすい4つのポイントをご紹介します。
結論から伝える
ニュース記事と同じように、プレスリリースも「誰が、何をしたのか」を最初に書くのが基本です。
冒頭で結論を示すと、記者や編集者がすぐに内容を理解でき、記事として取り上げる判断がしやすくなります。逆に結論を後回しにすると、「結局何を伝えたいのか」が分かりづらく、最後まで読まれないこともあります。
数字やデータを活用する
具体的な数字や調査データを盛り込むと説得力が増し、「客観的で信頼できる情報」として扱われやすくなります。
数字は大げさにする必要はなく、事実を正しく書くことが大切です。
読み手(記者・読者)の関心を意識する
プレスリリースは「自分たちが伝えたいこと」だけを書くのではなく、「読む人にとってどんな意味があるのか」を意識すると伝わりやすくなります。
- この情報は社会にどんな影響があるのか?
- 読者にとってどんなメリットや関心があるのか?
こうした視点を盛り込むことで、ただの会社のお知らせではなく、「記事として読者に届ける価値がある」と判断されやすくなります。
全体のボリュームを意識する
プレスリリースは短すぎても情報不足になり、長すぎても最後まで読んでもらえません。目安は A4用紙1〜2枚(800〜1,200字)。多くても3枚以内に収めるのが望ましいとされています。
記者は1日に何十本ものプレスリリースを読むため、短時間で要点が理解できるボリュームがベストです。
【関連記事】
プレスリリースで効果を出すコツとは?タイトルや構成の要点を紹介
プレスリリース作成時のNG例
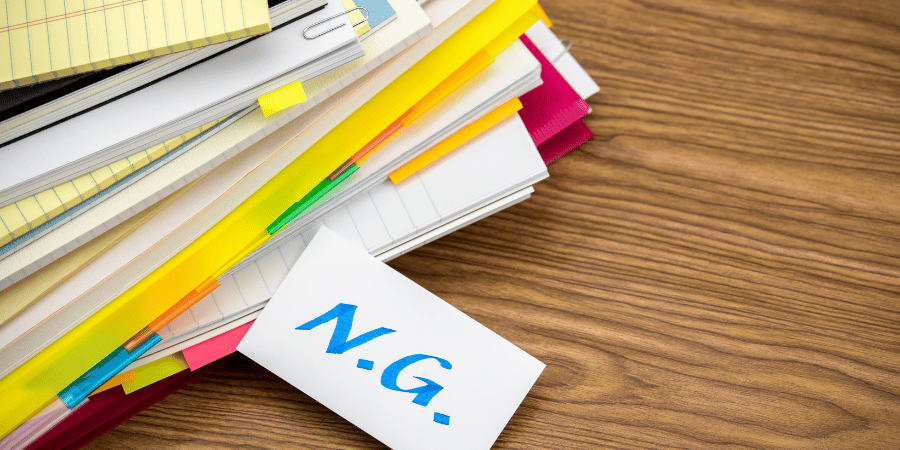
プレスリリースでは、「信頼できる情報」であることが何よりも大切です。
少しの言葉の使い方で印象が変わってしまうため、誤解を招く表現や過剰な宣伝には注意しましょう。特に初めて書くときは、次のようなNGパターンを意識して避けるのがおすすめです。
曖昧な表現
根拠がない表現は信頼性を下げてしまいます。できるだけ「具体的な数字」や「事実」に置き換えましょう。
誇張しすぎた内容
実際よりも成果を大きく見せたり、効果を断言したりすると、信頼を失う原因になります。数字やデータは「正確さ」を意識して伝えましょう。
宣伝色が強すぎる文面
プレスリリースは広告ではなく、ニュースとしての価値を伝えるものです。購買を促すより、「なぜそれがニュースなのか」を意識しましょう。
プレスリリースの注意点

プレスリリースは、信頼できる情報を正確に発信することが何より大切です。
ただし、伝え方やタイミングによって結果は大きく変わります。ここでは、プレスリリースを作成・配信するうえで知っておきたい注意点をご紹介します。
必ずメディアに取り上げられるとは限らない
プレスリリースを出したからといって、必ず記事になるとは限りません。メディアには毎日数多くの情報が届くため、その多くは記者の目に留まらず埋もれてしまいます。
取り上げられる確率を上げるには、タイトルやリード文で関心を引く工夫が必要です。また、発表して終わりではなく、定期的に情報を発信し続けることで、メディアとの信頼関係を築いていけます。
報道内容をコントロールできない
プレスリリースをもとにどんな記事を作成するかは、メディア側の判断に委ねられます。そのため、必ずしも自社の意図どおりに報道されるとは限りません。
誤解を防ぐためには、伝えたいポイントを明確かつシンプルに書くことが重要です。主観的な表現を避け、事実に基づいた情報を整理して伝えましょう。
配信タイミングに注意する
よい内容でも、配信のタイミングを誤ると読まれにくくなります。理想的なのは、メディアが情報をチェックしやすい平日の午前中です。
イベントや新サービスの場合は、開催・リリースの1〜2週間前を目安に配信すると、取材や掲載のスケジュールに余裕が持てます。
【関連記事】
プレスリリースを出すのに最適なタイミングはいつ?曜日や時間帯を解説
写真や資料の著作権・使用許諾に注意する
掲載する写真や画像、ロゴなどは、著作権や肖像権をクリアにした素材を使用しましょう。特に人物が写っている場合は、本人の同意が必要なケースもあります。フリー素材を使う場合も、商用利用の可否を必ず確認しましょう。
プレスリリースの配信方法
プレスリリースは、「どのように発信するか」で届く範囲や効果が大きく変わります。ここでは代表的な3つの配信方法をみていきましょう。
自社サイトで公開する
自社の公式サイトの「お知らせページ」にプレスリリースを掲載する方法です。顧客や取引先に直接伝えられるだけでなく、検索エンジン経由で一般の方に見てもらえる可能性もあります。
- メリット
無料で公開でき、公式情報として残しておける。長期的に検索されることもある。 - デメリット
メディア関係者が自社サイトを見に来ることは少なく、情報拡散のスピードや範囲は限られる。
配信サービスを利用する|PR TIMES など
代表的なのは「PR TIMES」などのプレスリリース配信サービスです。登録すれば、多数のメディアにまとめて配信できます。
- メリット
記者やメディア担当者に直接届きやすく、ニュースサイトに転載されることも多い。自社にメディアリストがなくても利用可能。 - デメリット
利用料がかかる。さらに、毎日大量のプレスリリースが流れるため、内容が平凡だと埋もれてしまうリスクがある。
メディアリストを活用して直接送付
新聞社や雑誌、Webメディアの記者や編集者の連絡先をリスト化し、メールや郵送で直接送る方法です。関係性が築ければ、記事として取り上げてもらえる可能性が高まります。
- メリット
ターゲットを絞って確実に届けられる。個別対応をすることで「この会社のリリースは信頼できる」と関係性を強化できる。 - デメリット
リスト作成や更新に手間がかかる。送付先にあわせて文面を調整する必要があり、工数が増える。
リスト作成や更新に手間がかかる。送付先にあわせて文面を調整する必要があり、工数が増える。
プレスリリース作成・配信を外注する方法

プレスリリースは自社でできるのが理想ですが、「人手が足りない」「後回しになってしまう」といった悩みを抱える企業も多いものです。
そんなときは、外注を活用するのも1つの方法。依頼先によって特徴や費用が異なるので、自社の状況に合った選択をすることが大切です。
PR会社や広告代理店に依頼
PRや広告のプロに依頼する方法です。戦略的に大規模な広報を仕掛けたいときに向いています。
- メリット
記者やメディアとのつながりが強く、テレビや新聞など大手メディアに取り上げられる可能性が高い。企画から配信までワンストップで対応してもらえる。 - デメリット
費用が高額になりがちで、数十万円〜数百万円かかることもある。小規模企業やスタートアップには負担が大きい場合がある。
フリーランスやライターへ依頼
文章作成を専門にしている個人に依頼する方法です。必要な部分だけを頼めるので、小規模案件でも活用しやすいです。
- メリット
比較的安価で、柔軟に対応してもらえる。記事執筆や取材経験のあるライターなら、分かりやすい文章に仕上げてもらえる。 - デメリット
品質や納期が個人のスキルやスケジュールに左右されやすい。当たり外れがあり、安定性にはやや不安が残る。
フリーランスやライターを探す場合は、クラウドソーシングサービス(例:クラウドワークス、ランサーズ)や、ライター専門のマッチングサイトを利用するのが一般的です。募集をかけると複数のライターから応募があり、その中から条件に合う人を選ぶ仕組みです。
オンラインアシスタントに依頼
リモートで業務をサポートしてくれるオンラインアシスタントに依頼する方法です。プレスリリース作成だけでなく、さまざまなバックオフィス業務を依頼できるのが特徴です。
- メリット
必要なときに必要な分だけ頼めるため、コストを抑えやすい。広報以外のバックオフィス業務もまとめて任せられるので効率的。 - デメリット
PR会社ほどの専門性は期待できないため、「大手メディアに載せる確率をできる限り上げたい」場合はPR会社も検討すべき。
オンラインアシスタントなら「フジ子さん」

「広報だけでなく、日々のバックオフィス業務もまとめて頼みたい」
「コストをなるべく抑えたい」
そんな企業におすすめなのが、オンラインアシスタントサービス「フジ子さん」です。
「フジ子さん」は、在宅で働く経験豊富なアシスタントが、チーム体制で業務を支援するサービスです。これまでに官公庁を含む2,000社以上への導入実績があり、信頼性と柔軟性の高さが評価されています。
費用は月20時間で税込65,560円〜、月10時間から利用可能と、パート社員を雇うのと同程度のコスト感でスタートできます。
また、最短1カ月から契約可能で、無料トライアルも実施中。必要な期間・業務だけを依頼できるため、初めて外注を検討する企業でも利用しやすい仕組みです。
チームで継続的にサポートを受けられるので、担当者が退職したり急に不在になったりするリスクを避けられます。「広報やプレスリリースを含めて、社内リソースをうまく補いたい」という企業は、ぜひフジ子さんをご検討ください。
まとめ|プレスリリースを理解し効果的に活用しよう
プレスリリースは、企業の活動やニュースを社会に広く伝えるための大切な手段です。基本の書き方や注意点を押さえ、信頼性のある情報を発信することで、メディア掲載や認知拡大につながります。
広報のリソースが足りない場合は、外注を活用するのも選択肢の1つ。なかでも、オンラインアシスタント「フジ子さん」は、広報業務だけでなくバックオフィス業務もまとめて依頼でき、限られた人員でも効率的に情報発信を進められます。
プレスリリースは一度出して終わりではなく、継続して発信することで信頼と認知が育っていくもの。まずは、自社のニュースをどのように伝えたいかを整理し、少しずつ発信を始めてみましょう。