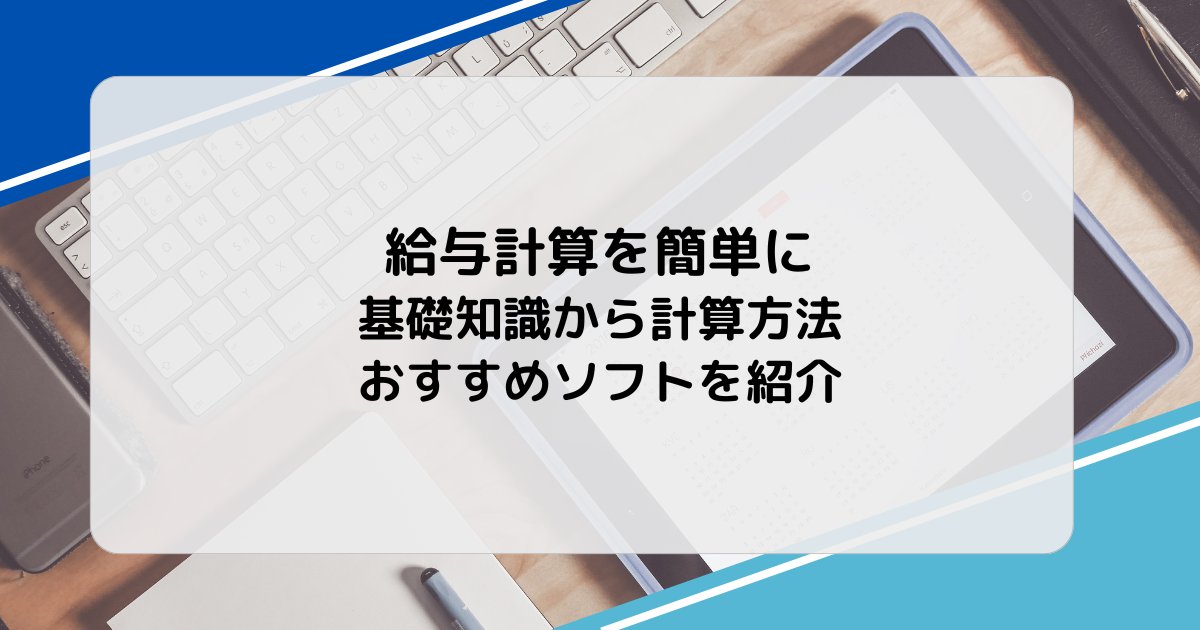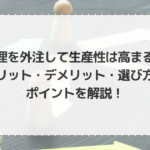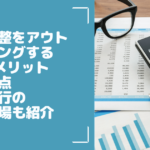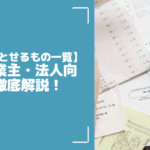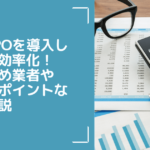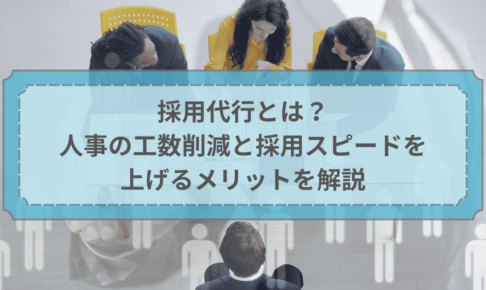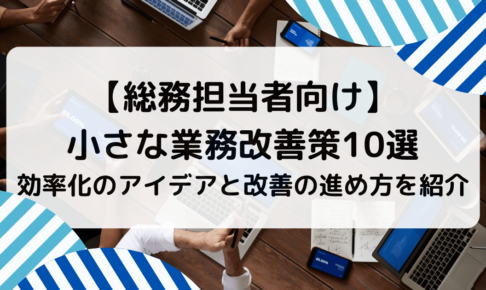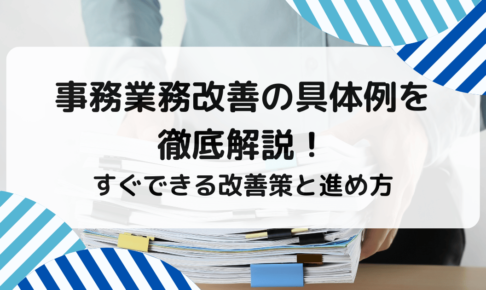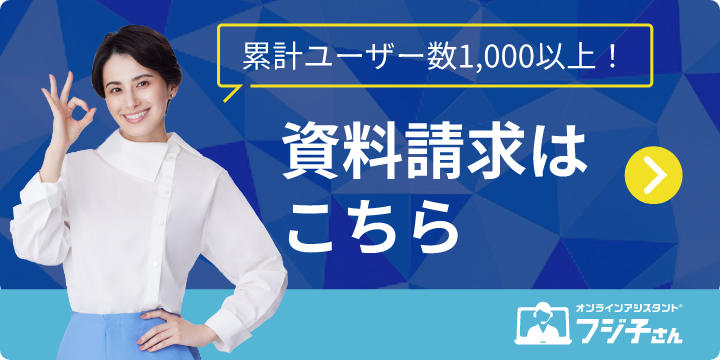企業と従業員は、従業員の労働に対し報酬(給与)を支払うという労働契約を結んでいるため、企業は給与を正確に支払う義務があります。つまり給与計算は、労働契約を履行するために欠かせない業務の1つといえます。
そのため、給与計算のミスや支払いの遅延は許されません。どこか1つでもミスが発生すれば、社会保険料や税金の納付に影響し、税務署への申告漏れに繋がる可能性もあります。
今回は給与計算の基礎知識から、計算方法、ポイント・注意点について解説します。後半では給与計算を効率よく正確に行う方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
給与計算の基礎知識|給与計算とは?
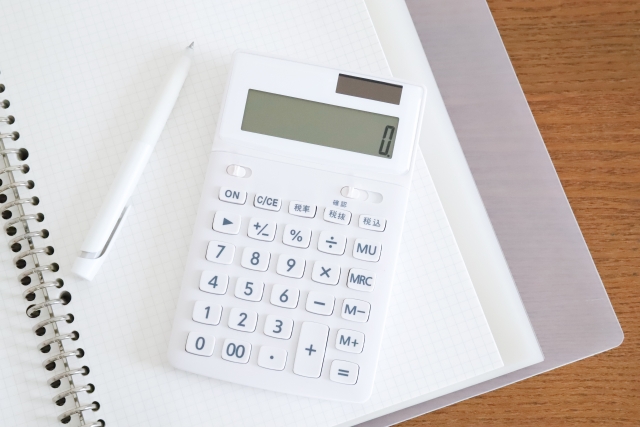
給与計算とは、従業員に支払う給与を正しく算出する業務のことです。
始めに、雇用契約や就業規則、関連する法令などに基づき、従業員の勤務実績などを考慮しながら、各種手当を含む総支給額を計算します。
次に、総支給額から社会保険料や税金を控除し、最終的な差引支給額(手取額)を従業員に支払います。その他に、従業員一人ひとりの社会保険料や税金の納付も担うため、非常に大切な業務です。
そのため、労働基準法をはじめ、所得税法、健康保険法などの法律を理解し、正確に計算することが求められます。
このように、給与計算はとても複雑な業務ですが、効率化の工夫やツールを取り入れることで、複雑な給与計算も簡単に進められるようになります。
給与計算で重要なポイント

給与計算を正しく、かつ効率的に行うためには、いくつかの基本ポイントを押さえておくことが欠かせません。以下の内容を理解することで、給与計算の根拠や複雑になりがちな給与計算も理解しやすくなります。
「賃金支払いの5原則」を守る
労働基準法第24条には「賃金支払いの5原則」が定められています。
- 通貨で支払う(通貨払いの原則)
- 直接従業員に支払う(直接払いの原則)
- 全額を支払う(全額払いの原則)
- 毎月1回以上支払う(毎月払いの原則)
- 一定の期日を定めて支払う(期日払いの原則)
このルールを守ることは給与計算の基本であり、従業員との信頼関係を保つうえでも重要です。
地域別の賃金ルールを確認する
最低賃金は都道府県ごとに異なります。毎年10月頃に改定されるため、給与計算を行う際には最新の最低賃金額を確認しておきましょう。アルバイトやパートの時給計算では違反がないよう注意が必要です。
従業員情報を正確に管理する
給与計算を円滑に行うためには、従業員の基本情報を正しく管理することが不可欠です。
- 雇用形態(正社員・パート・アルバイトなど)
- 勤怠記録
- 扶養家族の有無
- マイナンバーや住所(通勤経路)
これらを整備しておくことで、社会保険や税金の計算もスムーズに行えます。
社会保険・雇用保険の加入基準を理解する
給与計算では、社会保険や雇用保険の加入基準を正しく把握しておくことが大切です。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象
社会保険(健康保険や厚生年金保険)の加入対象は、現在、従業員数が51人以上の企業で以下の条件をすべて満たす従業員です。
- 週の所定労働時間:20時間以上30時間未満
- 月額賃金:8.8万円以上
- 雇用期間:2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
- 学生ではない
雇用保険の加入対象
次の条件を満たす場合、雇用保険に加入する必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
パートやアルバイトであっても、条件を満たせば加入が必須です。なお、雇用保険料は全額企業負担となります。
給与の計算方法

給与計算は、基本的に以下の式で計算します。
計算式:【総支給額 − 控除額 = 差引支給額(手取り額)】
ここからは、総支給額・控除額・差引支給額について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
総支給額の計算
総支給額とは、労働者が労働の対価として得る金額の総額です。
計算式:【総支給額 = 基本給 + 各種手当】
- 基本給
各種手当を含まない基本の給与のことです。企業ごとに勤続年数や学歴、職種、能力などを考慮して決定されます。 - 各種手当
経費の補填などのために支給される報酬です。法律で定められている手当には、時間外手当(残業代)、休日手当、深夜手当などがあります。その他に、企業独自の通勤手当や住宅手当、役職手当なども含まれます。
控除額の計算
控除額とは、総支給額から差し引かれる金額のことです。差し引かれる控除は、「法定控除」と「その他の控除」に分けられます。
- 法定控除
法律に基づいた控除項目です。主に、社会保険料(健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険)と税金(所得税・住民税)に分けられます。 - その他控除
企業ごとに定められた控除項目です。労働組合費、積立金、財形貯蓄、親睦会費、社宅費などが該当します。
差引支給額の算出
差引支給額とは、総支給額から控除すべき社会保険料と税金を差し引いた金額です。一般的に「手取り額」と呼ばれ、この金額が銀行口座に振り込まれます。
例として、以下の場合は手取り額がいくらになるか、実際に式に当てはめてみましょう。
- 基本給:250,000円
- 各種手当合計:120,000円
- 保険料控除:54,633円
- 税金控除:9,910円
計算式:【総支給額(250,000円+120,000円)ー控除額(54,633円+9,910円)=305,457円】
このように、シンプルな計算で算出できます。しかし、実際は控除すべきものは社会保険料と税金をあわせて5種類以上あり、給与計算において非常に大きな負担となる部分です。
そのため、給与計算を簡単に進めるには、控除額の計算をいかに効率化するかがポイントとなります。
【正社員】給与計算の仕方・手順
給与計算は、どのような手順で進めるのでしょうか。ここでは正社員を対象とした具体的なやり方を解説します。
給与計算の前には、基本給・諸手当に変更がないかを必ず確認しましょう。昇格、転居、結婚、出産などで人事データに変更があれば、保険料や税金にも影響するためです。
人事データに変更がないことが確認できたら、早速以下のステップから始めていきましょう。
①総支給額を計算する
給与は大きく、「固定性の給与」と「変動性の給与」に分けられます。
①ー1:固定性の給与
「固定性の給与」は、勤務実績に関係なく毎月一定の金額が継続して支給される給与です。
- 基本給
- 職務手当
- 住宅手当
- 通勤手当
- 単身赴任手当
原則として支給される金額は毎月同じですが、給与体系の変更や昇格、手当の追加などにより、変動する場合があります。
①ー2:変動性の給与
「変動性の給与」は、勤務実績によって支給額が変動する報酬です。
- 時間外手当(残業代)
- 休日手当
- 深夜手当
変動性の給与は、従業員の勤怠状況や成績によって異なるので、ミスがないかしっかり確認する必要があります。
計算式:【時間外労働の時間数 × 1時間当たりの基礎賃金 × 各割増率】
「1時間当たりの基礎賃金」は、労働基準法で除外が認められた手当以外の各種手当に、基本給を加えた金額を、1ヶ月の所定労働時間で割った金額です。
労働基準法で除外が許される手当は、家族手当や通勤手当、別居手当など労働と直接的な関係が薄い手当が該当します。
割増率表:
| 項目 | 条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 45時間以下 | 25% |
| 45時間超~60時間以下 | 30% | |
| 60時間超 | 50% | |
| 法定休日労働 | 法定休日に勤務した場合 | 35% |
| 深夜手当 | 22時から翌5時まで | 25% |
深夜残業が発生した場合は、時間外手当の割増率25%に深夜手当の割増率25%を上乗せします。
例:就業時間が9時から17時の従業員が9時から23時まで働いた場合
- 17時~22時:時間外手当として25%の割増率
- 22時~23時:時間外手当25%+深夜手当25%=50%
②控除額を計算する
控除額には「社会保険料の控除」と「税金の控除」があり、それぞれ算出方法が異なります。
②ー1:社会保険料の控除
正社員の場合、社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険)への加入が義務付けられています。
社会保険料の計算には、「標準報酬月額」を基準とするものと、「総支給額」を基準とするものの2種類があります。
- 健康保険・厚生年金・介護保険:標準報酬月額×保険料率÷2(従業員負担分)
- 雇用保険:総支給額×保険料率
標準報酬月額とは、給与を一定の幅に区分した仮の金額です。通常は4〜6月の基本給に、諸手当を加算した金額の平均をベースに算出され、毎年7月10日までに「算定基礎届」を管轄の年金事務所へ提出する必要があります。
【健康保険】
健康保険は、従業員の医療費を保障するための制度です。
運営主体は協会けんぽや組合保険、公務員の場合は共済組合であり、加入先によって保険料が異なります。協会けんぽの場合は、都道府県ごとに保険料率が異なる点に注意が必要です。
【厚生年金保険】
厚生年金は、将来の年金給付のために拠出する保険で、保険料率は一律18.3%です。平成29年の税率引き上げ後、現在の料率が維持されています。
【介護保険】
介護保険は40歳以上の従業員が加入対象となっており、40〜64歳の従業員は、健康保険料に上乗せして控除されます。65歳以上の場合は、市町村に納付します。納付額は加入している健康保険によって異なり、例えば協会けんぽの場合は、1.59%(令和7年4月30日納付期限分)が適用されています。
【雇用保険】
雇用保険は他の社会保険と異なり、以下の計算式で求めます。
計算式:【雇用保険=総支給額×保険料率】
保険料率は業種ごとに定められており、企業と従業員で分担して負担します。2025年4月1日現在、一般の事業の保険料率は14.5/1,000(企業9/1,000、従業員5.5/1,000を負担)となっています。
保険料控除のまとめ
給与から控除される保険料についてまとめると、以下のようになります。
| 項目 | 計算式 | 負担者 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 標準報酬月額×保険料率 | 企業と従業員で折半 |
| 厚生年金保険料 | 標準報酬月額×保険料率(18.3%) | 企業と従業員で折半 |
| 介護保険料 | 標準報酬月額×保険料率 | 企業と従業員で折半 |
| 雇用保険料 | 総支給額×保険料率 | 企業と従業員で分担 |
②ー2:税金の控除
毎月の給料から天引きされる税金は、所得税と住民税です。
源泉所得税
所得税は、年間所得額に応じて決定されるため、月々の天引き額はあくまで見込みの金額です。正確な源泉所得税額は年末調整で算出され、差額があれば還付または追加徴収されます。
計算式:【源泉所得税=課税所得額×所得税率ー控除額】
源泉所得税率は給与額と扶養家族の人数で異なり、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて税額を割り出します。
参考:令和7年分源泉徴収税額表
住民税
住民税は、前年度の所得により決定されます。毎年6月頃に、企業へ従業金の住民税課税決定通知書が届くので、請求された住民税額を12ヶ月に分割した金額を毎月の給与から控除します。
そのため、新卒や前年度に所得がない場合、入社した最初の年は住民税が天引きされないケースもあるため、注意が必要です。
③差引支給額を計算する
総支給額から②で求めた控除額を差し引き、差引支給額(手取り額)を求めます。
計算式:【差引支給額 = 総支給額 − (健康保険料 + 厚生年金保険料 + 介護保険料 + 雇用保険料 + 所得税 + 住民税)】
この金額が実際の手取りとして従業員に支払われます。
【アルバイト・パート】税金・社会保険の基準と給与計算のポイント
アルバイトまたはパートの場合も、総支給額から控除額を引いて差引支給額を算出する流れは、正社員と同様です。
正社員の場合との違いは、「控除される人」と「控除がない人」が出てくる点です。
ここでは、アルバイト・パートの場合、具体的にどのような基準で社会保険に加入が必須となり税金がかかるのか、詳しく見ていきましょう。
所得税がかかる基準
所得税は、基礎控除が48万円、給与所得控除は最低55万円が控除されます。
【基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円】
このため、収入が103万円以下の場合は課税所得が0円となり、所得税はかかりません。また、配偶者の扶養に入っている場合は、「配偶者控除」により配偶者の所得税・住民税が軽減されます。
一方、収入が103万円を超えると、超えた分に対して正社員と同様に、「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて算出された税額が給与から控除されます。収入が103万円〜201万円の場合、配偶者特別控除が受けられます。
ただし、配偶者控除および配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える年は控除を受けることができません。
住民税がかかる基準
住民税は、1月1日から12月31日までの所得について、翌年課税されます。居住する市町村により違いはありますが、前年度の所得がおおよそ100万円以下であれば、住民税はかかりません。
住民税の計算方法は、所得割と均等割の2種類から算出され、給与から控除されます。所得割は、所得金額に比例して前年度の所得に応じて課税されます。一方均等割は、所得に関係なく各市町村が定める一定額が課税されます。
給与明細は5年間保存しよう
給与明細の保存は、法律で義務付けられているわけではありません。しかし、給与明細に記載されている項目が賃金台帳と重なっているため、実質的には賃金台帳と同等に扱われます。
賃金台帳とは法定三帳簿の1つで、企業は最低5年間の保存が義務付けられています。そのため、給与明細も、企業は最低でも5年間は保存しておくことが望ましいといえます。
また、労働基準法の改正により、2020年4月から未払い賃金を請求できる期間が2年から5年に延長されました(当面は3年)。給与明細は従業員に給与を支払ったという重要な証拠になるため、企業・従業員双方にとって給与明細を5年分保存しておくメリットは大きいといえます。
その他にも、従業員が給与明細を保管しておくべき理由が4点あります。
従業員が給与明細を保管しておくべき理由
- 収入の証明に使用できる
クレジットカードやローン、賃貸などの審査で直近の収入の証明として給与明細が使用できる場合があります。 - 源泉徴収票の代わりに使用できる
確定申告や配偶者の扶養に入るための書類として使用可能です。確定申告の還付や控除の時効は5年のため、確定申告を行う場合は給与明細を5年分保存しておくことが望ましいです。 - 税金や保険料の支払いの証明になる
厚生年金保険料や支給額を見ながら、年金記録に間違いがないかを確認できます。 - 離職票の記載に間違いがないかを確認ができる
退職時、雇用保険の受給手続きで誤りがないかを照合できます。
以上の理由により、企業も従業員も給与明細の保管期間は5年が望ましいといえるでしょう。
給与計算の注意点

給与計算は毎月必ず発生する業務ですが、単純なルーチン作業に見えて、実は企業にとってリスクの大きい業務でもあります。一度のミスや不備が、従業員の不信感やトラブル、法的リスクにつながるため、以下の点には特に注意が必要です。
情報漏えい
給与明細や賃金台帳には、従業員の氏名、住所、マイナンバー、給与額などの高度な個人情報が含まれています。万が一情報が漏えいすれば、プライバシー侵害や企業の信用失墜につながる恐れがあります。
- 給与データはアクセス制限をかける
- パスワード管理を徹底する
- 外部に持ち出す場合は暗号化する
といった、情報セキュリティ対策を怠らないことが重要です。
計算ミス
給与計算は、労働時間、残業時間、各種手当、社会保険料、税金など、多くの要素を組み合わせて算出する必要があります。少しの入力ミスや計算方法の誤りがあると、従業員の不利益や賃金未払いのトラブルに直結してしまいます。
- 最新の法令や保険料率を定期的に確認する
- ダブルチェック体制を整える
- 給与計算ソフトを活用する
などの仕組みを整えることで、人的ミスの予防に努めましょう。
スケジュールの管理
給与は「毎月〇日支払い」とあらかじめ決められており、遅延は労働基準法違反にあたります。例えば月末締め翌月25日払いの場合、25日までに必ず計算を終え、振込データを金融機関へ提出する必要があります。
- 社内の締め日・支払日を常に意識する
- 祝日や年末年始など銀行休業日に備え、前倒しで準備する
- システム障害や人員不足に備えたバックアップ体制を整える
このようにスケジュール管理を徹底することで、安定した給与支払いが可能になります。
給与計算をミスしたらどうなる?
給与計算はミスが許されない非常に重要な業務です。従業員一人ひとりの勤怠状況や社会保険料、税金など多くの要素を考慮する必要があり、特に手作業が多い場合は、ヒューマンエラーが起こりやすくなります。
中には「翌月の給与で調整すれば問題ない」と考える人もいますが、実際には法令違反や従業員への不利益につながる恐れがあるため、細心の注意が必要です。
ミスが労働基準法違反につながるケース
給与の翌月精算は、労働基準法第24条が定める「賃金支払の5原則」に違反する可能性があります。
特に時間外手当が長期にわたって不足していた場合には、ただちに不足額を計算し、支払わなければいけません。さらに、遅延利息や遅延損害金、付加金などが発生する場合もあり、企業にとって大きな負担となります。
税金・社会保険への影響
給与計算に誤りがある場合、同時に社会保険料や税金の計算にもミスが発生している可能性があります。その場合、税金不足による追徴課税や、将来の年金受給額が実際よりも少ないといった従業員の不利益につながる可能性があります。
企業の信頼への影響とミスへの対応
給与計算を誤ったまま放置すると、従業員からの信頼を損ねるだけでなく、未払い賃金請求や訴訟に発展する可能性もあります。企業の社会的信用に関わるため、発覚した場合には迅速な対応が不可欠です。
万が一給与計算の誤りが発覚した場合は、
- 対象従業員へ速やかに謝罪する
- 正しい金額を再計算する
- 過不足分をただちに調整し支払う
といった対応を行いましょう。
給与計算を簡単にする方法|ツールを活用しよう
給与計算をすべて手作業で行うと、時間も手間もかかり、さらにミスが発生しやすくなります。そのため、ツールを活用して効率よく行うのがおすすめです。
特に、従業員数が少ない小規模事業者や個人事業主であれば、まずは無料で使えるWebサービスを試すことで、コストをかけずに給与計算を正確に進められます。
無料のサービスは、必要項目(労働時間や時給、各種控除額など)を入力するだけで自動で計算してくれるのが特徴です。複雑な計算式を覚える必要がなく、初めて給与計算を担当する人でも安心して使える点が大きなメリットです。
無料で使えるWebサービス
以下のような無料Webサービスを利用すれば、簡単に給与計算を行えます。いずれもブラウザ上で利用でき、会員登録不要で使えるものもあるため「今すぐ試してみたい」という方に便利です。
| サービス名 | 主な機能 |
|---|---|
| 給与ねっと | 給与計算、賞与計算、手取り計算、給与明細書作成 |
| イージー給料計算 | 給与・賞与計算、社会保険料・源泉所得税計算、給与明細・源泉徴収票作成 |
| 給与明細.net | 会員登録不要、入力だけで PDF の給与支払明細を作成可能 |
| パート勤務時間計算 | 勤務開始・終了時刻、休憩時間から労働時間・日給を計算 |
業務効率化におすすめの給与計算ソフト
次に、業務効率化におすすめの給与計算ソフトをご紹介します。無料サイトよりも多機能かつ使いやすいため、業務効率を大きく向上させたい場合に適しています。
フリーウェイ給与計算

出典:フリーウェイ
「フリーウェイ」は、毎月の給与計算から年末調整まで対応しているクラウド型給与計算ソフトです。従業員5人までは無料で利用でき、従業員6人以上でも月額1,980円と低コストで導入可能です。さらに、Windows、Macのどちらにも対応しているため、既存の環境を変える必要はありません。
総支給額や控除額の自動計算に加え、給与明細や源泉徴収票などの書類も簡単に作成できます。
シンプルな画面構成で操作しやすいため、給与計算に不慣れな方でも安心して使えるのが特徴です。少人数の事業者やコストを抑えながら正確な給与計算を行いたい企業におすすめです。
freee人事労務

出典:freee人事労務
「freee人事労務」は給与計算業務だけでなく、年末調整やマイナンバー管理、入退社管理など人事労務業務を一元管理できるクラウド型ソフトです。情報を集約できるため、転記作業が不要となり、入力ミスや業務の手間を大幅に削減できます。
基本料金0円+1名ごとの従量課金制で、必要な機能だけを月額2,000円から利用でき、導入支援サポートも充実しています。
マネーフォワード クラウド給与

「マネーフォワード クラウド給与」は、勤怠管理システムや労務管理ソフトと連携可能なクラウド型給与計算ソフトです。勤怠データや身上変更情報を自動で取り込みでき、給与計算の効率化を実現。給与明細のペーパーレス化や、オンライン確認にも対応し、印刷や郵送作業を削減できます。
個人事業主向けから大企業向けまで幅広い事業規模に対応可能で、すでにマネーフォワードクラウドを利用している方におすすめの給与計算ソフトです。
【マネーフォワード クラウド給与のサービス詳細はこちらから】
ジョブカン給与計算

出典:ジョブカン給与計算
「ジョブカン給与計算」は、給与計算に必要な基本機能を備えたクラウド給与計算システムです。給与計算担当者の声をもとに開発され、控除の自動計算や、帳票の自動出力が可能。また、ジョブカンシリーズと連携ができるので、ジョブカン勤怠管理との連携で、勤怠管理から給与計算までをシームレスに処理できます。
従業員5名までは無料で利用でき、6名以上の場合も月額2,000円(税抜)から導入可能です。ジョブカンシリーズを導入している企業には、一連の業務の効率化する効果が高くおすすめです。
弥生給与 Next

出典:弥生給与 Next
「弥生給与 Next」は、給与計算から振込までを自動化できるクラウド型ソフトです。最新の法令に対応しており、計算ミスのリスクを軽減できます。給与明細や申告書はWebで配布・回収でき、ペーパーレス化も実現。社会保険や労働保険の手続きもオンラインで完結します。さらに「弥生会計」「やよいの青色申告」と連携することで、会計業務までスムーズに処理可能。月額3,000円(税抜)から利用でき、3か月間の無料お試しも用意されています。
【関連記事】
クラウド型給与計算ソフト5つを比較!選び方も解説します
給与計算ソフトはどれを選ぶのが良い?種類ごとの特徴や選び方を解説
フジ子さんでも給与計算ソフトの比較検討をお手伝いします!

本ブログを運営するオンラインアシスタント「フジ子さん」では、給与計算ソフトの比較検討など、ご希望に合ったサービスや業者を探すお手伝いが可能です。
オンラインアシスタントとは
オンラインアシスタントは、Webを通じてクライアントのバックオフィス業務を代行するサービスです。経理や秘書業務、総務、一般事務、Web関連の業務など、幅広い業務に対応可能です。
当社の強みは、経験豊富なプロフェッショナルによる高品質かつスピーディーな対応と、業界水準の約半額というリーズナブルな料金設定です。一般的なオンラインアシスタントの相場は、月30時間で実働12〜15万円ほどですが、フジ子さんなら税込97,350円(※2025年4月1日より新価格)でご利用いただけます。
この圧倒的なコストパフォーマンスが高く評価されており、継続利用率はなんと96%以上。多くのクライアントにご満足いただいているサービスです。
2時間の無料トライアルを実施中
現在フジ子さんでは、2時間実働の無料トライアルを実施中です!まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
本記事では、給与計算の基礎知識から具体的な計算方法、注意点までを解説しました。
給与計算は、従業員一人ひとりの勤怠や保険料、税金などを考慮して行う必要があるため、非常に複雑で整理すべき情報が多い業務です。さらに、ミスが許されない分、担当者の負担は大きくなりがちです。
そのため、給与計算ソフトの活用や外注の検討は有効な選択肢となります。業務を自動化・効率化することで、ヒューマンエラーを防ぎつつ、担当者の負担を軽減できます。もし現状の給与計算に課題や不安を感じているのであれば、この機会に自社に合った解決策を取り入れることをおすすめします。