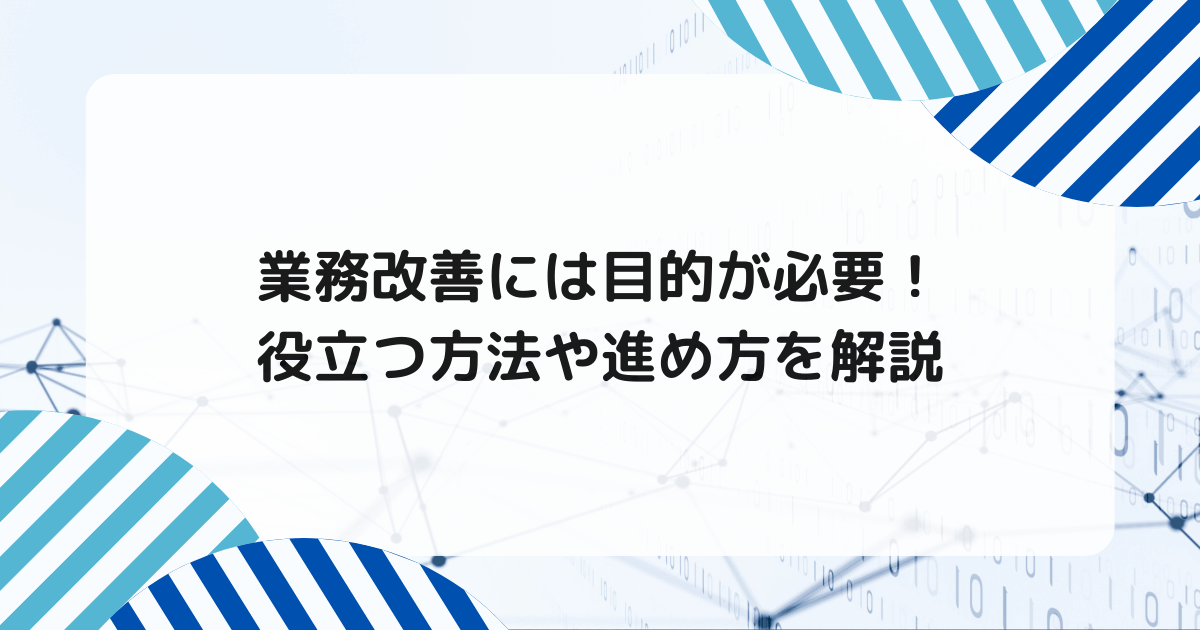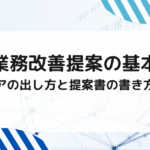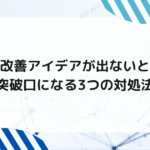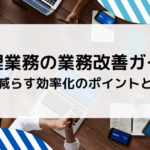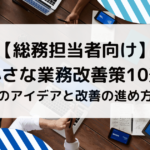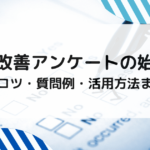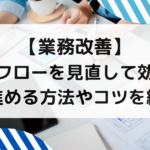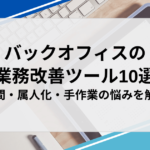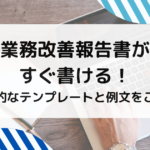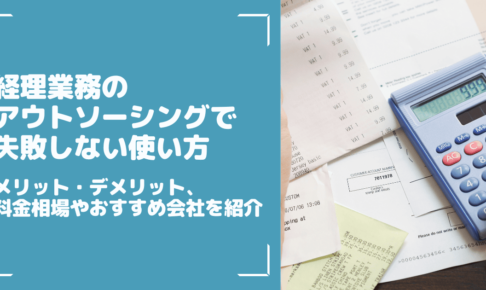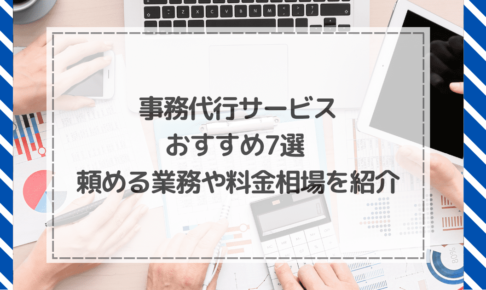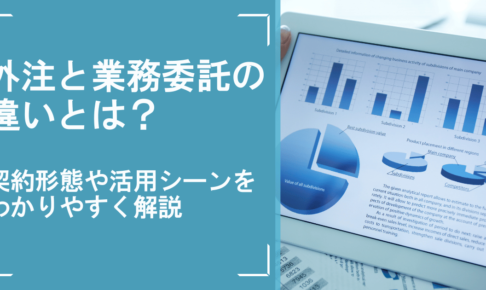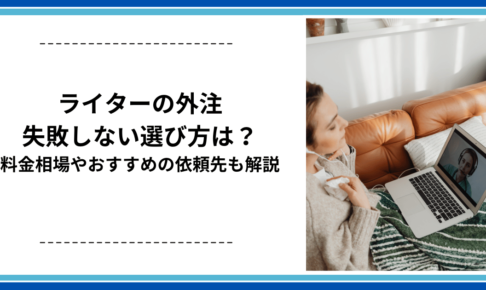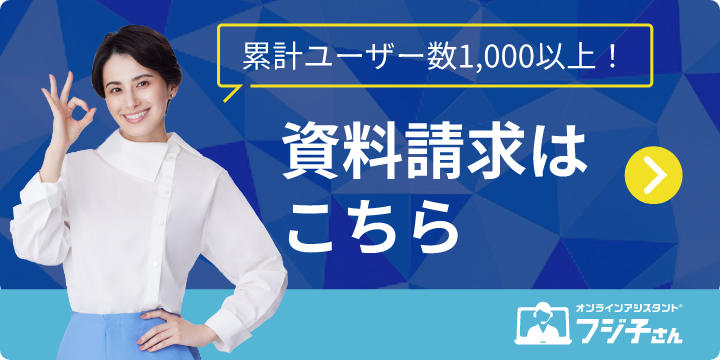業務改善を任されたものの、目的の立て方や進め方が分からず迷っていませんか?
「業務改善して効率よく仕事をしたい…」
「業務改善するには何から始めたらいい?」
「どうやって目的を決めるの?」
このような悩みを抱える方に向けて、業務改善の目的の決め方と実践に役立つ方法を解説します。
目的が曖昧なままでは、効率化やコスト削減の効果があまり感じられません。目的を明確にすれば成果を得やすくなりますので、本記事を参考に業務改善を成功へとつなげていきましょう。
目次
業務改善とは?
業務改善とは仕事のやり方を見直し、より良い形に変えて、効率的に質の高い成果を出すことです。
具体的には、無駄な作業をなくして時間を短縮したり、ミスを減らしたりする工夫をします。
業務改善は一度きりで終わるものではなく、継続して取り組むことで会社全体の成長や利益の向上につなげます。
業務改善に目的が必要な理由
業務改善に目的が必要な理由は、失敗を防ぎ、効果を確実に得られる可能性が高まるからです。
目的を設定しないまま改善に取り組んでも、成果はなかなか現れません。目的が曖昧だと改善の方向性が定まらず、時間やコストを投じても結果が見えにくくなるためです。
また、「時間を短縮したいのか」「コストを削減したいのか」「品質を向上させたいのか」によって、取るべき方法は大きく異なります。例えば、品質を向上させたいのに、単に人件費を削ってコストカットを進めても、かえって状況が悪化する可能性があります。
目的を明確にすると、社員全員が同じ方向を向き、改善の成果をより確実に得られるようになるはずです。
業務改善の主な目的5つ

業務改善をする主な目的を解説します。まずは自社に合わせた目的を見つけていきましょう。
1.業務フローを簡素化して作業時間を短縮
業務フローを見直し、簡素化して作業時間の短縮を図ることは、業務改善の重要な目的の一つです。
現在の仕事の流れから不要な工程や手続きを減らせば、作業時間が減り、別の重要な業務に充てられるようになります。
例えば、複数の承認ステップをまとめたり、同じ情報を何度も入力しなくてよい仕組みにしたりと、見直せる作業は少なくありません。
業務フローを効率化し、人員をより重要な業務に集中させることで、効果的な業務改善につなげていきましょう。
2.業務を効率化して人手不足に対応する
業務を効率化して、人口減少による人手不足に対応するのも目的の一つです。
日本の総人口は14年連続で減少しており、人手不足への対策は避けて通れません。
※参考:総務省「人口推計」
少ない人数でも仕事を回せるようにするには、作業方法の工夫やツールの活用が必要です。例えば、定型作業を自動化するシステムを導入する、仕事の分担を見直すといった改善が考えられます。
その結果、限られた人員でも安定した成果を出せる体制を整えられるでしょう。
3.業務を最適化してコスト削減する
業務の進め方を効率的に組み立て直し、無駄な費用を減らすことも業務改善の目的の一つです。
材料や人件費の使い方を見直したり、外注やツールを導入したりすると、コストを抑えやすくなります。
また、社内に専門スキルを持つ人材がいない場合は、専門業者へ外注することで最適なコストパフォーマンスを期待できます。
コスト削減は利益の増加に直結するため、重要な目的として位置づけている企業も多いでしょう。
4.品質を向上して顧客満足度を上げる
商品やサービスの品質を高め、顧客満足度を向上させることも、業務改善の目的の一つです。
業務内容のムラをなくし、市場の変化にあわせて商品やサービスを進化させ続けることで、お客様の満足度をさらに高められます。
その結果、リピート購入や口コミによる新規顧客の獲得にもつながるでしょう。
さらに、ミスや不良品を減らすためのチェック体制の強化や、社員のスキルアップ研修なども効果的な取り組みです。
5.働きやすい環境づくりで多様な働き方を実現する
働きやすい環境を整え、現代に合わせた多様な働き方を実現するのも、業務改善の目的として設定するとよいでしょう。
例えば、リモートワークやフレックスタイム制の導入など、柔軟な働き方を可能にする仕組みを整備します。
これにより、従業員の満足度が高まり、長時間労働や離職の減少にもつながります。
働きやすい環境は、人材の確保と定着に欠かせない要素です。
目的を定めるための3つのステップ
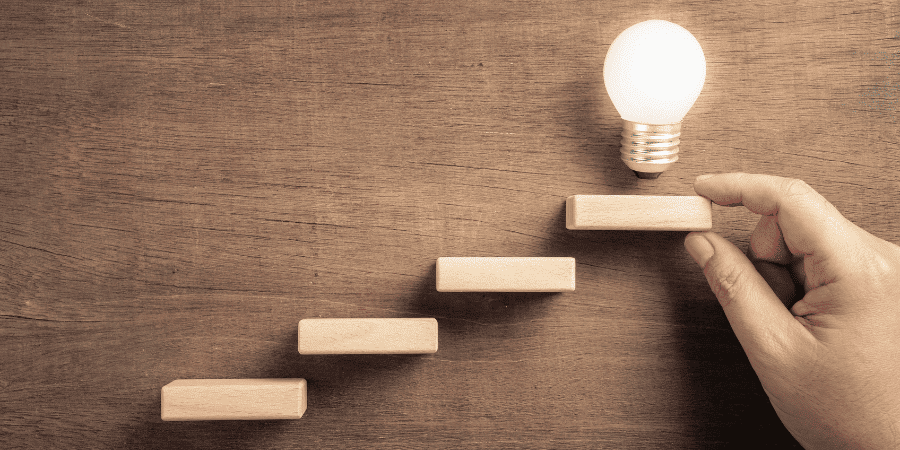
目的を定めるためのステップをご紹介します。やりたいことが複数ある場合でも、一つずつ着実に進めていくために、目的ごとにステップを進めましょう。
目的を定めるための3つのステップ
1.現状を分析して課題を洗い出す
2.改善の優先順位を決める
3.対応方法と期日を設定する
1.現状を分析して課題を洗い出す
まずは、今の業務の流れや成果を細かく確認し、どこに問題があるかをはっきりさせます。
作業時間が過度にかかっていないか、ミスが多発していないか、コストが想定以上にかかっていないかをチェックします。
課題を洗い出す段階では、「なぜその問題が起きているのか」という原因まで掘り下げることが重要です。現状を正しく理解しないまま改善を始めると、的外れな対策になる可能性があります。客観的な分析を行い、問題の原因を特定しましょう。
2.改善の優先順位を決める
課題を見つけたら、改善に取り組む順番を決めます。複数の課題がある場合、すべてを一度に解決しようとすると混乱を招くため、優先順位をつける必要があります。
判断基準は「効果の大きさ」「緊急度」「実行の容易さ」です。
例えば、早期に着手することで大きなコスト削減効果が見込めるものや、顧客満足度に直結するものは優先度を高く設定します。優先順位を明確にすれば、改善活動を計画的に進めやすくなるはずです。
3.対応方法と期日を設定する
改善の順番が決まったら、具体的な対応内容と期日を設定し、行動計画を立てます。
「誰が、何を、いつまでに」実行するのかを明確にし、進捗を確認できる仕組みを整えてください。
期日を設定することで改善が後回しにならず、計画通りに進めやすくなります。さらに、完了後は結果を振り返り、必要に応じて追加の改善につなげることが大切です。
業務改善に活用できるフレームワーク
業務改善を進める際に役立つフレームワークが、成果の質を高める「QCD」と、問題点を洗い出す「3M」です。それぞれ詳しく解説します。
【QCD】成果の質の向上を目的とした業務改善
QCDを意識した業務改善では「お客様に満足していただける品質を保ちながら、無駄なコストを減らし、約束した納期を守る」という3つの要素のバランスを整えることを目的とします。
QCDは「Quality(品質)」「Cost(コスト)」「Delivery(納期)」の頭文字です。
- Quality(品質):製品やサービスの質を高めること
- Cost(コスト):人件費や経費を削減すること
- Delivery(納期):決められた期限までに確実に届けること
例えば、ECサイトで商品を販売している会社であれば、以下のような目的を設定します。
- 品質:作業の手順を見直して不良品を減らす
- コスト:問い合わせ対応にAIを導入して人件費を削減する
- 納期:マニュアルを改善してスムーズな流れ作業を実現する
このように3つの視点をバランスよく取り入れることで、最適な形で業務を進められるようになります。
【3M】原因究明を目的にした業務改善
3Mとは、「ムリ」「ムダ」「ムラ」という3つの問題点を指します。
- ムリ:作業や人員に過剰な負担がかかっている状態
- ムダ:不要な作業や時間、コストが発生している状態
- ムラ:作業の量や品質にばらつきがある状態
3Mを見つけて取り除くことで、作業がスムーズになり、トラブルや失敗も減らせます。
例えば、次のような視点で確認すると効果的です。
「1人の社員に仕事が集中していないか?」
「同じ書類を何度も書き直していないか?」
「日によって成果の質が変わっていないか?」
日々の作業内容を分析して改善策を考えることが、3Mを活用した業務改善のポイントです。
【関連記事】
業務改善に役立つフレームワークとは?種類・活用法・選び方まで徹底解説
目的別に選べる!業務改善の具体的な方法7選
目的が定まったら、実際に業務改善を行います。そこで、業務改善をする具体的な方法をご紹介します。目的に合わせた方法で実行していきましょう。
目的別に選べる!業務改善の具体的な方法7選
- 【目的:時間短縮】
①業務を洗い出して不要な業務を削減
②社内コミュニケーションツールの活用 - 【目的:働き方改善】
ペーパーレス化してリモートワークを促進 - 【目的:作業効率アップ】
①自動化システムの導入
②会議の効率化 - 【目的:品質改善】
業務マニュアルを整備して属人化を防止 - 【目的:負担軽減】
外注・アウトソーシングの活用
【目的:時間短縮①】業務を洗い出して不要な業務を削減
作業時間を短縮したい場合は、現在の業務内容を洗い出して、不要な工程を削減しましょう。
まずは日々の業務をすべて書き出し、「やらなくても支障がない作業」や「重複している作業」を見つけることがポイントです。
業務を洗い出す際に、フレームワークの「3M」を活用して要点を整理すると、より業務フローの問題点に気づけるはずです。
慣習的に形式だけで行っている作業も、客観的に見れば不要と気づける場合があります。
不要な業務を減らすことによって、時間や人手をより重要な仕事に振り分けられます。
【目的:時間短縮②】社内コミュニケーションツールの活用
業務時間を短縮したい場合は、社内コミュニケーションツールを取り入れましょう。
席が離れている人に直接話しかけて質問したり、資料を紙に印刷して届けたりするのは時間のロスにつながります。
チャットツールやオンライン会議システムを導入すると、情報共有が早くなります。資料も添付できるので、紙のやり取りより効率的です。
また、チャットツールには履歴が残るので、必要な情報をすぐに見つけられる仕組みも整います。より効率的な業務フローを実現するためにも、積極的にコミュニケーションツールを活用しましょう。
3.【目的:働き方改善】ペーパーレス化してリモートワークを促進
リモートワーク・在宅勤務など、働き方の多様化を促進したい場合は、ペーパーレス化を検討しましょう。
紙の書類をデジタル化すると、オンラインで資料を共有できるため、在宅勤務や出張先からでもスムーズに作業が進みます。保管場所や印刷コストを削減できるのも大きなメリットです。
また、リモートワークが可能になれば通勤時間もなくなり、従業員の満足度向上も期待できます。
4.【目的:作業効率アップ①】自動化システムの導入
作業効率を高めたい場合は、自動化システムの導入がおすすめです。
データ入力や集計などの定型作業は、自動化ツールやRPA※を活用すれば、大幅な時間短縮が可能です。
※RPAとは、定型作業をソフトウェアロボットが代行して自動化できる技術。
定例作業を行う必要がなくなれば、人が担うべき業務に集中できるため、全体の生産性向上につながります。自動化システムの活用は、代表的な業務改善の手法といえます。
フレームワークの「QCD」を活用して自動化システムを導入すると、バランスよく業務フローが整いやすくなるはずです。
5.【目的:作業効率アップ②】会議の効率化
業務時間を見直す際には、会議の効率化も効果的です。
例えば、会議が始まってから議題を提示すると、その場で考える時間が発生し、無駄が生じやすくなります。また結論を次回に持ち越せば、意思決定が先延ばしになってしまいます。
効率的に会議を進めるには、目的と議題を事前に共有し、必要な人だけが参加する仕組みにしましょう。さらに、意思決定までの時間に上限を設けるなど、短時間で結論を出すルールを作れば、会議に費やす時間を大幅に削減できるはずです。
6.【目的:品質改善】業務マニュアルを整備して属人化を防止
属人化を防ぐには、業務マニュアルの整備が欠かせません。
特定の人しか対応できない業務は、引き継ぎや対応遅延の原因になります。例えば、1人しかできない業務の担当者が欠勤すれば、顧客に迷惑をかけるリスクが高まります。
作業手順やポイントをマニュアル化して共有すれば、誰でも同じ品質で業務を行える体制を築けるはずです。その結果、人によるばらつきが減り、品質のムラも改善できるでしょう。
7.【目的:負担軽減】外注・アウトソーシングの活用
社内に適正な人材がいない場合は、外注・アウトソーシングを検討しましょう。
専門知識が必要な業務や、時間のかかる定型作業を外部に委託すれば、社内の負担を減らせます。
外注は人手不足への対応や人件費の変動化、業務スピードの向上にもつながります。また、コスト削減効果を得られる場合も少なくありません。
外注して空いた時間は、自社のコア業務に使用できるので、事務業務に時間を取られている場合におすすめの業務改善の手段です。
外注するならオンラインアシスタントの「フジ子さん」

外注をご検討中の方にオンラインアシスタント「フジ子さん」をご紹介します。
フジ子さんでは、
- 秘書・総務
- 経理
- 人事・採用
- Webサイト運用
- マーケティング
- 翻訳
- デザイン
- SEOライティング
など、幅広い業務に対応しています。
担当アシスタントが連携して、日頃の業務を一元的にサポートします。
また料金プランは65,560円からあります。社員を雇うより安くすみ、無料トライアルもあるので、圧倒的にリーズナブルです。時間が余った場合は翌月へ時間を繰り越せるプランもあるため、業務量にあわせて柔軟に利用できます。
幅広い分野の実務経験者が対応しますので、興味がある方はぜひ無料トライアルをお試しください。
まとめ:業務改善は目的の明確化が成功のカギ
業務改善の目的や実践に役立つ方法をご紹介しました。
業務改善は「なぜ改善するのか」という目的を明確にすることが、成功への第一歩です。
目的が明確になれば、選ぶ方法や使うツール、取り組む順番も自ずと決まり、無駄な時間やコストを減らせます。
目的に合わせた改善策を選び、継続して取り組むことで成果が出やすくなります。
今日から目的を明確にし、業務改善に取り組んでみてください。