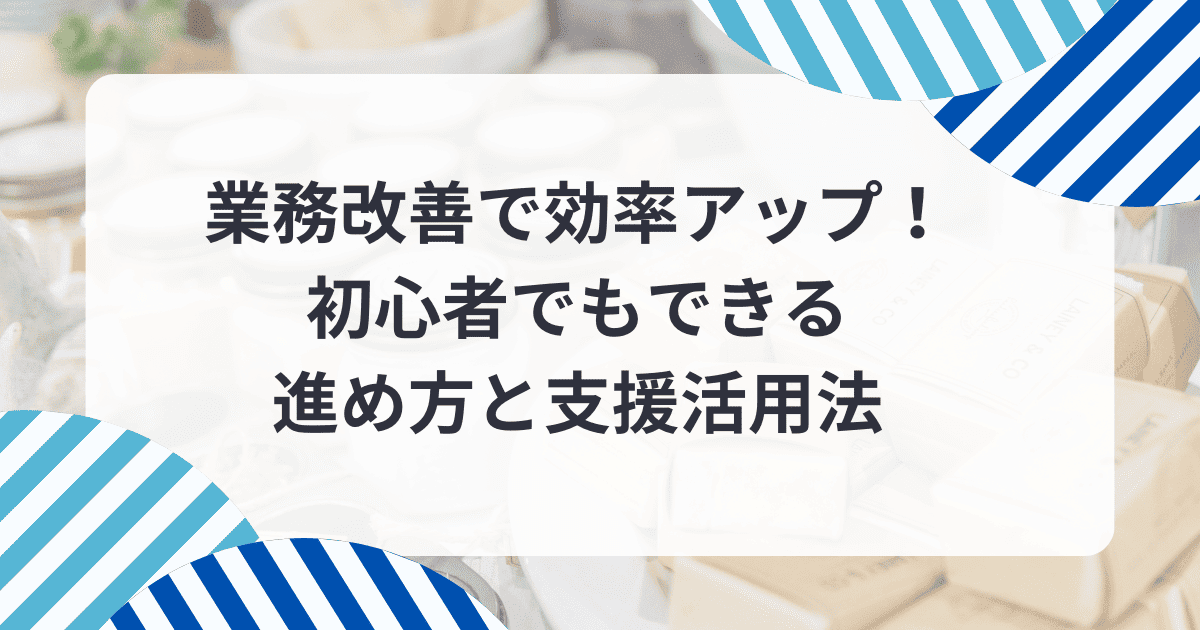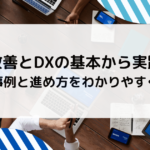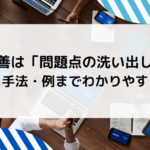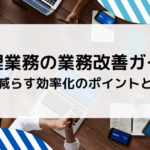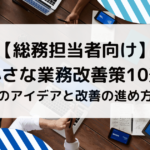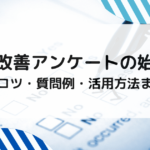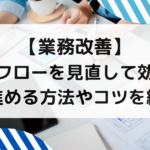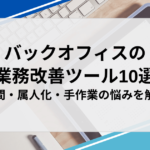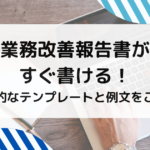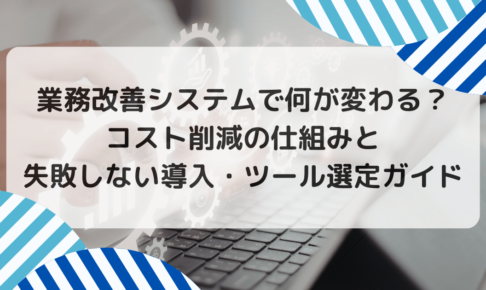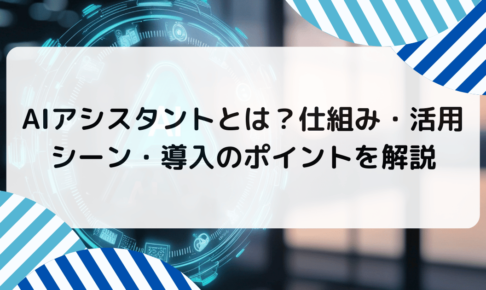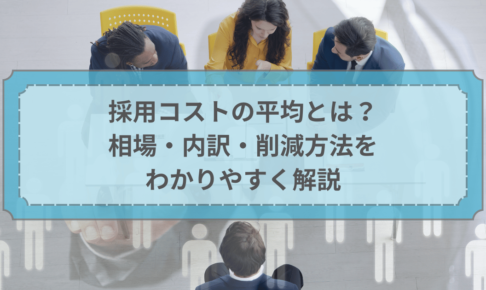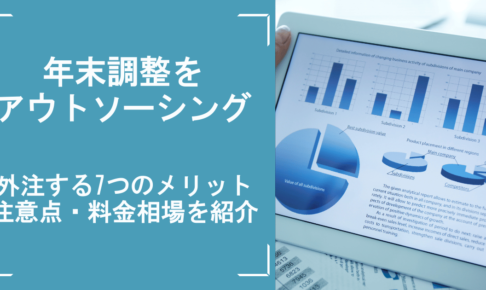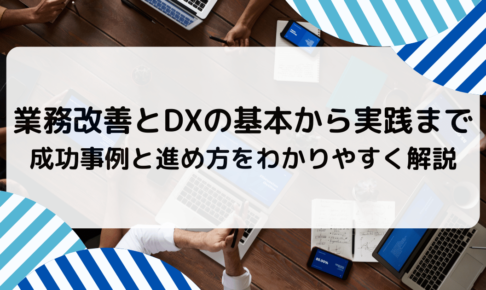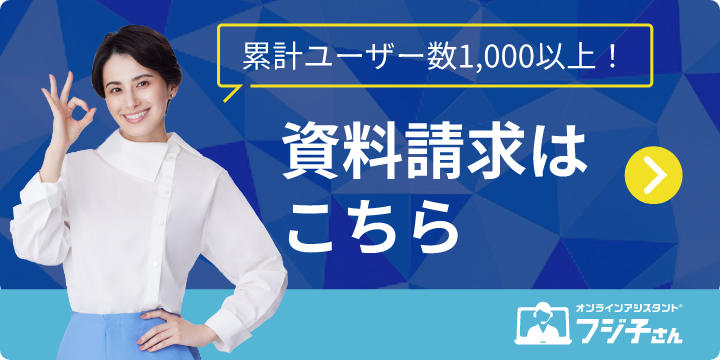生産性の向上や業務の効率化など、業務改善は企業の成長に欠かせません。働き方の見直しや人員不足を補うための労働生産性の改善は、多くの企業でこれまで以上に重要な課題になっています。
しかし、一口に業務改善といっても「どこから手を付けていいかわからない」「日々の業務を行いながらではなかなか進まない」といったお悩みも多いのではないでしょうか。
本記事では、業務改善の進め方、具体例から、成功のためのポイントまで具体例を交えて解説しています。業務改善を検討している方は、ぜひ参考になさってください。
目次
業務改善とは?

業務改善とは、日常業務の流れや手順を見直し、無駄を排除して効率化を図る取り組みです。
特別なスキルや高額なシステム投資が必要なわけではなく、誰でも「できることから少しずつ」始められる点が特徴です。特に中小企業やスタートアップのようにリソースが限られている現場では、日々の業務改善が生産性向上と事業成長のカギになります。
定義と基本の考え方
業務改善とは、現状のプロセスを大きく壊すことなく、無駄や非効率を取り除いて「よりよい状態」に変えていくことを意味します。業務そのものをゼロベースで作り直す「業務改革(BPR)」とは異なり、比較的スモールステップで進められるのが特徴です。
例えば、社内の資料共有に時間がかかっている場合、ファイルの保存ルールを整えたり、クラウドストレージを導入したりするだけで改善につながります。このように、まずは「現状を否定せず、工夫によって少しずつ良くしていく」姿勢が業務改善の基本です。
また、業務改善は一度きりでは終わりません。小さな工夫を積み重ね、変化にあわせて何度も見直すことで、企業の成長や競争力強化につながっていきます。
QCDの視点から見る業務改善の目的
業務改善を考える際には、「QCD」という3つの要素が重要になります。
QCDとは、Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)の頭文字を取った言葉です。
- Quality(品質):仕事の成果物やサービスのクオリティを維持・向上させること
- Cost(コスト):人件費、作業コスト、材料費などを最適化すること
- Delivery(納期):成果物をより早く、確実に届ける体制を整えること
例えば、見積書作成に無駄な手間がかかっている場合、テンプレート化や自動作成ツールを導入することで、作業時間を短縮(Delivery)しつつ、ミスを減らして品質(Quality)も高められます。
また、作業時間削減による残業削減がコスト(Cost)最適化にも直結します。つまり、業務改善は「速く・安く・質高く」を同時に実現することを目指す活動なのです。
業務改善はなぜ必要なのか?現場が直面する背景

近年、業務改善の重要性はますます高まっています。その背景には、社会情勢や働き方、経営環境の急激な変化が大きく関係しています。ここでは、現場が直面している課題を整理し、なぜ今すぐ業務改善に取り組む必要があるのかを掘り下げます。
働き方の多様化と人手不足
リモートワークや副業の普及により、企業は多様な働き方に対応する必要があります。一方で、少子高齢化に伴う人手不足も深刻化しており、「限られた人数で成果を上げる」ことが当たり前になりつつあります。
例えば、営業部門では従来の訪問営業だけでなく、オンライン商談を組みあわせて対応時間を最適化する取り組みが進んでいます。また、バックオフィス業務でも、経理や人事の業務を一部アウトソーシングするなど、効率化の工夫が求められています。
人手が限られるからこそ、無駄な作業を減らし、一人ひとりが本当に価値を生む業務に集中できる環境づくりが欠かせません。
長時間労働の是正
働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限が設けられました。長時間労働でカバーする働き方は、今や時代遅れとなっています。
例えば、毎月発生する手作業のデータ集計作業を、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で自動化する取り組みが進んでいます。単純作業を減らすことで、社員の負担を軽減しながら、生産性の向上と働き方改革の両立を実現するできます。
業務改善は「時間をかけて頑張る」から「時間内に成果を出す」働き方への転換を支える取り組みでもあるのです。
リモート対応やリスク管理の必要性
新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの企業がリモートワーク体制を整えました。しかし、急ごしらえのリモート対応では業務の非効率が露呈することも少なくありませんでした。
例えば、書類への押印を求めるフローがボトルネックになり、業務が停滞するケースが目立ちました。このような課題を解決するためには、業務プロセスそのものを見直し、ペーパーレス化や電子承認システムの導入など、根本的な改善が必要です。
また、自然災害やサイバー攻撃といったリスクにも備えるため、業務の標準化・マニュアル化を進めることが求められています。
業務改善で得られる効果とメリット

業務改善に取り組むことで、単に作業がスムーズになるだけではありません。組織全体のパフォーマンス向上や、働く人たちの満足度向上など、多方面にポジティブな効果をもたらします。ここでは、具体的なメリットを整理してご紹介します。
業務効率がアップする
業務改善の最大のメリットは、業務スピードと正確性の向上です。例えば、これまでメールでやり取りしていた情報共有をチャットツール(SlackやChatwork)に切り替えるだけで、レスポンス速度が格段に上がり、作業待ち時間を大幅に短縮できます。
また、業務フローの見直しによって、「担当者が不在のため進まない」「どの順番で対応すればいいか分からない」といった停滞が減り、全体のスムーズな連携が実現します。
結果として、同じ労力でもより多くの成果を出せるようになります。
コストを最適化できる
無駄な作業時間を減らすことで、残業代や人件費の削減が期待できます。また、紙ベースだった書類管理をデジタル化すれば、印刷コストや保管スペースの節約にもつながります。
さらに、業務の無駄を排除することで、外注費や材料費といった直接コストだけでなく、隠れた間接コストも抑えることが可能になります。中小企業やスタートアップにとっては、こうした積み重ねが経営基盤の安定化に直結します。
労働環境が改善する
単純作業や無駄な待ち時間が減ることで、社員一人ひとりのストレスが軽減されます。特に「無駄な作業に追われて本来の仕事に集中できない」という不満が解消されると、働くモチベーションが向上し、組織全体の雰囲気も明るくなります。
さらに、過重労働のリスクが減るため、離職防止にもつながります。結果として、人材の定着率が高まり、採用・教育コストの抑制にも好影響を与えます。
現場で使える!業務改善の考え方と進め方

業務改善を成功させるには、正しいステップを踏むことが大切です。一度に大規模な改革を目指すのではなく、小さな改善を積み重ねることで、無理なく定着させるられます。ここでは、現場で実践できる業務改善の基本プロセスをご紹介します。
業務を見える化する
まず最初に行うべきは、業務内容の「見える化」です。誰が・どの作業を・どのタイミングで・どのように進めているかを明確にし、全体像を把握します。
例えば、業務フロー図を作成したり、タスク管理ツールで作業を可視化したりする方法があります。これにより、どこに無駄が潜んでいるか、どこでボトルネックが発生しているかが見えてきます。
見える化を行う際は、実際に現場で働いているメンバーの声を拾いながら進めることが重要です。机上の理論ではなく、リアルな業務実態を把握することが改善への第一歩になります。
ムダ・ムリ・ムラを見つける
業務が見える化できたら、次は「ムダ・ムリ・ムラ」を洗い出します。これは、トヨタ生産方式でも有名な考え方で、以下のように分類されます。
- ムダ:なくても問題ない作業(例:無意味な報告書作成)
- ムリ:担当者に過剰な負担がかかっている作業(例:一人に業務が集中)
- ムラ:作業のばらつきや効率の悪さ(例:担当者によって対応時間が違う)
例えば、ある業務に1日かかる人と3日かかる人がいる場合、その業務にムラがあることがわかります。このように、非効率の原因を細かく分析していくことが重要です。
改善策を立てて優先順位を決める
洗い出した課題に対して、どのような改善策を講じるかを検討します。ただし、すべての課題を一度に解決しようとすると、かえって現場に負担がかかります。
そこで重要なのが、改善施策に「優先順位」をつけることです。例えば、影響度が大きいもの、効果が出やすいものから順に取り組むようにします。優先順位を決める際には、以下の2軸で評価するとわかりやすくなります。
- インパクト(効果の大きさ)
- 実行のしやすさ(コスト・手間の少なさ)
「小さなコストで大きな効果が期待できる施策」から着手するのが成功のコツです。
小さく始めて実行する
業務改善は、「完璧な計画」を立てるよりも、「まず小さく始める」ことが重要です。いきなり大規模な改革を目指してしまうと、関係者の負担が増えたり、現場の反発を招いたりして、頓挫するリスクが高まります。
例えば、業務のペーパーレス化を進めたい場合、いきなり全社導入を目指すのではなく、まずは一部部署だけでテスト導入してみるとよいでしょう。実際に小規模で回してみることで、想定していなかった課題や、改善ポイントが見えてきます。
また、「小さな成功体験」を積み重ねることで、現場のモチベーションも高まり、自然と業務改善への理解と協力が得られるようになります。「最初の一歩を軽くする」──これが、業務改善成功の大きなカギです。
評価し、継続的に見直す
業務改善は、一度やって終わりではありません。実施した改善策が本当に効果を上げているか、定期的に振り返ることが不可欠です。
例えば、KPI(重要業績評価指標)を設定し、改善前後で数値変化を比較する方法があります。「タスク完了までの平均日数」「エラー発生率」「対応件数」など、業務内容に応じた指標を設定して、客観的に効果を検証しましょう。
また、実行した改善策が思ったような効果を出せなかった場合も、失敗と捉えるのではなく「次の改善につなげる」ことが重要です。PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを意識して、常に業務をブラッシュアップし続ける姿勢が求められます。
業務改善に役立つフレームワーク集
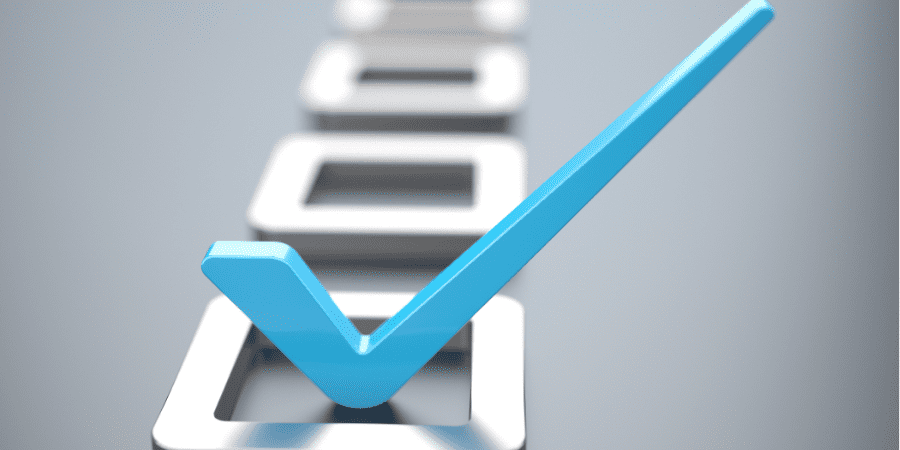
業務改善を効率的に進めるためには、便利なフレームワーク(考え方の枠組み)を活用するのが効果的です。ここでは、特に初心者でも取り入れやすい代表的なフレームワークをご紹介します。
PDCAサイクル
PDCAサイクルは、改善活動の基本ともいえる手法です。
- Plan(計画):どのような改善を行うか、目標と手順を決める
- Do(実行):計画に沿って実際に行動する
- Check(評価):実行結果を検証し、目標達成度を確認する
- Action(改善):検証結果をもとに、さらに改善策を講じる
この流れを繰り返すことで、業務の質を段階的に高めていけます。例えば、営業活動の効率化を目指す場合、まず訪問件数と成約率の関係を計測し、改善ポイントを特定する……といった形で活用できます。
KPT(Keep/Problem/Try)
KPTは、シンプルな振り返りフレームワークです。
- Keep:うまくいったこと、今後も続けたいこと
- Problem:課題やうまくいかなかったこと
- Try:次に試してみたいこと
例えば、定例会議の後に「今回よかった進め方(Keep)」「時間が足りなかった点(Problem)」「アジェンダ配布を早める(Try)」というように整理すると、次回以降の改善につながります。小さな業務改善を習慣化するのに便利な手法です。
ECRS(排除・結合・再配置・簡素化)
ECRSは、業務を見直すときに「どの観点で改善できるか」を整理するためのフレームワークです。
- Eliminate(排除):不要な作業をなくす
- Combine(結合):作業をまとめて効率化する
- Rearrange(再配置):作業の順番や担当を見直す
- Simplify(簡素化):作業手順を簡単にする
例えば、書類作成・承認・提出という一連の流れを見直し、承認手続きをオンライン化することで「排除」と「簡素化」を同時に実現できます。ムダを徹底的に省く思考法として、多くの現場で活用されています。
バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、企業活動全体を「価値を生み出す工程」と「そうでない工程」に分け、改善ポイントを特定する手法です。
- 製品開発
- 購買活動
- 生産活動
- マーケティング・販売
- サービス提供
このようなプロセスを一つずつ洗い出し、それぞれが顧客への価値提供にどう寄与しているかを検討します。無駄なプロセスがあれば省き、付加価値の高い部分にリソースを集中させることで、全体最適を図れます。
まず取り組みたい!業務改善の具体例6選

業務改善といっても、いきなり大きな改革を目指す必要はありません。ここでは、比較的取り組みやすく、効果が出やすい業務改善の具体例を6つご紹介します。まずはできるところから、着実に実践していきましょう。
分業化する
業務が一部の担当者に偏っていると、負担が集中し、効率が悪くなります。そこで、作業内容を細かく分解し、それぞれの工程を複数人で分担する「分業化」が有効です。例えば、請求書処理業務であれば、以下のように工程を分けられます。
- 請求データの入力
- 請求書の発行
- 顧客への送付
- 入金確認・管理
このように役割を分担することで、ひとりに負担が集中せず、スムーズに作業が進むようになります。また、特定の担当者に依存しない体制を作れるため、業務の属人化防止にもつながります。
ペーパーレス化を進める
紙の書類を使っていると、印刷・保管・郵送などに時間もコストもかかります。これらを電子化することで、大幅な業務効率化が期待できます。
例えば、契約書の電子化(電子契約サービスの導入)や、稟議書のオンライン承認システムへの移行などです。特にリモートワークが普及した現在では、ペーパーレス化は単なる効率化にとどまらず、業務継続性(BCP対策)にも役立ちます。
まずは「社内稟議」や「勤怠管理」など、身近な書類からペーパーレス化を進めると、スムーズに浸透させられるでしょう。
マニュアルを作成する
「やり方を聞かないと作業できない」という状況は、業務の属人化と非効率を招きます。
そこで、業務手順を標準化し、マニュアル化することが効果的です。マニュアル作成のポイントは、「新しく入った人でも読めばわかるレベル」に落とし込むことです。
また、テキストだけでなく、図やスクリーンショットを多用して視覚的に理解できるようにすると、より実用的なマニュアルになります。マニュアルがあれば、新人教育の効率も格段にアップし、引き継ぎの際のトラブルも防げます。
テンプレート化する
よく使う書類やメール文面は、都度ゼロから作成するのではなく、テンプレート化しておくと効率的です。例えば、
- 見積書・請求書のフォーマット
- 顧客向けお知らせメールの定型文
- 社内会議議事録テンプレート
こうしたテンプレートをあらかじめ用意しておけば、作成ミスも防げるうえ、作業時間を大幅に短縮できます。業務内容に応じてテンプレートを整理し、社内で共有する仕組みを作ると、さらに効果的です。
ITツールを導入する
作業をアナログで進めていると、どうしても非効率が生まれがちです。そこで、業務内容に応じたITツールの導入を検討してみましょう。
例えば、以下のような比較的安価かつすぐに使えるツールも多くあります。
- タスク管理ツール(例:Trello、Asana)
- 情報共有ツール(例:Slack、MicrosoftTeams)
- 経費精算ツール(例:マネーフォワードクラウド経費)
ただし、導入時は「使い方を社内で統一する」「最初にしっかり運用ルールを決める」ことがポイントです。
アウトソーシングを活用する
社内リソースだけで業務を回そうとすると、どうしても限界が来ます。特に専門性が高い業務や、繁忙期の一時的な業務負荷には、外部リソースを活用するのも有効です。
オンラインアシスタントサービスを活用することで、以下のような業務を外部に任せられます。
- データ入力
- 調査・リサーチ
- スケジュール調整
これにより、社内メンバーは本来のコア業務に専念でき、生産性を最大化できるでしょう。
【関連記事】
業務改善の具体例7選│どこから始めるべき?業務改善のアイデア&効果的な手法を解説
改善提案を通すためのコツ

業務改善は一人で完結するものではありません。現場の協力や上司の承認を得ながら進める必要があり、そのためには「改善提案を通す力」も求められます。ここでは、提案を成功させるためのポイントを解説します。
「文句」と「提案」の違いに気を付ける
業務改善の提案が通らない大きな原因のひとつが、「単なる不満の表明」になってしまうことです。「ここがダメだ」「あれが使いにくい」と問題点だけを指摘すると、受け取る側はネガティブな印象を持ってしまいます。
重要なのは、「問題提起+具体的な改善案」をセットで提示することです。
- ✖「このシステム、使いにくいです」
- ◎「このシステムの申請フローを短縮すれば、申請時間を30%削減できそうです」
このように建設的な提案スタイルを心がけましょう。「課題に対して主体的に解決策を考えている」という姿勢が伝われば、提案はぐっと通りやすくなります。
チームや上司を巻き込むよう工夫する
業務改善は、提案者一人の力だけでは成功しません。周囲の理解と協力を得るために、チームや上司を巻き込む工夫が必要です。例を挙げるなら以下のアプローチが効果的です。
- 現場メンバーと課題を共有し、改善案を一緒に考える
- 小さな改善を実施し、成果を見せてから上司に本格提案する
- 「この改善によってチーム全体が楽になる」という視点で話す
特に上司に提案する際は、「コスト削減」「業務効率化」「コンプライアンス強化」など、会社にとってのメリットを明確に伝えると説得力が高まります。
【関連記事】
これで伝わる!業務改善提案書をパワーポイントで作る方法【無料テンプレートプレゼント】
業務改善を成功させるための注意点

業務改善は、やみくもに進めると失敗するリスクもあります。ここでは、実践時に気を付けるべきポイントを整理します。
一度の改善で終わらせない
業務改善は一度きりで完結するものではありません。最初に設定した改善策が常にベストとは限らず、時間の経過とともに状況も変化します。
そのため、以下のような姿勢が欠かせません。
- 「まず試してみる」
- 「定期的に効果を検証する」
- 「さらに良くできないか考え続ける」
改善活動を継続的に行うことで、組織全体の成長にもつながります。
現場の声を無視しない
現場の実情を無視して机上の空論だけで改善を進めると、現場からの反発を招き、結局定着しません。実際に作業している社員から「ここを変えるなら、この工程も変えないと現場が回らない」というようなリアルな意見が出てくることもあります。
改善を進める際には、現場メンバーのヒアリングを欠かさず、フィードバックを取り入れながら柔軟に修正していくことが大切です。
改善範囲を広げすぎない
あれもこれもと手を広げすぎると、結局どれもうまくいかない結果になりがちです。業務改善は「範囲を絞る」「優先順位をつける」ことが成功の秘訣です。
まずは「最も影響の大きいボトルネック」を見つけ、そこから着実に改善を進める。この積み重ねが、最終的に大きな成果へとつながります。
よくある質問(Q&A)
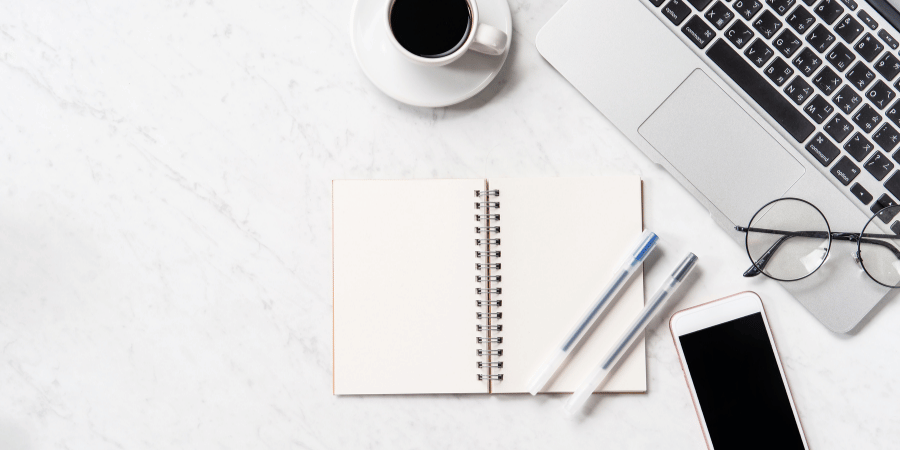
業務改善に取り組むにあたって、特に初心者が疑問に思いやすいポイントをまとめました。
新人が業務改善を提案してもいいの?
もちろん可能です。むしろ、新人だからこそ「なぜこのやり方なのか?」という疑問を持ちやすく、改善のチャンスを見つけやすい立場にあります。
ただし、提案の際は「現場の事情を理解した上で」「チーム全体のメリットを意識して」伝えることが大切です。生意気と受け取られないよう、敬意を持って提案する姿勢を忘れないようにしましょう。
業務改善を上司に反対されたらどうすればいい?
すべての改善提案がすぐに受け入れられるわけではありません。反対された場合は、一度引き下がり、次のようなアプローチを取りましょう。
- 改善案を小さく分割して提案する(段階的な導入を提案)
- データを示して説得する(数値で効果を裏付ける)
- 上司のメリットを強調する(負担軽減や成果向上をアピール)
「なぜ反対されたのか」を冷静に分析し、次の提案につなげる姿勢が大切です。
どこから手をつければいいかわからない
まずは「業務の見える化」から始めましょう。いきなり改善策を考えるのではなく、現状の業務フローを洗い出すことで、課題やムダが自然と見えてきます。
- 「時間がかかりすぎている作業」
- 「ミスや手戻りが多い作業」
- 「担当者によって差が出やすい作業」
特に上記の内容などに注目すると、優先的に改善すべきポイントが見つかりやすくなるはずです。
社内で進めるのが難しい場合は外部サービスも活用を

どんなに業務改善の意欲があっても、「人手が足りない」「日常業務に追われて改善に手が回らない」という現場は少なくありません。そんなときは、無理に自社だけで抱え込まず、外部サービスの力を借りる選択肢を検討しましょう。
リソースが足りないときの選択肢
業務改善はスピードが重要です。対応が後手に回れば、現場の不満が蓄積したり、せっかくの改善機運が失われたりする恐れもあります。リソースが足りないときは、
- 業務設計やマニュアル作成を外部コンサルに依頼する
- RPA導入やツール活用をサポートする業者に支援してもらう
- 業務の一部をアウトソーシングする(例:バックオフィス業務)
といった手段をうまく活用することで、改善活動を加速させることが可能です。
特に日常の定型業務を手放すことで、社内の人材をコア業務に集中させられるメリットは大きいです。
「フジ子さん」を利用して業務改善に取り組む余裕を

「業務改善に取り組みたいが、日々の業務に追われて時間がとれない……」そんな現場の悩みを、低コストかつスピーディーに解決できる手段としておすすめなのがオンラインアシスタントサービス「フジ子さん」です。
フジ子さんは、幅広い業務支援をオンラインで提供しています。例えば、マニュアル化できる事務処理などのノンコア業務をフジ子さんに任せれば、自分にしかできないコア業務に集中することができます。
フジ子さんは必要なときに必要な量だけ依頼できるため、固定費を抑えつつ柔軟にご利用いただけます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
まとめ

業務改善は、「特別なスキルがないとできないもの」ではありません。現状を見直し、無駄を減らし、より良くしていく意識を持つだけで、誰でも取り組めます。
ポイントは、以下の通りです。
- 小さな改善から着実に始めること
- 継続的に見直しながら進めること
- 周囲を巻き込み、チーム全体で改善に取り組むこと
もし「やりたいけど、時間がない」「人手が足りない」と悩んでいるなら、外部リソースの活用も視野に入れてみましょう。オンラインアシスタント「フジ子さん」なら、あなたの業務改善を強力にサポートします。まずは気軽に資料請求・お問い合わせください。
小さな一歩が大きな成果への第一歩です。今こそ、業務改善に踏み出してみましょう!