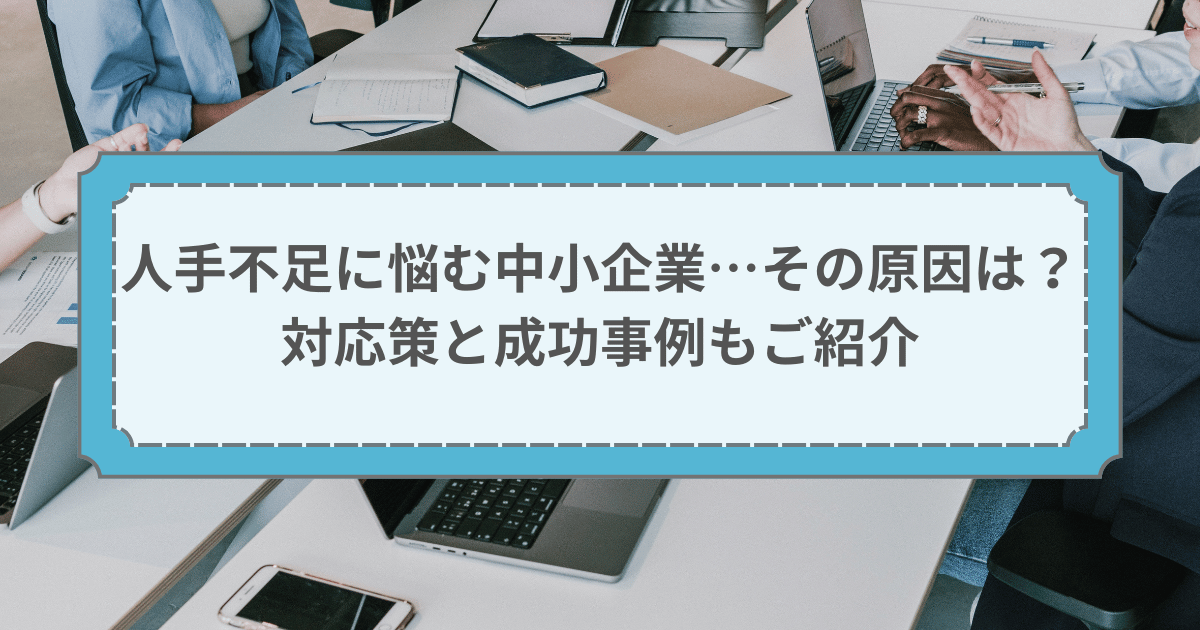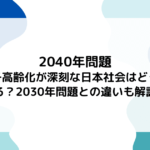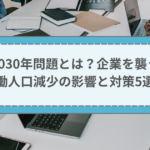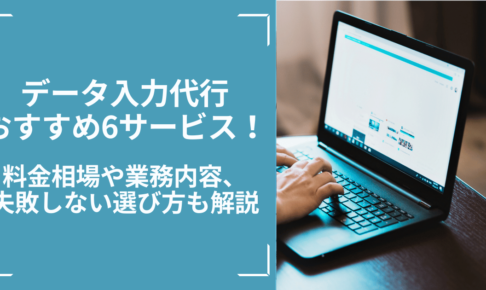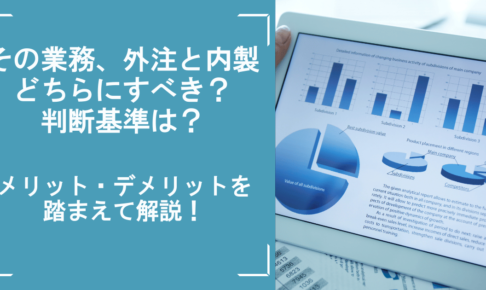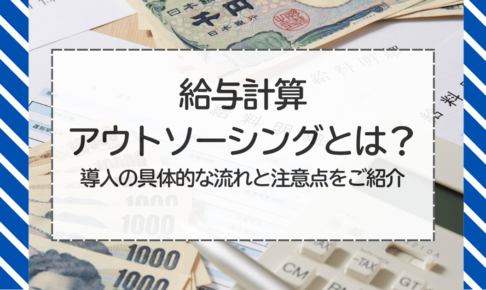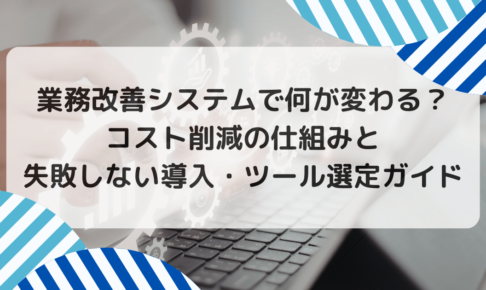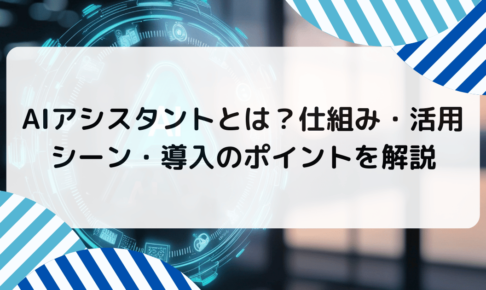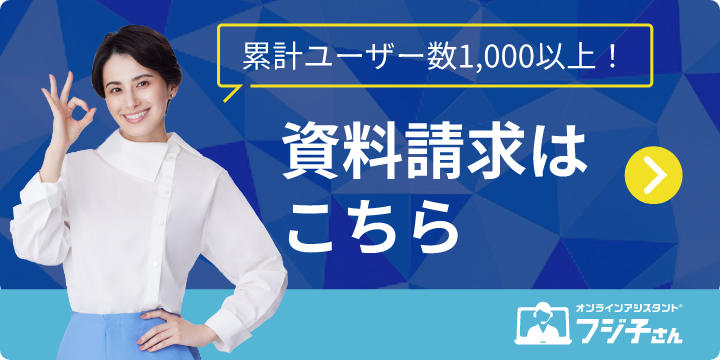中小企業は10年以上にわたって深刻な人手不足に直面しており、多くの経営者にとって事業運営の大きな課題となっています。
本記事では、中小企業が抱える人手不足の現状を具体的なデータとともに紹介し、少子高齢化や労働人口の減少といった主な原因について詳しく解説します。
また、人手不足を解消するためのポイントや、人手不足解消に成功した企業の事例もご紹介します。
持続可能な事業運営を実現するためのヒントをお探しの方はぜひご覧ください。
目次
データから見る中小企業の人手不足の現状
まずは、中小企業の人手不足に関するデータから現状を解説します。
従業員の過不足具合
2024年版「中小企業白書」によると、人手不足の現状は下図のようになっています。
出典:2024年版「中小企業白書」第4章第1部 中小企業・小規模事業者が直面する課題と今後の展望
オレンジ色が従業員の過不足です。中小企業が四半期ごとの従業員数を「過剰」と答えたか「不足」と答えたかを%で表しています。数値が高いほど、人員が足りているわけです。これを見ると、2011年以降は常にマイナスで、人手不足の状態が10年以上続いていることがわかります。
現場にいると人手不足をひしひしと感じると思いますが、こうして数字で見ても、日本全体で人手不足が深刻な問題となっていることがわかります。
どのような人材が不足しているか
次に、どのような人材が不足しているかを見ていきましょう。下図をご覧ください。
出典:2024年版「中小企業白書」第2部第1章 人への投資と省力化
「中核人材」とは、管理職、専門職などを指します。7割を超える中小企業が、この中核人材が不足していると回答しています。
また通常業務を行う人材が不足していると感じている企業も6割を超えていることから、中小企業がいかに人材不足に悩んでいるかがうかがえます。
中小企業の人手不足が続いている原因
中小企業の人手不足が10年以上も続いてしまっている原因には以下のようなものがあります。
- 少子高齢化による労働人口の減少
- 業種別の人手不足の深刻さ
- 中小企業と地方企業の特有の課題
少子高齢化による労働人口の減少
日本では少子高齢化が急速に進行しており、2065年には生産年齢人口(15~64歳)が2020年の7,509万人から約4割減少して4,529万人になると予測されています。(引用:令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少 総務省)
生産年齢人口、つまり労働人口の減少により、すでに中小企業は人材確保が一層困難になっています。人手不足により業務の効率化が求められる一方で、従業員一人ひとりの負担が増加し、モチベーションの低下や離職率の上昇といった問題が発生しています。
中小企業は新たな採用戦略の導入や業務の自動化など、持続可能な経営に向けた取り組みを行う必要があります。
業種別の人手不足の深刻さ
調査された全ての業種で人手不足という結果がでていますが、業種によってその深刻さは異なります。
出典:労働経済動向調査(令和6年8月)図2 産業別正社員等労働者過不足判断D.I. 厚生労働省
こちらのグラフは、業種によって人手不足感が異なることを示しています。ポイントが多いほど、人手不足が深刻な業界であると言えます。特に、医療・福祉、運輸業・郵便業、建設業、学術研究の業種では人手不足が顕著です。
それぞれの業種で人手不足を引き起こしている原因は異なりますが、共通する要因として「労働条件の厳しさ」「高齢化・労働力の減少」「資格・スキルの必要性」などが挙げられます。
| 業種 | 主な人手不足の理由 |
| 医療・福祉 | 高齢化による需要増加、過酷な労働環境、資格の必要性 |
| 運輸業・郵便業 | 長時間労働、物流需要の増加(2024年問題)、高齢化 |
| 建設業 | 高齢化・後継者不足、厳しい労働環境、インフラ老朽化対応 |
| 学術研究 | ポスト不足、研究資金の減少、海外流出 |
中小企業と地方企業の特有の課題
中小企業の中でも、特に地方の企業における人手不足には特有の課題が原因となっています。それは人口減少と都市部への若年層の流出です。
特に地方では少子高齢化が進み、働き手の確保が難しくなっています。
地方における人口減少と高齢化の進展は顕著であり、2045年には、65歳以上人口の割合は、首都圏で30%台であるのに対し、地方では40%を超えると予測されている。(引用:令和4年版 情報通信白書|地方における少子高齢化 総務省)
また、地方の中小企業は給与や福利厚生が都市部の企業と比べて魅力に欠けることが多いため、人材確保が困難です。さらに、公共交通機関の利便性が低く、通勤が不便なことも、新規採用や定着率の低下を招いています。
人手不足が中小企業に与える影響
人手不足は中小企業に以下のような大きな影響を与えます。
- 売上機会の損失
- 残業時間の増加など労働環境の悪化
- 商品・サービス品質の低下
- 倒産リスクの上昇
売上機会の損失
人手不足が直接的に売上機会の損失につながる例として、注文処理の遅延やサービス提供の遅れが挙げられます。
例えば、受注増加に対応できる人員を確保できず、納期遅延が発生。その結果、顧客の信頼を失い、リピーターの減少や新規顧客獲得の機会を逃す、という事態も起こりうるのです。
商品・サービス品質の低下と倒産リスク
人手不足は、中小企業の品質管理にも大きな影を落とします。
例えば、製造業では、人員不足によって品質検査がおろそかになり、不良品の増加につながる可能性があります。実際に、人手不足が原因で検査工程を簡略化した結果、重大な製品欠陥が見逃され、リコールに発展したケースも少なくありません。
また、サービス業では、スタッフ不足によってお客様一人ひとりに丁寧なサービスを提供することが難しくなり、顧客満足度の低下を招くリスクがあります。例えば、レストランであれば、注文ミスや料理提供の遅延などが発生しやすくなり、お客様に不快な思いをさせてしまう可能性があります。
このような不良品の増加やサービスの質の低下が続けば、顧客離れが進み、売上が減少していくことは避けられません。さらに、企業の評判が悪化し、取引先の信用を失うことにもなりかねません。品質の低下は、企業の信頼性を揺るがす大きな問題であり、最悪の場合、倒産へとつながる可能性も孕んでいるのです。
これを防ぐためには、適切な人材確保と品質管理体制の強化が不可欠です。人材不足の解消によって従業員一人ひとりの負担を軽減し、品質管理に十分なリソースを割けるようにすることで、企業としての信頼を守っていくことが重要です。
残業時間の増加など労働環境の悪化と離職率の上昇
人手不足が続くと、従業員の業務負担が増加し残業時間が増加する恐れがあります。過重労働によるストレスが深刻化することも考えられます。従業員の健康やモチベーションが低下すると生産性にも悪影響を及ぼすため注意が必要です。
また、労働環境の悪化は離職率の上昇につながります。離職が続くと、新規採用のコストも増加し長期的な経営の安定性が損なわれるため、人手不足の解消と同時に労働環境の改善への意識も高める必要があります。
人手不足を解消し、持続可能な経営を実現するための対策
人手不足を解消し、持続可能な経営を実現するには単一の施策ではなく、複数の戦略を組み合わせて取り組む総合的なアプローチが必要です。
採用活動と人材育成の見直し
効果的な採用活動を行うためには、採用ターゲットの明確化や採用エリアの拡大が大切です。また、採用後の教育プログラムを充実させることで、長期的な定着率向上につながります。
採用エリアの拡大とターゲットの明確化
採用対象を広げるため、地方の求職者や、リモートワーク・短時間勤務への対応、外国人材の活用などを検討することが効果的です。採用ターゲットを明確にし、適切な採用戦略を策定することが求められます。
ターゲットが明確が明確になったら、効果的な求人の出し方についても検討が必要です。求人サイトにも様々なものがありますので、迷ったときは以下の記事をご参照ください。
【しゅふJOB】無料・有料の求人サイト18選|自社に合った求人掲載方法を解説します
内定者フォローの充実
採用後のフォロー体制を整え、早期離職を防ぐことが重要です。フォローが不足していると、新入社員が適応しにくくなり、業務への不安や孤立感が増す可能性があります。丁寧な研修やメンター制度を導入し、スムーズな定着を支援します。
【関連記事】
中途採用がうまくいかない原因とは?よくある理由と解決策を紹介
業務効率化
業務効率化を図ることで、少ない人員でも一定の業務量を無理なくこなせるようになり、従業員の負担軽減、残業時間の削減、ひいては人件費の削減にもつながります。
業務の自動化やシステム導入によって、これまで人間が時間をかけて行っていた作業を効率化し、生産性を向上させることができます。
特に、単純作業や繰り返し発生する業務は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の活用によって自動化することで、大幅な負担軽減とヒューマンエラーの削減を実現できる可能性があります。
例えば、データ入力、請求書処理、顧客情報管理といった定型業務はRPAで自動化できる代表的な例です。
【関連記事】
アウトソーシングの活用
社内リソースが限られている場合、一部業務を外部委託することで、社内の負担を軽減し、コア業務への集中を強化することができます。
例えば、専門知識や経験が必要とされる 経理や人事業務 をアウトソーシングすることで、これらの業務に精通した外部のプロフェッショナルに任せることができ、社内の業務効率向上やコンプライアンス強化を図ることが可能です。
また、 顧客対応業務 を担うコールセンター業務を外部委託することで、顧客満足度の向上や応対品質の均一化、業務の効率化を実現できる可能性があります。
さらに、 物流業務 を外部委託することで、在庫管理、梱包、発送などの業務を効率化し、コスト削減や配送時間の短縮、サービス品質の向上につながる可能性もあります。
その他にも、システム開発 や Webサイト制作・運用、マーケティング活動 など、様々な業務において外部委託の活用が可能です。
【関連記事】
アウトソーシングとは?メリット・デメリットや契約先の選び方【わかりやすく解説】
外国人材の雇用と活用
外国人労働者の活用は、人材不足の解決策として有効な選択肢となりえます。特に、少子高齢化による労働力不足が深刻化する中で、外国人労働者の受け入れは重要な課題となっています。
外国人労働者を雇用する際には、特定技能在留資格の活用や、外国人雇用に詳しい専門家のサポートを受けることが有効です。 専門家は、ビザ取得のサポートだけでなく、労働条件の整備、文化や習慣の違いを考慮したコミュニケーション方法のアドバイスなど、多岐にわたるサポートを提供しています。
しかし、外国人労働者の雇用には、文化や言語の壁、ビザ取得の複雑さ、労働環境の整備など、考慮すべき点が多く存在します。 外国人労働者が働きやすい環境を整え、相互理解を深めることが、企業の成長と多様性の実現につながるでしょう。
中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドラインの活用
中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン(中小企業庁)は⼈材活⽤に関する課題を解消するためのガイドラインです。このガイドラインでは、経営戦略と連動した「人材戦略」が事業継続の鍵となるという考えのもと、人材戦略の検討方法を3つのステップに分けて解説しています。
⼈材戦略を検討するための3ステップ
- 経営課題と⼈材課題を⾒つめ直す
- ⼈材戦略の検討
- ⼈材戦略の実⾏
多くの企業が抱える10の課題ごとにチェックリストが用意され、検討すべき人材戦略が分かりやすく解説されています。是非一度ご覧ください。
中小企業・小規模事業者人材活用ガイドライン(中小企業庁)
よろず支援拠点の活用
「よろず支援拠点」とは、中小企業の経営に関するあらゆる悩みを相談できる経営相談所です。国によって全国に設置されており、無料で相談できます。
多くの事例をもとにした実現可能な提案により、多くの企業が悩みを解決しています。
中小企業・小規模事業者の人材活用事例
ここからは、人手不足解消のための取り組みを実施し、実際に成果をあげている企業の事例を3件ご紹介します。ご紹介する事例は中小企業・小規模事業者の人材活用事例集(中小企業庁)を参照しています。
従業員の得意・不得意に合わせた人材配置により生産性が向上
株式会社阿智精機は、部品製造から、機械の組み立てまで一貫して受注する機器メーカーへ業態転換、人材不足に加え、人事評価制度が不明瞭という課題がありました。そこで支援機関と連携しながら、人事・給与・目標制度の改革を実施。その結果従業員の士気が上がるとともに、生産性も向上するという成果をあげています。さらに、従業員の紹介での採用が増え、人材不足も解消されつつあります。
発信力の強化で知名度の向上と採用力の強化を実現
株式会社吉備総合電設は、事業は安定している半面、組織の硬直化・縦割り化の進行という課題を抱えていました。そこで全従業員にヒアリングを実施し、昇格や配置転換などを含む総合的な組織改革を行った結果、従業員のモチベーション向上や組織の活性化に成功しています。また、自社HPのリニューアル、SNSでの積極的な情報発信により、安定的な新卒採用につなげています。
働き方の選択肢を増やすことで専門スキルを持つ人材を採用しやすくなった
キャップクラウド株式会社は、慢性的な人材不足に悩んでおり、他社との差別化を図り、自社の魅力を作る必要がありました。そこで「働き方、パーソナライズ」という企業理念を作り、従業員一人一人の状況に合わせた働き方を選択できるように環境を整備。東京に本社を置きながら、山梨県富士吉田市にサテライトオフィスを開設してリモートワークの希望にも応えることで、U・Iターンの人材も候補に入るなど、人材獲得のチャンスを広げました。学生からも選択されることが多くなり、採用コストの低減にも成功しています。
中小企業の人手不足解消にはフジ子さんもおすすめ

中小企業の人手不足解消には、採用戦略の見直し、業務効率化、柔軟な働き方の導入が重要です。経営戦略にあった人材戦略をたて、人手不足解消を行いましょう。
中でもアウトソーシングは即効性が高く、大きな効果を期待できる有効な手段の一つです。
従来の雇用形態にとらわれず、必要な業務を必要な期間だけ外部に委託することで、人材不足を解消するだけでなく、社員の負担を軽減し、本来集中すべき業務に専念できる環境を整えられます。
当ブログを運営するフジ子さんには、バックオフィス業務だけでなく以下のような専門的な業務もアウトソーシング可能です。
- コール業務
- 経理
- 人事労務
- RPAなどを活用した業務効率化支援 など
ニーズに合わせて、様々な業務を柔軟にサポートしています。
2時間の無料トライアルでフジ子さんをお試しいただくことも可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。