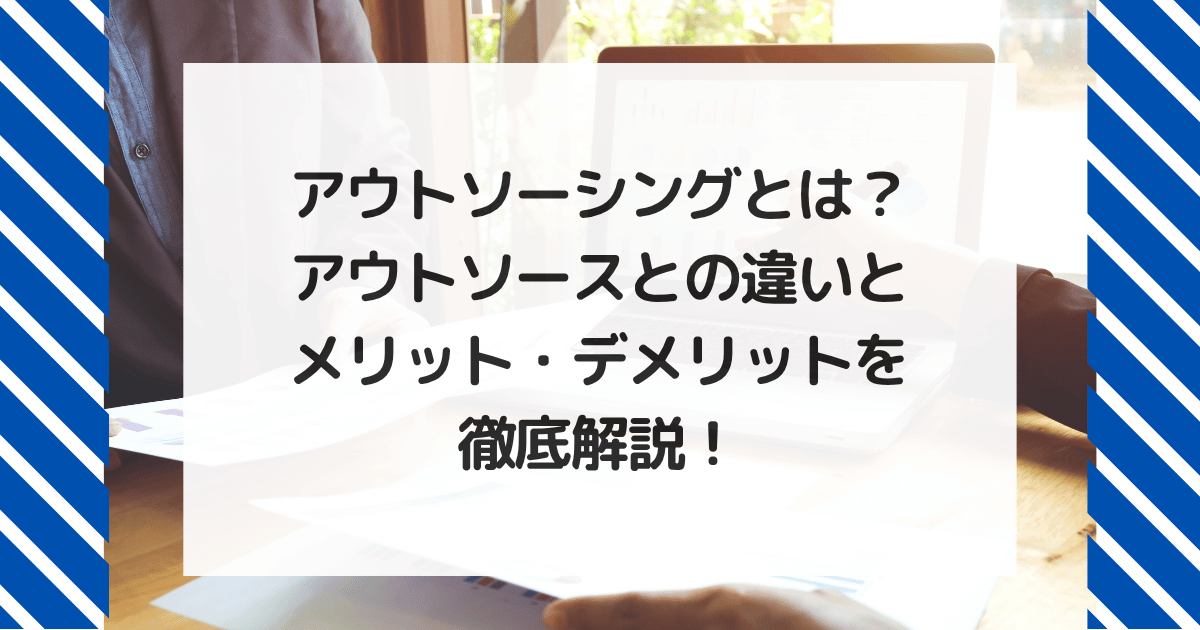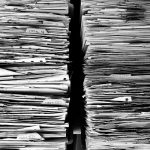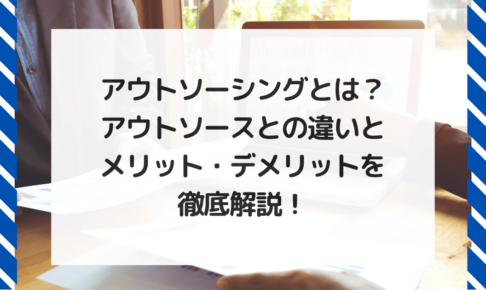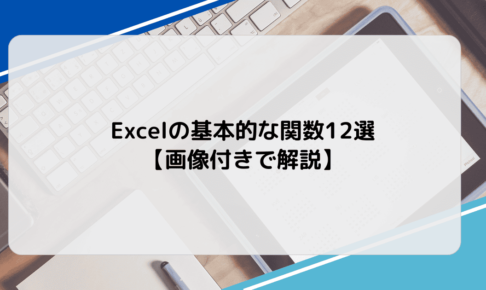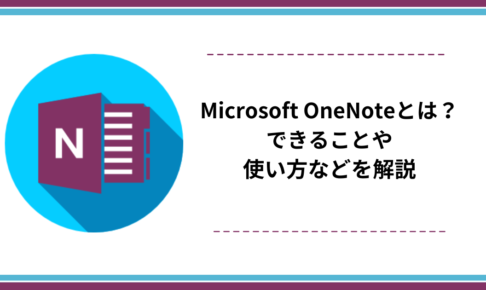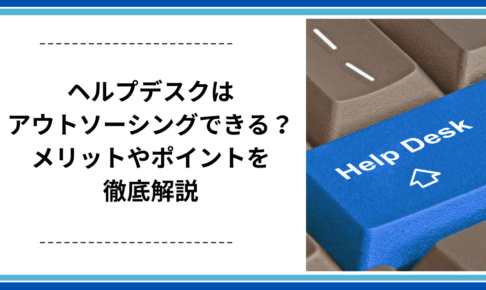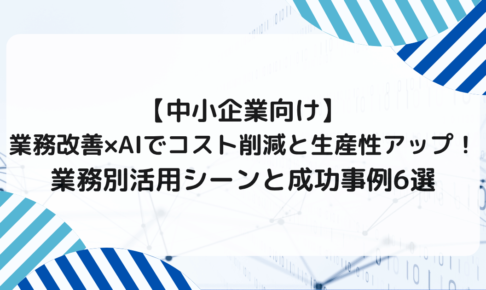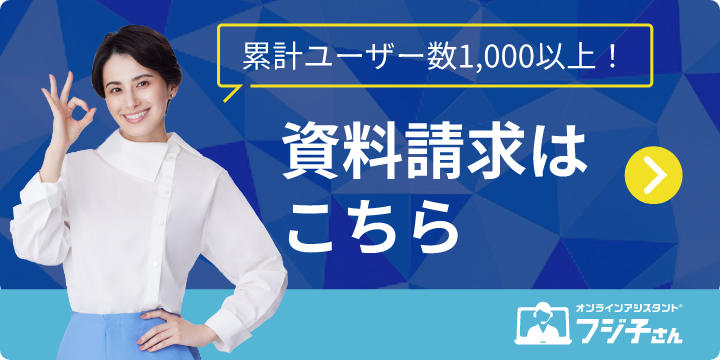「人手が足りない」
「人を雇う以外によい方法はないだろうか……?」
このような課題を持つ企業にとって、有効な手段の1つがアウトソーシング(業務の外部委託)です。
アウトソーシングは、業務効率化や人材不足の解消に役立つだけでなく、専門性の高い業務をプロに任せることで、業務品質の向上も期待できます。
本記事では、主にバックオフィス業務のアウトソーシングを検討している方向けて、アウトソーシングの定義と依頼できる業務、契約の種類、メリット・デメリットまで、わかりやすく解説します。
自社のリソースやノウハウに課題を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
アウトソーシングとは外部に業務を委託すること

アウトソーシングとは、簡単に言うと「外注」です。企業が自社で行っていた業務の一部、または全部を外部の業者に委託することを指します。近年、企業の経営効率化や人手不足解消を目的として、幅広い業種でアウトソーシングが導入されています。
以下のグラフからわかるように、環境・防犯関連、情報処理のような専門的なサービス、事務処理といったマニュアル化が可能な業務のアウトソーシングが進んでいるようです。
引用元:「経済社会と働き方の変化等について/アウトソーシングの現状」(厚生労働省)
アウトソーシングとアウトソースの違い
アウトソーシングとは別に、「アウトソース」という言葉を耳にすることもあるのではないでしょうか?アウトソーシングとアウトソースは、ほぼ同義です。ただし、アウトソーシングは業務を委託するビジネス戦略として広く用いられていますが、アウトソースは業務を委託する行動そのものを指しています。
一方、単純なコスト削減を目的とした下請け外注は、アウトソースともアウトソーシングとも異なります。
アウトソーシングと人材派遣の違い
アウトソーシングと人材派遣もよく比較される概念です。
両方とも外部の力を活用するという点では共通ですが、厳密には異なります。人材派遣は許可を受けた者しか派遣業を運営できませんが、アウトソーシングはその縛りがありません。
違いを簡単にまとめてみました。
| 項目 | アウトソーシング | 人材派遣 |
| 契約形態 | 業務委託契約 | 労働者派遣契約 |
| 業務の指示者 | 指揮命令関係はない※雇用契約ではないので、依頼元の企業から直接指示することはできない | 指揮命令関係あり※派遣先企業の指揮命令に従う |
| 責任の範囲 | 準委任契約:業務を行う契約。最終的に結果や成果物に繋がらない場合もある。請負契約:結果や成果物を納める。 | 派遣先企業:業務の遂行、結果、衛生管理について責任を負う。派遣元:労働時間の管理、給与の支払いなど |
アウトソーシングでは「業務委託契約」(準委任契約または請負契約)、人材派遣は「労働者派遣契約」で契約を結びます。また、アウトソーシングは作業者に直接指示ができませんが、人材派遣では依頼した企業による直接指示が可能です。
加えて、両者は責任の所在も異なります。アウトソーシングは準委任契約や請負契約が多いですが、人材派遣の場合、業務責任は派遣先企業、雇用に関する責任は派遣元企業が負います。
アウトソーシングと人材派遣の違いについては、以下の記事もあわせてご一読ください。
【関連記事】
アウトソーシングと人材派遣の違いとは?意味やメリット、使い分け方などを解説
派遣と請負は何が違う?メリット・デメリットや委託・委任・嘱託との違いも解説!!
アウトソーシングの種類

アウトソーシングの種類は、業務内容によって細かく分類されています。
| 略語(正式名称) | 内容 | 主な例 |
| BPO(ビジネス プロセス アウトソーシング) | 業務プロセス全体または一部を外部に委託する | コールセンター運営、会計処理、人事管理 など |
| RPO(リクルートメント プロセス アウトソーシング) | 採用活動の全体または一部を外部に委託する | 求人広告掲載、応募者選考、面接 など |
| KPO(ナレッジ プロセス アウトソーシング) | マニュアル化しにくい知的業務処理を外部に委託する | 企画、業務改革 など |
| ITO(インフォメーション テクノロジー アウトソーシング) | 情報システムの運用・管理を外部に委託する | サーバー管理、セキュリティ対策 など |
| SPO(セールス プロセス アウトソーシング) | 営業活動の全体または一部を外部に委託する | 顧客への提案、受注、アフターフォロー など |
| LPO(リーガル プロセス アウトソーシング) | 法務事務を外部に委託する | 契約書作成、法的チェック(※弁護士へ依頼時は委任契約) |
特定の分野専門のアウトソーシング先を探す際には、この略語を使用すると探しやすいので参考にしてください。
アウトソーシングの契約形態

続いて、アウトソーシングの契約形態は大きく2種類があります。
- 準委任契約
- 請負契約
「準委任契約」は業務の遂行そのものを目的とする契約で、作業の成果物が明確に決められていない業務に適用されます。メールの確認、スケジュール調整、資料作成など、日々の事務作業を依頼する場合です。
一方「請負契約」は、成果や結果が求められる業務に適用されます。システム開発やホームページ制作、製品の製造など、完成した成果物を納品してもらうことが目的の契約です。
契約の違いについては以下の記事でも触れています。ぜひご覧ください。
【関連記事】
業務をアウトソーシングするメリット

アウトソーシングには次のようなメリットがあります。
- コスト削減が期待できる
- 人材不足を補える
- 自社のコア業務に集中できる
- 業務効率と品質がアップする
- 外部の専門的なノウハウを取り入れられる
コスト削減が期待できる
まず、コストの削減を目指せることです。企業にとって人件費は大きなコスト要因であり、採用や教育にも時間と費用がかかりますが、採用した人材が長く定着するとは限らず、投資が無駄になる可能性も否めません。
その点、アウトソーシングは繁忙期や閑散期に応じて業務量を調整できるため、固定人件費を抑えることが可能です。
人材不足を補える
人材不足対策になることも大きなメリットです。人手不足が進んでいる昨今、経験とスキルが求められる経理や労務の人材を自社ですぐに雇用するのは難しいものです。
また、退職者が出たら人員を補充し、教育する必要もあります。人手不足の中で採用・教育を行うことは企業にとって負担になるでしょう。
その点アウトソーシングでは、業務を行う人材をアウトソーシング先が補充します。人員交代があっても、アウトソーシング先で業務の引継ぎをしてくれるため、負担になりません。
自社のコア業務に集中できる
人材補充がうまくいけば、社内の重要な業務に社員を割り振ることも可能です。例えば立ち上げ間もない会社の場合、1人が複数の役割を持っていることは珍しくありません。
経営者が経理、人事労務などバックオフィス業務を行っていたり、営業担当者が事務作業や商品在庫の管理を行っていたりする場合もあるでしょう。
アウトソーシングを利用すれば、このようなノンコア業務は外部に委託し、コア業務に専念することが可能です。
業務効率と品質がアップする
業務効率と生産性の向上も期待できます。「餅は餅屋」ということわざがあるように、プロに任せた方が業務効率と品質がアップすることは多くあります。
資料の作成を1つとっても、見やすくわかりやすい文書の作成には、訓練が必要です。しかし、訓練に充てる時間がない場合も少なくありません。
アウトソーシングで資料作成のプロにわかりやすい文書を迅速に作成してもらうことで、その業務そのものの効率性と品質アップが期待できます。
外部の専門的なノウハウを取り入れられる
またアウトソーシングを活用すれば、外部の専門的なノウハウを取り入れることも可能です。
例えば社内研修を自前で行う場合、指導役の育成や内容の更新に多くの手間とコストがかかり、コア業務への支障も生じやすくなります。
研修をアウトソースすれば、プロによる指導を通じて、質の高い教育を効率的に実施でき、社内リソースの最適化にもつながります。
アウトソーシングで業務効率化できる7つの業務

アウトソーシングで業務効率化を目指しやすい業務は、自社内では費用負担の大きいものやノンコア業務、ルーティンワークなどです。ここではアウトソーシングにおすすめの業務をご紹介します。
1.総務・人事労務
まず総務・人事労務です。一口に総務と言っても、備品購入、入退社手続き、給与計算などその業務内容は多岐にわたります。
総務スタッフの業務量が多く、残業が常態化している場合はアウトソーシングを利用するとよいでしょう。
マニュアル化しやすい手続き関連や、給与計算などある程度経験が必要な業務についてはアウトソーシングを利用すると業務効率がアップする可能性があります。
【関連記事】
総務アウトソーシングの料金やメリット・デメリット、おすすめを紹介
人事労務アウトソーシングのおすすめ5選!費用相場や外注先の選び方なども解説
給与計算アウトソーシングサービス10選!選び方のポイント5つも解説
2.採用
続いて採用です。募集文面を考えたり、面談をしたりとさまざまな業務が含まれます。
求める人材を採用するには、最新の求人動向に合わせた採用活動も必要です。ノウハウがない場合、思うように進められない可能性があります。
時間がかかる採用活動を効率的に行うためにアウトソーシングを利用するとよ良いでしょう。
【関連記事】
RPO(採用アウトソーシング)とは?意味や業務内容、企業のメリットなどを紹介
3.経理・会計
経理・会計もアウトソーシングに適しています。バックオフィス業務の中でも特に専門性が高く、知識や経験が求められるため、人材の確保や育成が難しい分野です。特に月末や期末などの繁忙期には、残業が増えることも少なくありません。
経理をアウトソーシングすることで、社内スタッフの負担を軽減できます。例えば、給与計算や労務管理といった毎月のルーティン業務は、継続的に任せやすく、安定した運用が可能です。
【関連記事】
経理アウトソーシングの失敗しない使い方!メリット・デメリット、料金相場やおすすめ会社なども紹介
4.コール業務
コール業務もアウトソーシングに適した業務の1つです。例えば、営業活動で行うテレアポは今でも有効な手法ですが、100件架電してもアポイントが取れるのはわずか1〜2件程度。効率面を考えると、こうした業務は外部に委託し、社内の人材はより重要な業務に集中させた方が効果的です。
テレアポのほかにも、電話取次・顧客対応などの一定の型がある業務は、アウトソーシングしやすいです。コールセンターやカスタマーサポートの運営も外部に任せることで、自社の負担を大きく減らせます。
【関連記事】
コールセンター代行サービスとは?料金やおすすめ業者10選を紹介
5.情シス
情シスは、社内のシステム関連の管理を行う情報システム部門のことで、専門性が求められます。パソコン、インターネットを使用しない企業は現在ではほぼないことから、セキュリティ対策などを行う情シスは必要な存在です。
専門性が求められるため、企業によっては、人材確保や育成が難しい場合もあります。そのため情シスもアウトソーシングするのに適した業務といえるでしょう。
【関連記事】
情シス・社内SEを外注!メリット・デメリット、おすすめアウトソーシング先などを紹介
6.デザイン
デザインはスキルや経験が必要となる業務です。優秀なデザイナーは採用市場でも引く手あまたです。募集をかけても、求めるレベルのデザインが可能な人材から応募が来ないということも十分にあり得ます。
デザイナーの採用経験があまりなく、どんなデザイナーを採用したらよいのか採用の判断が難しいという場合もあるでしょう。
アウトソーシングの場合採用コストをかけることなく、ハイレベルなデザイナーに依頼できます。
【関連記事】
デザインをアウトソーシングする方法とは?メリット・デメリットも紹介!
7.運営管理
店舗や事務所、工場などの運営管理もアウトソーシング可能です。例えば、接客、清掃、一般事務や店舗の運営者そのものを外部にアウトソースするケースもあります。
ほか、工場での商品製造や在庫管理、梱包、発送といった業務も外部委託しやすい分野です。これらの業務は手順やルールが明確で標準化されているため、品質を保ちながら効率的にアウトソースできます。
ここまでアウトソーシングで業務効率化しやすい業務を7つみてきました。しかしながら、安易に業務をアウトソーシングすることは問題を引き起こすことにもつながります。次に、続いて、アウトソーシングのデメリットを解説します。
業務をアウトソーシングするデメリット
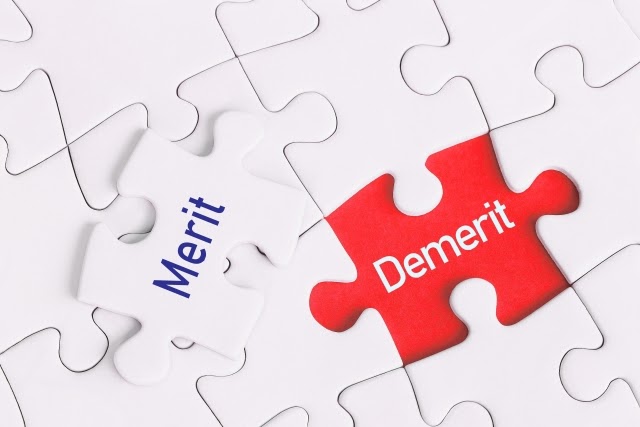
業務をアウトソーシングするデメリットもいくつかあるのでご紹介します。
- 社内情報を外部に出さなければならない
- 委託した業務の実態を掴みにくくなる
- 自社独自の事情に柔軟に対応してもられない場合がある
社内情報を外部に出さなければならない
アウトソーシングでは、人事業務や工場運営などの性質上、社員の個人情報や顧客データ、製品の設計図などの社内機密を外部に共有する必要があります。
例えば人事業務を委託する場合、給与情報や勤怠データを、コールセンター業務では顧客の氏名・連絡先・対応履歴などです。
多くの事業者は厳重に管理しており、情報が漏洩するケースは稀ですが、意図しないリスクが生じる可能性もあります。
そのため、アウトソーシング先を選ぶ際には、情報管理体制やプライバシーポリシー、過去の運用実績などをしっかり確認し、信頼できる業者を選定することが重要です。必要に応じて、守秘義務契約(NDA)の締結も検討しましょう。
委託した業務の実態を掴みにくくなる
アウトソーシングを利用すると、自社が業務の現場に直接関わらなくなり、実際にどのような手順で業務が進められているのか把握しにくくなることもあります。
例えば、経理業務を外部に委託した場合、仕訳処理の仕方や、請求書・支払い処理の手順が社内から見えにくくなります。その結果、業務ミスが積み重なっていても、すぐに気づけないリスクがあります。
こうした事態を防ぐためには業務報告を定期的に受け、担当者とこまめに連絡を取り合うことが重要です。また、作業マニュアル・チェックリストを完備し、定期的な報告会などで業務の透明性を高めましょう。
自社独自の事情に柔軟に対応してもられない場合がある
アウトソーシング先では、決められた業務フローや手順に従って作業を行うことが一般的です。そのため、自社の独自ルールや細かい運用方法があっても柔軟に対応してもらえないケースもあります。
例えば、請求書の処理において「社内では2名の承認が必要」「支払日は月末ではなく15日」といった独自ルールがある場合でも、委託先の標準手順ではそれに対応できないことがあります。
このようなミスマッチを防ぐには、契約前に自社の業務フローやこだわりポイントを明確に伝え、委託先がどこまで対応できるかを事前にしっかり確認しておくことが大切です。
バックオフィスのアウトソーシングなら「フジ子さん」
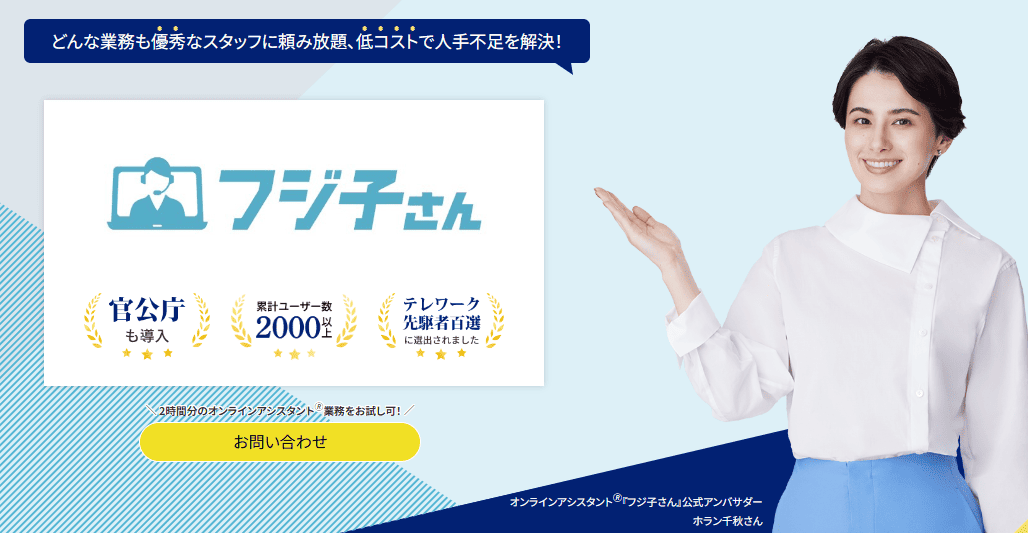
アウトソーシングサービスには、経理専門、採用専門、コール専門など特定の専門分野に特化したサービスもあります。専門サービスを利用する方法もありますが、幅広く業務を委託したい場合は、1つの契約でさまざまな業務を依頼できるオンラインアシスタントがおすすめです。
例えばフジ子さんの場合、スケジュール調整などの秘書業務だけでなく、経理、採用、コール、WEB制作など専門知識が必要な分野にも対応可能です。依頼する業務を絞る必要がないので、利用途中に新たな業務を依頼することもできます。
フジ子さんに幅広い業務を依頼した結果、以下のようにコア業務に集中できたケースは少なくありません。
フジ子さんについて詳しく知りたい方は、こちらからご覧ください。
まとめ
今回はアウトソーシングについて、アウトソースとの違いを始めとした基礎知識を解説しました。あわせてアウトソーシングにおすすめの業務と、メリット・デメリットについても触れています。業務課題の解決策としてアウトソーシングを検討している方はぜひ参考にしてください。
アウトソーシングの手段として、オンラインスタントを検討するのもおすすめです。フジ子さんの場合、1つの契約で幅広い業務を依頼できます。活用方法の詳細は以下よりご確認ください。