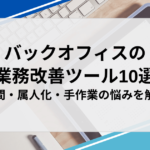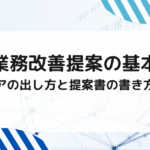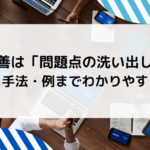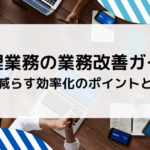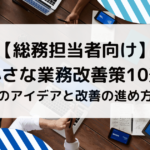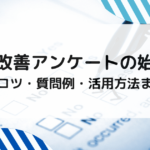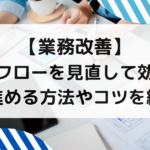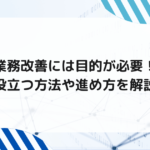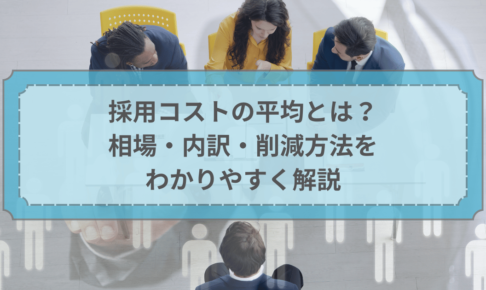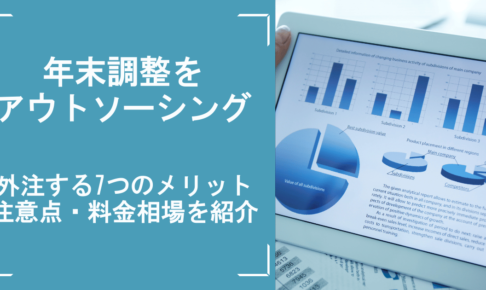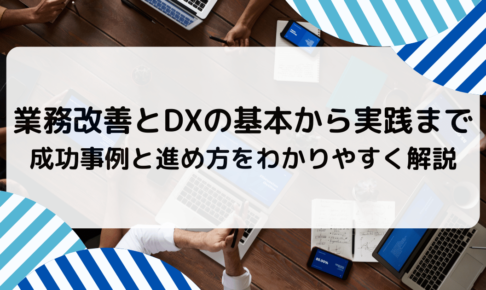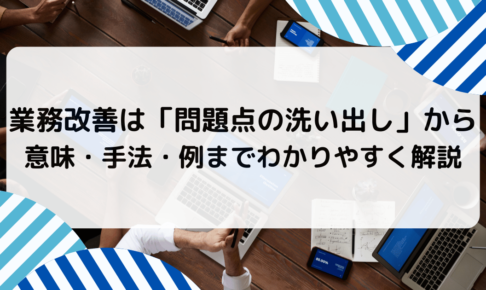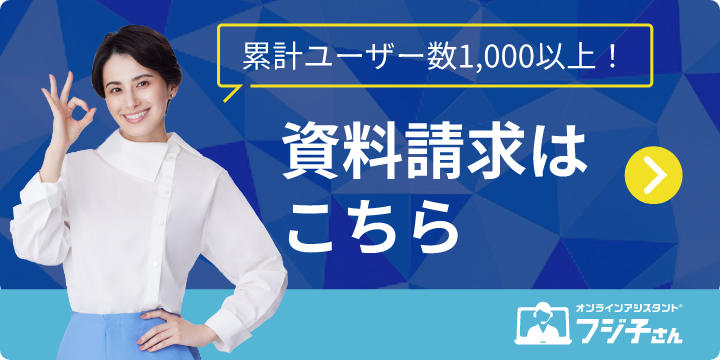業務改善報告書を上司から求められたものの、何を書けばいいのか悩んでいませんか?
「できるだけ時間をかけずに、要点をしっかり伝えたい」と考えている方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、報告書の基本構成や書き方のポイントに加え、すぐに使えるテンプレートや例文もご紹介しています。
「とにかく早く、でもきちんと仕上げたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
業務改善報告書とは?基本と役割を理解しよう
業務改善報告書は、現場で発見した課題に対して「どのような改善を行い」「どんな成果が出たのか」を整理して、上司や関係者に共有するための書類です。
改善内容には、コストをかけて行う「有償」の改善と、アイデアや工夫で実現する「無償」の改善があります。
特に無償で効果を出せた取り組みは、企業にとっても非常に価値が高く、改善の成果に応じた報奨金や賞与が支給されるケースもあります。
こうした背景からも、業務改善報告書は組織運営において、重要な位置づけを持つ資料といえるでしょう。
業務改善報告書の目的
業務改善報告書の主な目的は、現場で実施した改善活動を「見える化」し、関係者と共有することです。
上司やマネージャー層はもちろん、普段は関わりの少ない部署のメンバーにも、改善の経緯や成果を伝える役割があります。
また、改善プロセスを記録に残すことで、同じ問題を再発させないための組織的なノウハウとして活用できます。
さらに、改善活動を全社的に評価・展開しやすくなるため、業務効率や生産性の向上、社員満足度の向上といった効果も期待できます。
業務改善報告書が求められるタイミング
業務改善報告書が求められるタイミングとして多いのは、改善活動がひととおり完了した後です。
例えば、業務フローの見直しやシステム導入、人員配置の変更などを実施した際に、「どのように改善し、どんな成果が出たか」を報告するシーンが該当します。
また、改善活動を継続的に行っている職場では、月次や四半期ごとなど、定期的な提出が求められるケースもあります。
業務改善“報告書”と業務改善“提案書”の違い
業務改善報告書と混同されやすいのが「業務改善提案書」です。
業務改善提案書は、これから実施したい改善案を上司に提案するための資料で、未来志向の内容になります。
場合によっては、トラブルや課題の事前報告を兼ねることもあります。
一方、「業務改善報告書」は、すでに行った改善の内容と成果をまとめたものです。
企業によっては提案書と報告書の使い分けが曖昧なこともありますが、本記事では「改善後の報告書」として扱います。
提案書が「これからの取り組み」、報告書が「完了した改善の記録」という違いを理解しておくことで、目的に応じた資料を作成しやすくなります。
業務改善報告書の基本構成と書き方の流れ

業務改善報告書は、単に情報を詰め込むだけでは伝わりません。
「誰に」「何を」「どう伝えるか」を意識し、必要な情報を整理して伝えることが重要です。
ここでは、書き始める前に押さえておきたい考え方や、報告書に必要な構成・記載項目について解説します。
書く前に意識したい3つのポイント
まず意識したいのは、「読み手が求めている情報は何か」という視点です。
報告書は自己満足のためではなく、上司や関係者にとっての判断材料となる実務文書です。
そのため、以下の3点が求められます。
- 抽象的な表現を避ける
- 事実ベースで簡潔に
- 数字や具体例を交えて書く
また、改善の経緯だけでなく、背景や成果の評価も記載しておくと、内容への納得度が高まります。
業務改善報告書に盛り込むべき基本項目
業務改善報告書に盛り込むべき主な項目は、以下の通りです。
これらの要素を押さえておくことで、説得力のある報告書が完成し、読み手にも改善活動がスムーズに伝わります。
| 項目 | 内容・記載のポイント |
|---|---|
| 基本情報 | 日付、報告者名、タイトル |
| 業務改善の背景・目的 | 業務改善の全体像やねらい |
| 業務改善前の状況・課題 | 現場の状態(作業手順、体制、業務負荷など)どんな課題があったのか、なぜ改善が必要だったのか |
| 業務改善の施策 | 実際に行った改善の内容(具体的な対策や手順) |
| 業務改善後の効果 | どんな変化や成果が得られたのか(定量的に示せるとベター) |
| 業務改善にかかったコスト | かかった期間、人的リソース、金銭的コストなど |
| 今後の課題・懸念点 | 実施後も残る課題や、今後のリスクとその対処方針 |
フォーマットの準備と使い分け方
社内でフォーマットが決まっている場合は、それに従うのが基本です。
一方、決まった書式がない場合は、上記の構成を意識して作成しましょう。
目的に応じて、次のように使い分けると相手にとっても読みやすい資料になります。
| 用途 | 想定する相手 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 社内用 | チーム内、直属の上司 | ・口語表現もOKなケースがある ・重要なのは「事実」と「伝わりやすさ」 |
| 社外用 | クライアント、委託元など | ・ビジネス文書として体裁を整える ・敬語や整った文法が求められる ・トラブルや遅延などの報告を兼ねる場合は、謝罪と再発防止策を明確に記載することが重要 |
業務改善報告書がスラスラ書ける裏技
業務改善報告書は、「しっかり書こう」と思えば思うほど手が止まりがちです。
特に「最初の一文」をどう書き出すかで手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。
ここでは、業務改善報告書の作成を楽にするための4つの裏技をご紹介します。
「書き方の正解がわからない」「うまく文章がまとまらない」と感じたときに、ぜひお試しください。
テンプレートを活用して“構成の迷い”をなくす
ゼロから書き始めると、何をどこに書けばいいのか迷ってしまいがちです。
そんなときは、あらかじめ構成が決まっているテンプレートを使えば、流れに沿って必要な情報を埋めるだけで大枠は完成します。
自分で考える量が減る分、文章のハードルがぐっと下がり、前向きに報告書の作成に取り組めるでしょう。
例文からヒントを得る
「1行目が書けない…」というときは、例文を参考にするのが最短ルートです。
構成や言い回しのパターンをいくつか見ておけば、自分の報告にも応用しやすくなります。
例えば「どの程度の具体性が必要か」で迷ったら、例文にある数値や金額を参考に、自分の報告書への応用ができます。
いきなり文章にしない
最初から完璧な文章にしようとせず、まずは分かっている事実を箇条書きで書き出してみましょう。
「報告書=きれいな文章を書くこと」ではなく、伝える内容を組み立てることが大切です。
- いつ/どこで/誰が/何をした
- なぜそれが必要だった
- 最終的にどのような結果になった
このようにメモ感覚で整理しておけば、最後に文章にするだけで形になります。
過去の報告書を参考にする
過去の業務改善報告書が閲覧できる場合、それを真似ることもおすすめです。
特に上司や先輩が通した報告書は、会社に合った表現や構成の参考になります。
もちろんそのままトレースしてはいけませんが、文章のトーンや分かりやすい表現を真似ることで、「どう書けばいいか分からない」という悩みも解消されるはずです。
業務改善報告書のテンプレートと記載例
先ほどもお伝えしたとおり、何から書き始めればいいか分からないとき、頼りになるのがテンプレートと具体的な記載例です。
ここからは、基本的なテンプレートと記載例をご紹介します。
業務改善報告書を書くためのガイドとしてご活用ください。
テンプレート例
以下は、業種を問わず幅広く使える汎用的なテンプレートです。
必要に応じて、自社のルールや目的に合わせてカスタマイズしてください。
- 報告書タイトル
- 作成日
- 作成者
- 改善の背景・目的
- 実施した改善施策
- 改善前の状況と課題
- 得られた効果(定量・定性)
- 実施にかかった期間・コスト
- 今後の課題・追加検討事項
記載例
以下は、実際の業務に即した具体的な記載例です。
書類の種類や部門、ツール名まで明記することで、読み手に状況が伝わりやすくなります。
記載例
- タイトル:法人契約申込書の電子管理による業務効率改善報告書
- 作成日:20XX年XX月XX日
- 作成者:営業企画課 山田健太
- 背景・目的
法人向けインターネット回線の申込書を紙で管理していたが、件数の増加に伴い、検索・再確認作業に多くの時間がかかっていた。また、紛失リスクや二重処理の発生も課題となっており、業務効率・正確性の両面で支障をきたしていた。これらを解消し、申込書の処理スピードと保管の信頼性を向上させることを目的に、電子管理への移行を実施した。 - 改善前の状況と課題
・年間1,200件の申込書を紙で管理(営業部門で保管)
・書類の検索や内容再確認に平均12分を要していた
・管理不備による紛失リスクや重複処理が月2~3件発生 - 実施した改善施策
・既存の紙書類をすべてPDF化
・Google ドライブ上で「契約ID+法人名」によるフォルダ分類を実施
・スキャン業務・運用ルールについて、営業担当者向けの操作研修を実施 - 得られた変化や成果
・書類検索時間が12分 → 3分に短縮(75%改善)
・紛失・重複処理の報告がゼロ件になった
・営業部門から管理部門への問合せが月20件以上減少
・複数部署による同時閲覧・共有が可能になり、業務の連携が円滑になった - 実施にかかった期間・コスト
・期間:2025年3月中旬~4月末
・コスト:1万円(社内研修資料作成・講師費用)
※既存スキャナとGoogle Workspaceを活用したため、ソフト・機材の追加費用は発生せず - 今後の課題・追加の検討事項
一部業務では原本保管が必要な契約もあるため、法務部と連携しつつ、完全ペーパーレス化に向けた業務フロー整備と社内ガイドラインの明文化を検討中。
業務改善報告書をわかりやすく書くためのコツ

先ほどの記入例は、具体的で内容も理解しやすかったのではないでしょうか。
このように、伝わる報告書に仕上げるための実践的なコツと、陥りがちなNGパターンをご紹介します。
作成した業務改善報告書を見直す際に、一緒にチェックしていきましょう。
目的と結果を明確にする
「なぜやったのか(目的)」と「どうなったのか(成果)」を必ずセットで伝えましょう。
特に成果は、読み手の判断に直結する最重要ポイントです。
- NG例:「作業効率が良くなったと思う」
- 改善例:「入力作業にかかる時間が長く、他業務を圧迫していたため、マクロを導入。結果として処理時間が平均15分から7分に短縮された」
具体的かつ客観的に伝える
報告書は、感覚や印象ではなく、事実ベースで定量的に書くことが基本です。
数字や比較があるだけで、報告書の説得力が大きく変わります。
- NG例:「スムーズに対応できるようになった」
- 改善例:「1件あたりの対応時間が12分から3分に短縮された」
誰でも理解できる表現にする
業務改善報告書は、上司や他部門などさまざまな立場の人が読む可能性があります。
専門用語や略語、社内用語には注釈を入れるか、わかりやすい言葉に置き換えましょう。
- NG例:「CMSで申請業務を自動化」
- 改善例:「コンテンツ管理システム(CMS)を活用し、Web申請の自動処理を実現」
文章構成は「背景→課題→施策→結果」で書く
伝わる報告書の基本構成は、「なぜ」「何が」「どうなった」の順です。
書く順序を整えるだけで、読みやすさがぐっと上がります。
- NG例:「新ツールを導入しました。改善になったと思います。」
- 改善例:「作業時間が膨大だったため、〇〇ツールを導入。結果として対応時間が60%削減されました」
業務改善報告書は、書き方のポイントさえ押さえておけば、誰でも説得力のある内容に仕上げられます。
今回ご紹介した基本とコツを活用して、自分の業務にあった伝え方を見つけ出しましょう。
自社だけで抱えきれないと感じたら
業務改善は進めれば進めるほど、「ここも変えたい」「でも人手が足りない」といった課題に直面しやすくなります。
最初は社内だけで対応できていたとしても、継続的に改善を回すには時間も体力もリソースも必要です。
特に、次のような状況では外部の力を借りることが有効な場合もあります。
- 定型的な業務がボトルネックになっている
- 改善の意欲はあるが、人手が追いつかない
- コア業務に集中したいが、周辺業務に時間を取られている
こうした場面で、アウトソーシングという選択肢を検討するのは、戦略的な判断と言えます。
例えば、オンラインアシスタント®「フジ子さん」は、バックオフィス業務を得意とする人材を、必要に応じて柔軟に活用できるサービスです。
経理やカスタマーサポート、マーケティング支援など、幅広い業務に対応しており、多くの企業で導入されています。
「具体的にどんな業務を依頼できるの?」「費用は?」といった疑問がある場合は、以下のリンクから資料請求ができますので、ぜひお役立てください。
業務改善報告書に迷ったらテンプレに立ち戻ろう
ここまで読んで、「なんとなくイメージはつかめたけど、やっぱり手が止まりそう」
そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。
そんなときは、テンプレートや例文に立ち戻って、まずは“枠”を埋めることから始めてみましょう。
頭の中で考えているだけでは進まなかった作業も、書き出してみることで不思議と流れに乗って作業が進むことも珍しくありません。
業務改善報告書の作成は、考えることが多く、どうしても時間がかかる作業です。
だからこそ、テンプレートや例文を上手に活用して、ムダなく・迷わず・伝わる報告書を作成していきましょう。