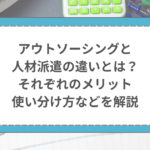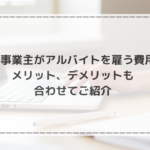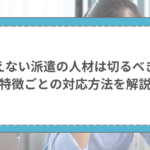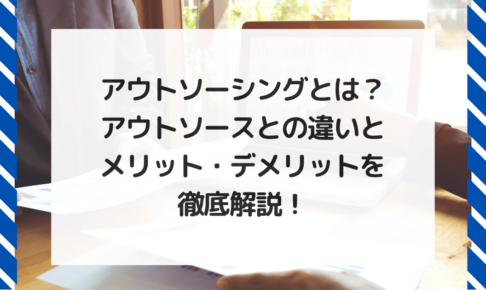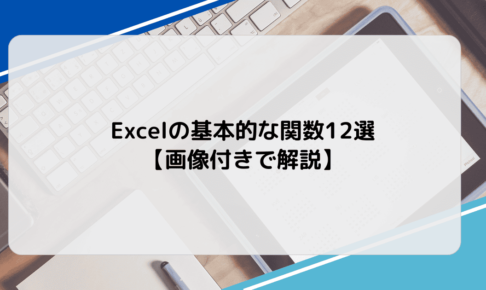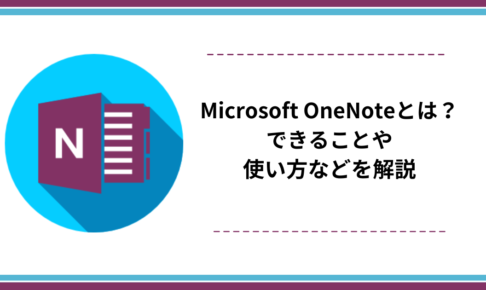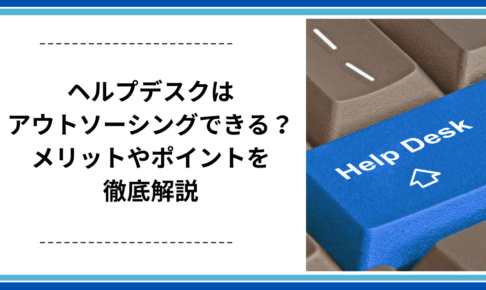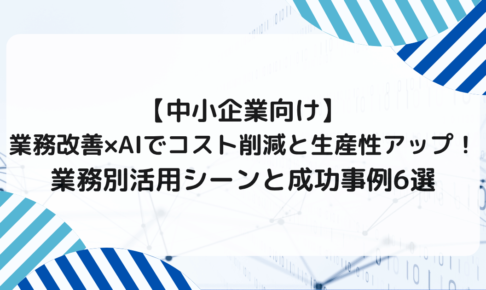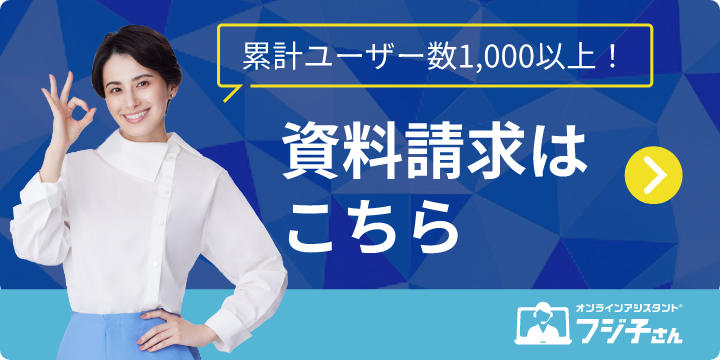「効果的な人件費削減の方法を知りたい」「従業員を解雇すれば人件費削減できるけれど、人手不足になりそう」このようにお悩みではありませんか。
人件費削減と聞いて、給与を減らすことや従業員を解雇することを思い浮かべた方は多いのではないでしょうか。しかし、従業員を解雇するのは高リスクでおすすめの方法ではありません。
そこで本記事では、人件費の基礎知識や人件費削減のメリット、適切な人件費の算出方法、効果的な人件費の削減方法を紹介します。
目次
そもそも人件費とは?
「人件費」とは、従業員に対して発生する費用を指します。人を雇用するには給与以外にも費用がかかるため、人件費は企業において経費のなかでも特に大きなコストになるのです。
私たちが普段イメージする狭義の意味としての「人件費」では、給与や賞与などを表すことが多いです。一方、広義の意味の「人件費」には、採用教育費・外注費なども含まれます。
「狭義の人件費」と「広義の人件費」について、詳しく解説します。
狭義の人件費
「狭義の人件費」とは、一般にイメージする人件費を指します。従業員へ支払う基本給や通勤手当などの給与と、それ以外の社会保険に関する健康保険や年金などの費用があり、具体的には以下の通りです。
- 給与:企業との労働契約において決められた基本給と時間外労働分の賃金。
- 賞与:企業の業績に応じて、夏季・冬季などに支給される賃金、ボーナス。
- 福利厚生費:冠婚葬祭、健康診断、社員旅行などにかかる費用。(福利厚生費として認められるためには、支給対象が全従業員であること、現物支給以外であることなどの条件を満たす必要がある。)
- 法定福利費:厚生年金保険などの社会保険料と、労災保険や雇用保険といった労働保険料に対して、企業が負担する費用。(どの程度企業が支払うべきかは法律で定められている。)
広義の人件費
「広義の人件費」とは、先述した狭義の人件費以外にも、幅広く考えた際に人件費として捉えられる費用のことを指します。つまり「従業員に対して発生する費用」であれば、幅広く人件費として捉えられるのです。
具体的には、以下のようなものが広義の人件費として挙げられます。
- 労務費:製造部の従業員に支払う給与のこと。また、給与には、直接的に製造に関わった従業員に支払う「直接労務費」と、間接的に商品製造に関わった従業員に支払う「間接労務費」の2種類がある。
- 外注費:外部の人間に業務を委託した際に発生する費用のこと。例えば、サイトデザインを外部のデザイナーに頼んだり、商品説明のライティングを外部ライターに依頼したりした場合が該当する。
- 採用教育費:従業員の採用フローや研修教育にかかる費用のこと。従業員募集のための広告費や、研修の会場にかかる費用などが該当する。
人件費削減の4つのメリット
まずは、人件費削減によって得られる4つのメリットを紹介します。
1.大幅なコストカットが見込める
人件費は経費のなかでも特に大きな割合を占めるため、単純に従業員数が減少すれば給与や賞与も減ります。さらに、その他人件費に関わる費用についても削減となり大幅なコストカットが見込めるでしょう。
業務を効率化して残業を減少できれば、給与や残業代だけでなく、水道光熱費や通信費、交通費、研修費、日用品などの費用も節約できます。コピー用紙や電気代を節約するよりも大きなコストカットが見込めるのです。
2.人件費を削減できた費用を事業の拡大、立ち上げにまわせる
人件費を削減できた費用を他の目的に投資できれば、業務効率の向上や事業の拡大、新規事業の立ち上げなども可能です。
一部を外注費に使用することで、残業が多い従業員の負担軽減につながり、労働環境も整うでしょう。
3.金融機関から評価が得られる
適切な人件費削減であれば金融機関からの評価が高くなり、融資を受けやすくなります。
人件費削減は利益が増えることにつながるので、数字上で赤字から黒字にすることも可能です。
利益が上がっているかどうかで金融機関の評価が良くなるため、決算書が改善されれば、融資の審査をパスしやすくなるでしょう。
4.株価上昇につながる
人件費削減により、株価の上昇が期待できます。売上高人件費率がアップすることで営業業績がアップし、投資家から高評価が得られやすくなるからです。
プラスの評価が得られると株式が購入されやすくなるので、株価が上昇するでしょう。
自社の人件費が適正かを見極めるための指標
人件費を削減する前に、自社の人件費は適切か検討しましょう。
自社の人件費が適切かどうか判断するための指標が「人件費率」と「労働分配率」です。ここでは、それぞれの指標の概要や計算方法、目安について解説します。
人件費率
人件費率は、売上に対し、人件費がどの程度占めているのかを表します。次の式で計算可能です。
人件費率(%)=人件費÷売上×100
例えば、売上300万円で人件費60万円の場合、人件費率は20%となります。人件費率の割合が大きすぎると、経営が圧迫されるので注意しましょう。
しかし、人件費を極端に削ってしまうと従業員に負担がいき、労働のモチベーションが下がってしまうリスクがあります。そのため、適切な比率の人件費率に抑える必要があるのです。
一般的に人件費率20~30%前後が平均値です。飲食店の人件費率は売上高の30〜40%が目安ですが、サービス業では50%を超えることもあり、業種によって異なります。
各業種の人件費率の平均値は次の通りです。これらの値を参考に、自社の人件費の目標値を決めましょう。
| 小売業 | 10%~30% |
| ホテル業 | 30%前後 |
| サービス業 | 40%~60% |
| 飲食業 | 30%~40% |
| 卸売業 | 5%~20% |
参照:TKC(https://www.tkc.jp/tkcnf/bast/sample/)
労働分配率
「労働分配率」とは、「付加価値額」に占める「人件費」の割合のことです。
付加価値額とは、商品を販売し、売上から原価を引いた金額のことを指します。例えば、800円で仕入れた商品を1,000円で売った場合、200円が付加価値額です。また、労働分配率は次の式で計算できます。
労働分配率(%)=(人件費÷付加価値額)×100
この労働分配率が高いと、人件費の比重が大きいと判断できます。あまりに人件費の比重が高いと、経営が圧迫されかねません。
人件費を下げて労働分配率の割合を無理やり下げたとしても、従業員のモチベーションが低下してしまうリスクもあります。そのため、労働分配率は適正値で保つ必要があるのです。
各業種の労働分配率の適正値は次の通りです。参考にして、自社の労働分配率を考えましょう。
| 建設業 | 45~65% |
| 卸売業 | 45~55% |
| 小売業 | 35~65% |
| サービス業 | 55~67% |
| 飲食業 | 40~60% |
参照:TKC(https://www.tkc.jp/)
人件費削減における4つのリスク
経営を改善するための人件費削減は、さまざまなメリットがあります。しかし検討する際には、次の4つのリスクがあることも確認しておきましょう。
1.従業員のモチベーションや生産性の低下
給与・賞与のカットや解雇することで、一時的に人件費削減となるかもしれませんが、おすすめできません。なぜなら、同時に従業員のモチベーションが低下するため、かなり高リスクとなるからです。生産性や業務効率の低下が、売上・業績ダウンにつながり悪循環になることもあります。
効果が大きい分、その代償が大きいということを理解しておかなければなりません。どうしても経営が上手くいかなかった場合にのみ、従業員の給与・賞与のカットや解雇を検討しましょう。
2.会社の信頼性の低下・イメージダウン
人件費削減を行うのは最終手段であるべきなので、給与・賞与のカットや解雇をする場合は深刻な業績不振と判断されます。それにより、取引先や金融機関、投資家などからの評価が低下し、会社のイメージダウンにつながる可能性があるでしょう。
さらに、一度企業としての信用を失うと、業績アップしたとしても新規人材獲得・新規事業参入などが難しくなることも予想できます。
3.人手不足が生じる
給与・賞与カットや解雇による人件費削減は、従業員の離職のリスクが高くなります。早期退職を募った場合には、必要な人材が辞めてしまって人手不足となることも考えられます。
その結果、残った従業員の負担が大きくなり業務効率も低下するため、職場環境が悪くなります。さらに他の従業員が離職してしまう可能性も出てくるでしょう。適度に人件費削減ができる予定が、急激に人手不足に陥ることもあり得るのです。
4.違法になる可能性がある
退職の検討をお願いするのみであれば問題ありません。しかし、個別に退職してほしい人を呼び出して、しつこく退職を説得すると、パワハラ防止法に触れる場合があるので注意が必要です。
リスクを回避しながら人件費削減で成功するポイント
給与・賞与カットや解雇などで人件費を削減するだけでは、生産性が下がり利益も減るリスクがあります。生産性を上げて利益を伸ばし、人件費率の削減を目指すことが望ましいといえるでしょう。
ここからは、リスクを回避しながら人件費削減で成功するポイントを6つ紹介します。
1.業務のムダをなくす
本来必要でない残業をしていないかなど、業務フローを見直すことで、人件費を削れます。例えば、書類をメールでメンバーに送っていた場合、クラウド化すれば、一度に多くのメンバーが書類を閲覧できます。
また、残業が常態化している場合は、タスクごとの時間管理をしっかり行う、19時以降はオフィスに入れないなどの施策をすると良いでしょう。
従業員のスキルアップの促進や、スタッフ育成による生産性アップなども人手不足にならず、業務効率化につながるのでおすすめです。
2.人員配置を見直す
人員配置を見直すのも、人件費削減の方法です。例えば、事務作業を行う従業員を、利益に直結するコア業務の部署に移動させることで、人件費率に対する利益率を増やせます。
もちろん、事務も会社運営になくてはならない業務なので、外部パートナーに委託するなどして調整しましょう。
3. IT機器やソフトウェアで効率化する
IT技術で業務を効率化することで、人件費を削減可能です。例えば、契約書をデジタル化して保管できるソフトを使えば、書類を効率良く管理できます。
また、勤怠管理ソフトや経費精算システムの導入をすれば、より多くの社員が利益に直結するコア業務に集中できるでしょう。
4.商品の価値に見合った値付けをする
商品の価値に見合った値付けをすることで、利益を増やし、人件費率を削減できます。
商品の質が改良されていないにもかかわらず、高すぎる単価を設定してしまうと、売上が大幅に下がるかもしれません。極端に単価を上げることなく、あくまで商品に見合った範囲内で価格を調整するようにしてください。
また、最適な価格設定だけでなく、戦略的に商品コンセプト、売る場所、商品の売り方なども考慮できるとよいでしょう。
5.外注を活用する
外注を活用するのも、人材の採用・教育にかかる費用をカットする方法の1つです。外注することでコストパフォーマンスが高くなる場合は、繁忙期のみ業務委託することや、一部業務のみの委託などを検討してみてください。
一部の業務を今より安価で外注すれば、人件費を削減可能で、利益を出すためのコア業務に多くの社員が集中できるのがメリットです。例えば、サイト設計であれば、自社社員より外部のパートナーの方が専門知識を持っており、費用も安く済む場合があります。
社員の負担を減らし、労働環境が整えられれば、長期的にみて業績アップや生産性の向上につながります。
6.従業員に負担をかけない人件費削減を目指す
従業員の給与や賞与を下げるのは、大きなリスクを伴う可能性があるため、できるだけ避けたい方法です。
経営がうまくいかなくなった場合の最終手段と考え、前述した人件費削減で成功するポイントなどを取り入れて、従業員に負担をかけない人件費削減を目指しましょう。
高コスパのフジ子さんに外注して人件費削減を
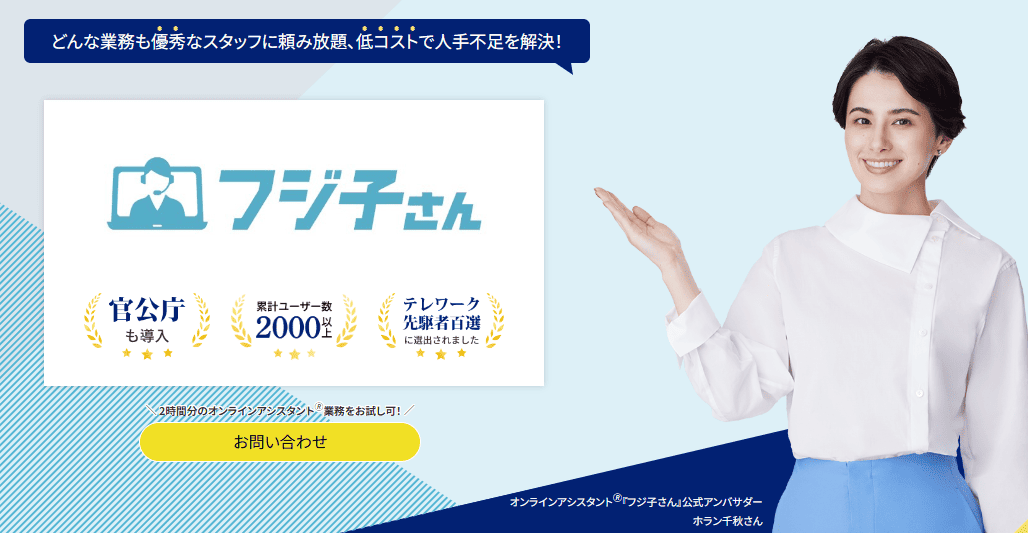
人件費削減の方法の1つである外注を活用する場合は、幅広い業務を依頼できて高コスパの「フジ子さん」の利用がおすすめ。フジ子さんは、オンライン上で業務をサポートしてくれるサービスです。
社内で行う必要がない業務をフジ子さんで代行できます。IT機器やソフトウェアで業務効率化はもちろん、幅広いバックオフィス業務に対応できるので従業員の残業を減少させ、負担軽減につながるでしょう。
フジ子さんの一番の特徴は、業界平均の半額ほどというリーズナブルさです。
例えば月30時間実働のプランだと、相場が12~15万円/月なのに対し、フジ子さんなら税込97,350円で利用可能です。※2025年4月1日より新価格。
また、幅広い実務経験・高い能力を持ったスタッフが業務を代行するため、高いクオリティが保証されます。
経理、Web、人事、翻訳、総務など幅広い業務を依頼でき、かつ高コスパです。人件費を削減したいのであれば、一度利用を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、人件費の基礎知識、人件費削減のメリット、適切な人件費の算出方法、効果的な人件費の削減方法を紹介しました。
従業員の給与を減らす、解雇するなどの高リスクの方法を取らなくとも、業務を効率化したり外注を利用したりすれば、従業員に負担の少ない人件費削減が実現できます。
適切な方法で人件費の削減を検討してみましょう。