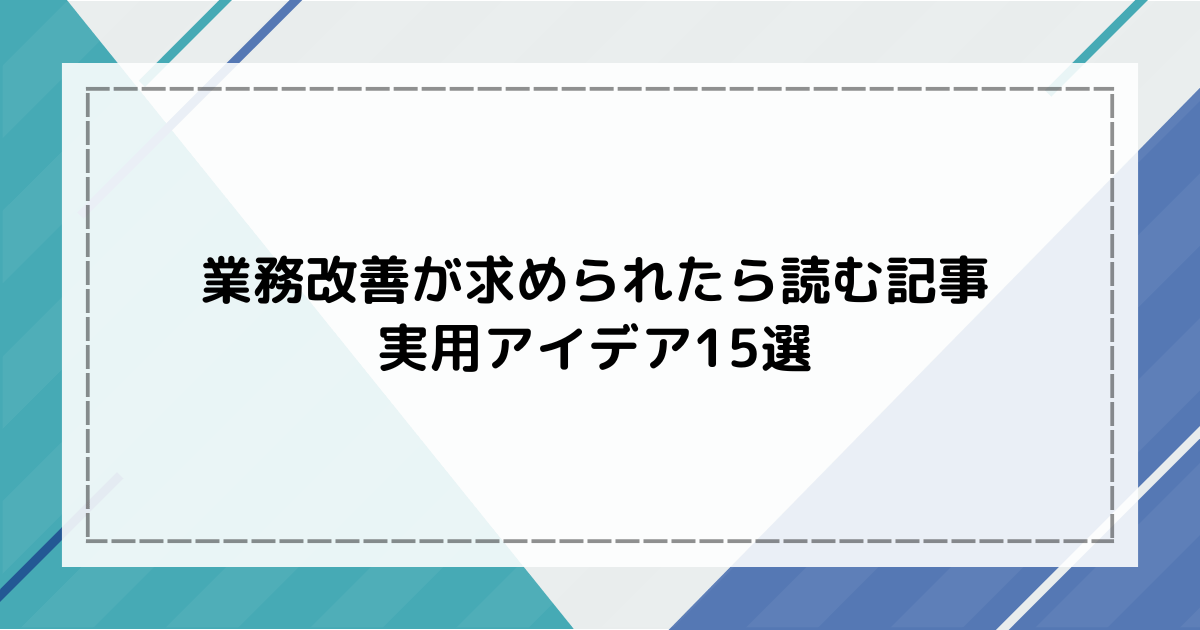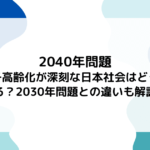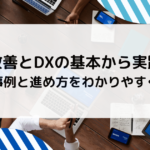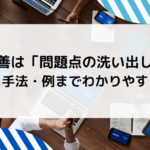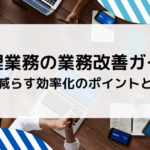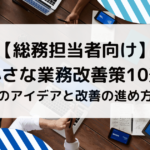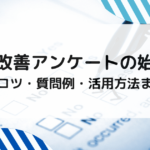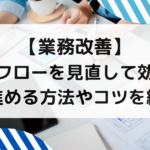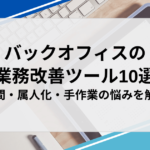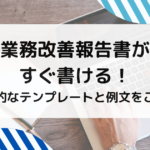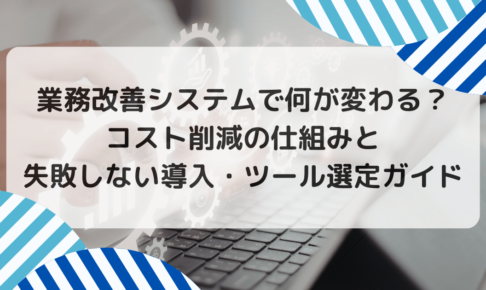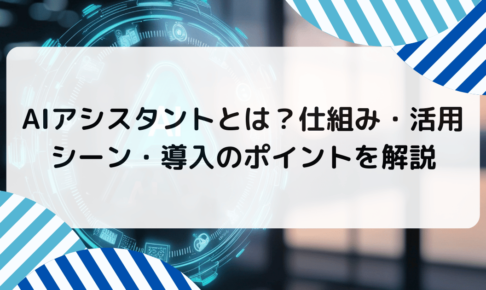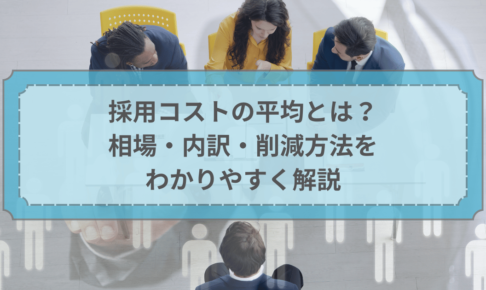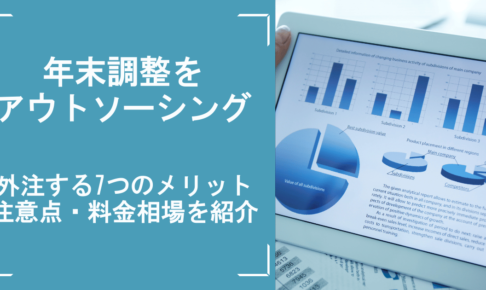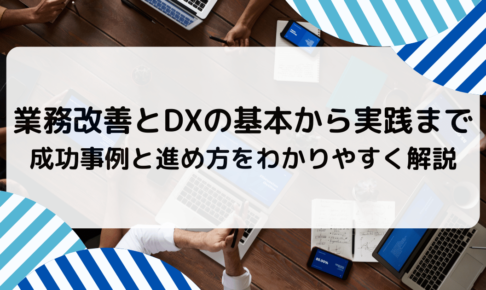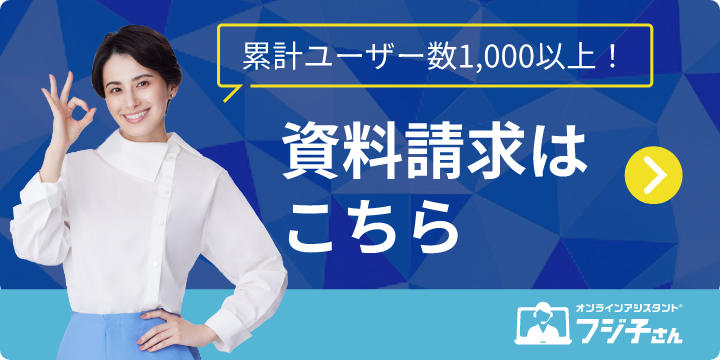「業務改善を考えてほしい」と言われても、何から始めればいいのか迷うことはありませんか?
本記事では、事務職などでもすぐに実践できる業務改善アイデア15選をご紹介します。
実例や提案のコツ、外部リソースの活用法まで、現場で役立つ情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
目次
業務改善とは?まず押さえておきたい基本

日々の業務に追われていると「今のやり方が本当に最適なのか」を見直す余裕がなくなりがちです。しかし、だからこそ業務改善が必要です。
ここでは業務改善について、基本的な考え方と現代のビジネス環境で重要視されている理由を解説します。
業務改善の定義と目的
業務改善とは、日々の業務の中で発生しているムダや非効率、ミスの原因を見つけ出し、業務フローやツール、担当の仕組みなどを見直すことで、仕事全体の効率や生産性を高める取り組みです。
目的は単に「時間を短縮する」「作業を簡素化する」ことにとどまりません。改善を通じて社員の業務負担を減らしたり業務の質を向上させたりと、さまざまな側面でポジティブな効果が期待できます。
組織全体の業務パフォーマンスを効率化し、競争力を高めることが最終ゴールです。
なぜ今、業務改善が求められているのか
業務改善の重要性はますます高まっています。その背景には以下のような要因があります。
人手不足への対応
少子高齢化や採用難により、少ない人数で業務を回さざるを得ない企業が増加しました。人に頼る体制ではなく、仕組みで効率化を図ることが求められています。
働き方改革と多様な就労形態の拡大
テレワークやフレックス制度の導入により、従来通りの業務の進め方では不便が生じやすくなりました。業務内容やフローの見直しが求められる場面が増えています。
デジタル化の進展とツールの多様化
業務効率化を支援するITツールやクラウドサービスが充実してきたことで、業務改善のハードルは以前よりも下がっています。こうした状況下において「業務改善」は避けて通れないテーマです。
業務改善アイデアを出す前に考えるべきポイント

「何か改善したいけれど、どこから着手すればいいのかわからない」「改善案が浮かばない」という声は少なくありません。実際、業務改善の第一歩でつまずく人はいるものです。
ここでは、改善アイデアを出す前に押さえておくべきポイントをご紹介します。やみくもに案を出すのではなく、対象や視点を明確にすることで効果的な改善につながりやすくなります。
業務改善の対象を明確にする
まずは「何を改善するのか」を具体的にすることです。例えば「業務を効率化したい」といった漠然とした目標では、現場レベルでの具体的なアクションに落とし込みにくく、取り組み案も曖昧になりがちです。
改善すべき主な例は以下のとおりです。
- 社内文書の作成に時間がかかる
- 会議が多く、準備や議事録作成が負担になっている
- 業務の引き継ぎに時間がかかり、ミスが発生している
- データの集計や入力が手作業で時間がかかっている
このような現場で日々「面倒」「二度手間」と感じている業務をリストアップし、対象を絞り込むことで、改善策も具体化しやすくなります。
アイデアが出ないときの考え方・ヒント
いざ改善案を出そうと思っても、「何をどう変えればよいのか思いつかない」ということはよくあります。アイデアが出ないときには、以下の視点で業務を見直すことが役立ちます。
- 繰り返し作業が多くないか?
- 情報が分散していないか?(例:メール、チャット、紙)
- 作業フローにムダな手順はないか?
- 「誰かしかできない仕事」が存在していないか?
また、他部署や他社の事例を調べてみるのも有効です。「このツールを使えば効率化できそう」「この進め方は自社でも応用できるかも」といったヒントが得られることがあります。
「完璧なアイデアを出そう」と意気込まず、小さな違和感や不便さに目を向けることが、改善の第一歩となるでしょう。
すぐに使える業務改善アイデア15選
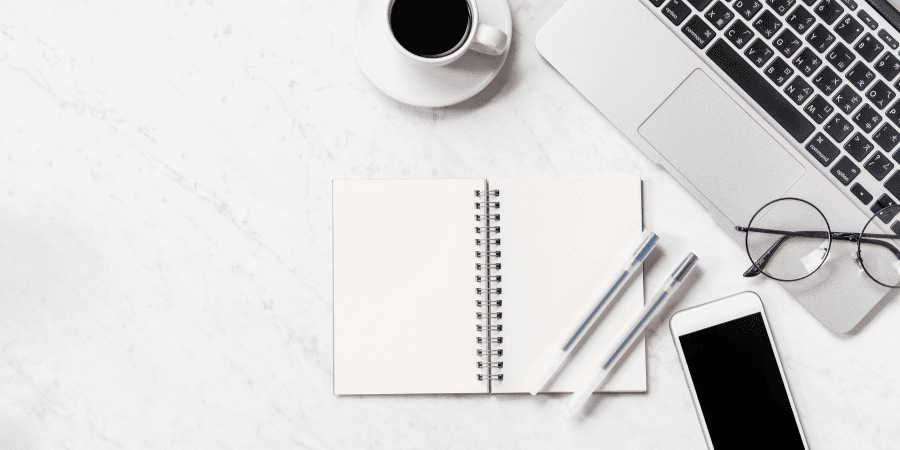
業務改善のアイデアは、特別なスキルや大きな予算がなくても実践できるものが多くあります。そこでここでは、明日からでも取り組めるような「すぐに使える改善案」を15個ご紹介します。
日々の業務を少しでも効率的にストレスなく進められるよう、現場でよくある課題に対する実践的なヒントをまとめました。ぜひ参考にしてください。
1. 不要な業務を洗い出して削減する
業務改善の出発点として最も効果的なのが、「本当に必要な業務だけを残す」ことです。業務フローが複雑化し、慣習的な仕事が増えてくると、非効率なタスクが含まれていることが少なくありません。
例えば、形式だけの定例会議やあまり読まれない報告書、チェックする人がいないダブルチェック工程などはないでしょうか。このような業務は、一度立ち止まって必要性を再検討してみてください。
削減を検討する際は現場の担当者にヒアリングし、「やめても問題が起きない仕事はないか?」という観点で洗い出すとよいでしょう。
すべてを変える必要はなく「週に1回の集計業務を月1にする」「チェック工程を簡素化する」などの小さな工夫でも十分改善につながります。
2. 業務フローを可視化し、ムダを発見する
次に不透明な業務フローを洗い出し、ムダを見つけることも重要です。
業務が非効率になる原因として「全体の流れが把握できていない」ことがあります。自分の担当業務しか見えず、前後の作業に無関心でいると、ムダな手順や重複作業が見えにくくなるものです。
そこで有効なのが業務フローの可視化です。例えば、業務プロセスマップやフローチャートを使い、関係者と一緒に「いつ・誰が・何をしているか」を図解にしてみてください。
可視化することで、情報の受け渡しが滞っている箇所やボトルネックになっている工程、二度手間になっている作業などが浮き彫りになります。
3. 担当者・分担の見直しで負荷を平準化する
続いて、業務の分担を定期的に見直すことも重要です。一部の業務が特定の担当者に集中していると、その人の不在時に業務が滞ったり、属人化が進んでミスやトラブルの原因になります。また、人によって業務量に偏りがあると、不満やモチベーションの低下にもつながりかねません。
そうならないためにも、業務状況を確認し、分担が偏らないようにすることが重要です。各自の業務量やスキル、繁忙期の負荷などを整理し「誰が何をどのくらい抱えているか」を把握するところから始めましょう。
Excelで工数表やガントチャートを作成するなど、方法はシンプルでかまいません。見直しの結果、負担の大きい業務を他の人とシェアしたり、担当ローテーションを導入したりすることで、負荷の平準化やノウハウの共有が進みます。
4. 外注・オンラインアシスタントの活用を検討する
業務量が多すぎて改善の手が回らない、またはそもそも人手が足りない場合は、思い切って外部の力を借りることも検討しましょう。特に資料作成・データ入力・経理補助・調査など、業務内容が定型化しやすい仕事であれば、外注やオンラインアシスタントの活用が有効です。
最近では、オンラインで依頼できる「アシスタントサービス」が増えており、必要なときだけプロに業務を頼める仕組みが整っています。単純作業だけでなく、SNS運用やリサーチ業務、マニュアル作成などのやや専門的な業務にも対応しているサービスもあります。
自社でリソースを増やすにはコストも時間もかかりますが、外部リソースを活用すれば、スピーディーかつ低コストで業務効率化を目指せるでしょう。
5. 業務マニュアルを整備して属人化を防ぐ
業務マニュアルの整備も欠かせません。「この業務はAさんしかできない」「休まれると困る」という状態は、業務が属人化している証拠。属人化は業務工程が不明瞭になるブラックボックス化を招きます。引き継ぎや教育が難しくなるだけでなく、トラブル時の対応も遅れやすくなります。
このようなことにならないよう、マニュアルを用意しましょう。業務内容や進め方が誰でも再現可能となり、業務の品質も安定します。マニュアル作成のポイントは「読む人の立場でわかりやすく書く」ことです。
また、マニュアルは一度作って終わりではなく、定期的に更新しながら運用することが大切です。業務が変化したときは必ず見直しを行い、現場で使いやすい状態を維持することで、継続的な業務改善にもつながるでしょう。
6. 業務改善ツールや自動化ツールを導入する
「時間がかかる」「ミスが多い」と感じるときには、ツールを活用することで大幅に改善できる可能性があります。非効率な工程があると時間がかかりますし、人はミスをするものです。
最近では、クラウドサービスやRPA(Robotic Process Automationの略:繰り返し作業を自動化する技術)など、検討すべき業務効率化のためのツールが多く登場しています。
例えばスケジュール調整には「Calendly」、タスク管理には「Trello」や「Backlog」、経費精算には「マネーフォワードクラウド」など、無料または低コストで導入できるツールも多く存在します。
手作業で行っていた業務を自動化すれば人的ミスを減らし、従業員がより重要な業務に従事できるようになるでしょう。導入の際は、現場の声を参考に操作性と実用性の高さを検討してみてください。
7. チェックリストやテンプレートでミスを防ぐ
ミス対策を強化したい場合は、チェックリストの活用が有効です。業務上のミスは手順の抜けや確認漏れから生まれることが多く、どれだけ経験のある人でもヒューマンエラーは避けられません。
請求書の発行や入金確認、商談後のフォロー連絡など、手順が決まっている業務にチェックリストを設ければ、作業の抜けを防ぎ、誰がやっても同じ品質が保たれます。
また、報告書や議事録、提案資料などの定型文書にはテンプレートを用意しておくことで、作成時間の短縮と品質の安定化が図れます。
テンプレートは共有フォルダやナレッジベース(業務知識やノウハウを蓄積・共有する仕組み)にまとめておくと、組織全体の生産性も底上げできるはずです。
8. 情報共有のルールと仕組みを整える
情報共有に課題を感じている場合は、ルールと仕組みも整えましょう。情報が関係者にうまく共有されていないと、業務に無駄な手戻りや遅れが発生します。
「メールは送ったけれど読まれていない」「データの場所がわからない」「別の部署が同じ作業をしていた」という問題は、情報共有インフラが整っていない典型例です。
このような状況を防ぐには、まず「誰が・いつ・どのように情報を共有するか」というルールを定めましょう。メールやチャットの使い分け、ファイル管理のルール、報告の頻度やフォーマットなどを明文化することも、情報の伝達ミスや認識のズレを防げます。
さらに、社内のどこからでも情報にアクセスできる体制を整えることも良案です。GoogleドライブやBox、Notionといったクラウドツールを活用すれば、チーム間の連携がスムーズになるでしょう。
9. ペーパーレス化で業務スピードを上げる
業務スピードが気になる場合は、ペーパーレス化も有効です。紙ベースの業務は、ファイリング・印刷・郵送・押印といった手間が多く、時間もコストもかかります。また紙の文書は検索性が低く、必要な情報を探すのに時間がかかることも少なくありません。
そこで紙の作業を減らすことが役立ちます。「書類をPDFやスプレッドシートで管理する」「契約書や申請書を電子化する」「FAXの代わりにクラウド送信ツールを使う」など、小さな一歩から始めることで、業務全体のスピードと正確性を高められます。
ペーパーレス化には、社内の合意形成や上長の理解も必要になるため、まずは「コスト削減」や「保管スペースの削減」といった効果を具体的に示すと進めやすいでしょう。業務改善の足がかりとして、比較的取り組みやすい施策です。
10. 会議やミーティングのルールを見直す
日常的に会議やミーティングが行われている企業では、ミーティングのルールを見直しも業務改善の対象です。目的やゴールが曖昧なまま会議を開いてしまうと、長時間にわたる割に結論が出ない、参加者が疲弊する、などの悪影響を及ぼします。
改善の第一歩は「この会議は本当に必要か?」という視点を持つことです。必要な会議は、アジェンダ(議題)と終了目標時間を事前に明示し、話すべきことを明確にしておきましょう。ファシリテーターや議事録担当を決めておくと、スムーズな進行にもつながります。
さらに、全員参加の会議を減らし、必要な人だけが短時間で集まるスタイルに変える、チャットやメモ共有で代替できるものは非対面で済ませるなど、会議の在り方自体を柔軟に見直すことも大切です。
11. タイムマネジメントを意識して時間の使い方を最適化する
どの業種にかかわらず、時間の使い方を見直し、最適化を図りましょう。「1日があっという間に終わってしまう」「気づけば残業している」という声は、多くの職場で聞かれます。
タイムマネジメントを改善するには、まず「自分がどの業務にどれだけ時間を使っているか」を把握することが重要です。1週間だけでもタスクの所要時間を記録してみると、「本来の業務」より「調整や雑務」に時間を取られていることに気づく人も多いでしょう。
そのうえで、業務を「集中すべき仕事(クリエイティブ・判断が必要なもの)」と「短時間で処理できる仕事(ルーチン・作業系)」に分けて、それぞれに適した時間帯を設定します。
例えば、午前中に集中が必要な仕事をまとめ、午後は確認作業やミーティングに充てるといった運用が効果的です。
また、ポモドーロ・テクニック(25分作業+5分休憩を繰り返す)など、集中力を維持するための時間管理術を導入するのも有効です。小さな工夫で、1日の使い方は大きく変わります。
12. スキルアップの機会を設け、従業員の力を引き出す
業務改善というと仕組みやツールの話になりがちですが、「人」の成長も欠かせない要素です。担当者のスキルが上がれば判断力や対応力が増し、業務効率も自然と向上します。
また、学びの機会があることで、従業員のモチベーションや満足度も高まるでしょう。例えば社内勉強会を定期開催したり、業務に関連する外部セミナーへの参加を支援したりすることで、スキルアップの土台づくりが可能です。
さらに、ナレッジ共有の文化を促進し、学んだことをチーム内で伝える仕組みをつくると、全体のスキルの底上げにもつながります。
13. テレワークや柔軟な働き方を制度として整える
続いて、柔軟な働き方を制度として取り入れることも大切です。コロナ禍をきっかけに広がったテレワークは一時的な措置ではなく、恒常的な働き方として定着しつつあります。
しかし「在宅勤務ができる制度はあるが、実際にはうまく活用できていない」という企業もあるでしょう。
柔軟な働き方の導入は、業務改善のチャンスでもあります。例を挙げると、在宅勤務により通勤時間が削減されることで、社員がより集中して業務に取り組めるようになります。
時間や場所に縛られない働き方は社員のワークライフバランスの向上にも貢献し、結果的に生産性が上がるという好循環が生まれます。
14. データや業務情報を一元管理できる仕組みをつくる
業務のスピードアップを図るうえでは、業務情報を一元管理できる仕組みを導入することも役立ちます。必要な情報を探す時間を減らせるからです。
社内のファイルがバラバラに保管されていたり、更新されていないマニュアルが残っていたりすると、必要な情報を見つけるのに多くの時間がかかり、生産性を下げてしまいます。
こうした問題を解決するには、情報管理の仕組みを整えることが効果的です。例えば、GoogleドライブやMicrosoft SharePointなどを使って、部署や業務ごとにフォルダを整理し、最新ファイルのみを共有するようルール化するだけでも、情報へのアクセス性は大きく向上します。
さらに、業務の進捗管理や問い合わせ対応なども、Excelベースではなく一元的なクラウドツールで管理することで、作業効率や情報の可視性がアップするでしょう。
15. 複数の改善策を組み合わせて効果を最大化する
ここまで14つの業務改善アイデアをみてきましたが、単発の施策だけでは限界があります。業務フローを見直しても、マニュアルが整っていなければ定着せず、ツールを導入しても使い方が理解されていなければ効果が出ません。
そこで、複数の施策を組み合わせて実施することが役立ちます。例えば【業務の可視化】+【チェックリストの導入】+【外注による負担軽減】のように、相乗効果を意識した改善プランを設計してみてください。より持続性のある仕組みづくりが可能でしょう。
そしてこれらを「試してみて、改善を繰り返す」という姿勢も大切です。一度で完璧な解決策を目指すのではなく、小さな改善を積み重ね、PDCA(計画・実行・評価・改善を繰り返すサイクル)を回すことで、組織に根付く業務改善が実現します。
実際の改善事例を紹介
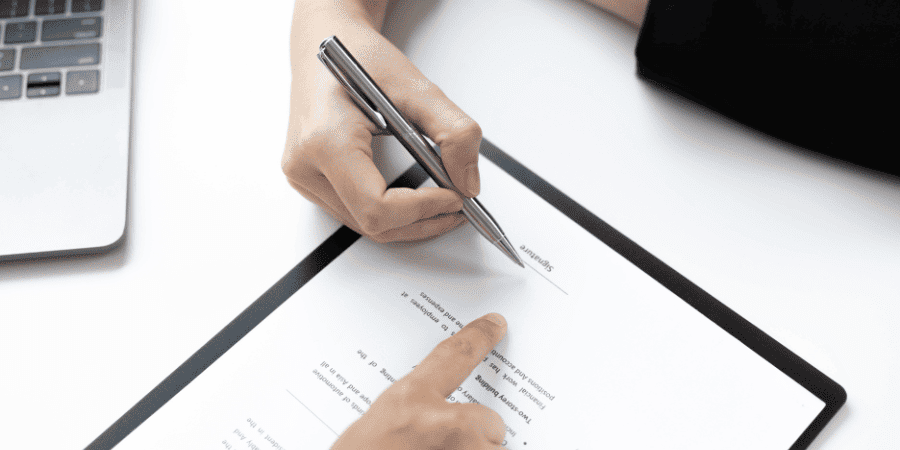
前章では15の業務改善アイデアをみてきましたが、ここでは小さな工夫から事務職が取り組める改善案、さらに外部サービスを活用した事例まで、改善事例をご紹介します。自社で導入できそうな事例をイメージしながら読み進めてみてください。
小さな工夫で効率アップした事例
株式会社高速道路総合技術研究所では、議事録作成の効率化を目的にAI議事録作成ツール「Rimo Voice」を導入。会議参加者が多く、発言の記録や特定が難しかった従来の方法では、議事録作成に多くの時間と労力を要していました。
導入後は、音声認識による自動文字起こしと話者分離機能により、誰がどの発言をしたかが明確になり、確認作業の大幅な軽減に成功。議事録作成時間は従来の3分の1、場合によっては20分の1まで削減されました。
このような「一部の業務に特化したツールの導入」は、大規模な業務改革をしなくても、限られた範囲で着実な効率化が図れる好例です。
事務職でもできる改善案の実例
株式会社花山うどんでは、店舗ごとにバラバラだった業務マニュアルのフォーマットや内容に課題がありました。Excelベースで管理されていたマニュアルは、作成者の違いによって記載内容に差があり、情報の参照や共有がスムーズに行えないという問題が発生していました。
この状況を改善するために、統一管理が可能な業務マニュアルの管理ツールを導入。マニュアルをオンライン上で一元管理できるようになったことで、スタッフが自ら必要な情報を確認できるようになり、本部への問い合わせ件数も減少。結果として、現場の対応力が向上し、全体の業務負担も軽減されました。
特別な技術や予算を必要としない改善ですが、「見える化」と「標準化」によって誰でも実践可能な改善手法として参考になります。
ツールや外部サービスを使った改善事例
外部のリソースやツールを上手に活用することで、自社の業務負担を大きく軽減した事例も増えています。
例えば、フジ子さんのようなオンラインアシスタントを活用し、資料作成・データ入力・スケジュール調整などの業務を外注することで、社員がコア業務に集中できるようになった企業もあります。具体的には、以下のとおりです。
- 見積作成業務をアシスタントに一任することで月20時間の工数削減
- 営業会議用の資料作成を外注し、社内のリソースを提案資料作成に集中
- 問い合わせ対応の一部を委託し、カスタマーサポートの品質向上と時間確保に成功
こうした事例からわかるのは、「自社だけで完結させる」発想から「外部と協力して効率を上げる」という視点転換の重要性です。特に中小企業やスタートアップにとっては、限られた人員でも成果を最大化する有効な手段といえるでしょう。
改善提案を通すためのポイント
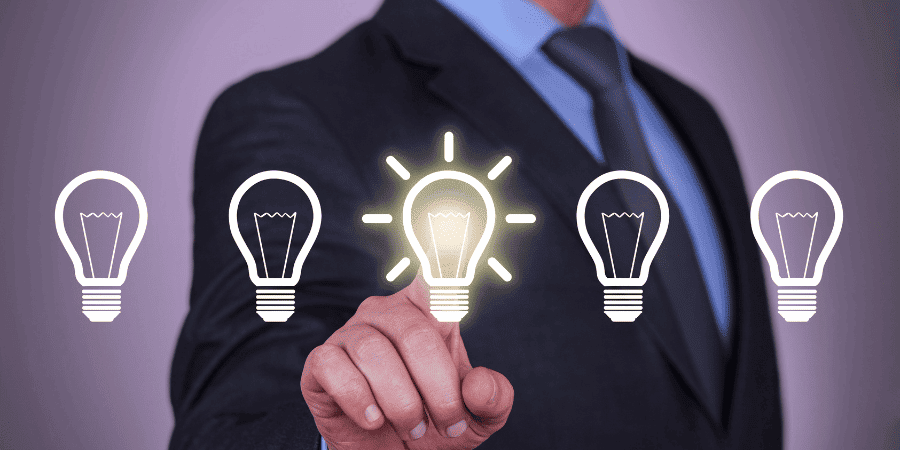
業務改善のアイデアが出てきたとしても、それを実現するには「社内で提案を通す」というステップが欠かせません。しかし、どれだけよいアイデアであっても、伝え方やタイミングを間違えると却下されてしまうこともあります。
ここでは、社内で通りやすい提案のポイントや、ありがちなNG例、改善提案制度の活用方法について解説します。
社内で通りやすい提案のコツ
改善提案を通す際に大切なのは、「その提案によって、誰が、どんなメリットを得られるか」を具体的に伝えることです。
「ただ非効率だから変えたい」と主張するのではなく、「これを改善すれば○○の作業時間が週3時間減ります」「このツールを使えば、ミスが年間○件削減できます」といったように、数値や具体的な効果を交えて説明することが説得力につながります。
また、提案内容が自分だけで完結せず、他部署に影響する場合は、関係者への事前相談も重要です。「関係部署とも相談済みです」と伝えるだけで、上司の安心感が増し、承認されやすくなるでしょう。
提案内容と文句の違いに注意
改善提案をする際によくある失敗の1つが、「文句」や「不満の吐き出し」に聞こえてしまうケースです。例えば、「○○のやり方は非効率」「○○部門の対応が遅い」といった表現は、意図しなくても否定的な印象を与えてしまいます。
重要なのは、「現状の課題」ではなく「課題をどう解決したいか」という建設的な視点を中心に据えることです。課題の指摘だけでなく、「こうすれば改善できるのでは?」という具体的な提案を添えることで、前向きな印象を与えられます。
また、表現を柔らかくすることも効果的です。「現状の○○には改善の余地がありそうです」といったクッション言葉を使えば、受け取り手の抵抗感を和らげられます。
改善提案制度がある企業での進め方
改善提案制度が社内にある場合は、それを最大限に活用しましょう。制度によっては、提案のフォーマットや評価基準、インセンティブが明確に決められており、ルールに則って進めることでスムーズに評価されることがあります。
提案書を作成する際には、「現状」「課題」「改善案」「期待される効果」「費用やリスク」などを簡潔にまとめるのがポイントです。評価者にとって「判断しやすい」形で提出することで、採用率が高まります。
また、提案制度の中には「アイデア段階で応募可能」「少額改善案でも歓迎」といった柔軟な仕組みもあります。制度の目的や過去の採用事例を確認しておくと、自分の提案の方向性を決めやすくなるでしょう。
改善提案制度は、日常業務の気づきを形にする大切な機会です。制度がある環境がある方は、ぜひ積極的に活用してみてください。
「時間が足りない」「人手が足りない」と感じたら

業務改善に取り組みたいという意識があっても、現場では「日々の業務に追われて時間がない」「人手が足りず手を付けられない」という声がよく聞かれます。
しかし、その状況こそ、改善が必要なサインです。限られたリソースの中で効率化を進めるためには、外部の力を上手に取り入れるという選択肢があります。
業務改善には外部リソースの活用も有効
すべての業務を社内の人材だけで回そうとすると、どうしても手が回らない部分が出てきます。そこで有効なのが「外部リソースの活用」です。単純作業や定型業務、繁忙期だけ発生する仕事などは、外部に委託することで、社内リソースを本来注力すべき業務に集中させられるでしょう。
アウトソーシングは「人手不足を補う」ためだけでなく、「業務の質を一定に保つ」「教育や引き継ぎの負担を減らす」など、さまざまな面で業務改善に貢献します。特に事務作業や資料作成などは、ルールさえ整っていれば外部への切り出しがしやすく、導入ハードルも低い分野です。
オンラインアシスタント「フジ子さん」でできること

「フジ子さん」は、オンラインで利用できるアシスタントサービスで、主に中小企業やスタートアップのバックオフィス支援を行っています。依頼できる業務は多岐にわたり、以下のような作業を依頼可能です。
- 資料作成(Word・Excel・PowerPoint)
- データ入力・集計・加工
- 経理業務(仕訳・請求書作成など)
- スケジュール調整・メール対応
- 営業リスト作成・リサーチ業務
- 採用活動のサポート(候補者管理・日程調整など)
いずれもオンライン上でやり取りが完結するため、オフィスに常駐する必要はなく、業務単位で依頼できます。「時間がないけれど任せられる人がいない」「でも採用までは難しい」という現場には適した選択肢です。
導入の流れと相談方法
「フジ子さん」を導入する際は、まず公式サイトから無料相談を申し込めます。相談では、自社の課題や依頼したい業務内容をヒアリングしたうえで、どのように業務を分担できるかを提案してもらえます。
その後、業務内容のすり合わせを経て契約・業務開始となるため「いきなり使い始める」のではなく、段階を踏んで安心して導入できるのが特徴です。契約形態や料金も柔軟に設定できるため、まずは一部の業務だけ委託して、様子を見るといった使い方も可能です。
まとめ
業務改善は、日々の小さな課題に気づき、それを解決しようとする意識から始まります。とはいえ「やるべきことが多くて改善まで手が回らない」「人手が足りずに既存業務で精一杯」という声も現場ではよく聞かれます。そんなときこそ、外部リソースの活用を視野に入れてみてください。
オンラインアシスタント「フジ子さん」は、事務作業・営業支援・人事・経理など、幅広いバックオフィス業務をオンラインでサポートするサービスです。資料作成やデータ入力、スケジュール調整、SNSの運用補助といった業務を切り出すことで、社内の限られたリソースを本来のコア業務に集中させられます。
「まずは一部の業務だけ試してみたい」という場合でも、業務内容に応じて柔軟な利用が可能です。また、導入前には無料相談で業務内容や課題をヒアリングし、自社に最適な利用方法をご提案します。
「業務改善を進めたいけれど、時間も人手も足りない」と感じている方は、まずはフジ子さんの無料相談をご利用ください。業務の見直しと効率化の第一歩として、ご活用いただければ幸いです。