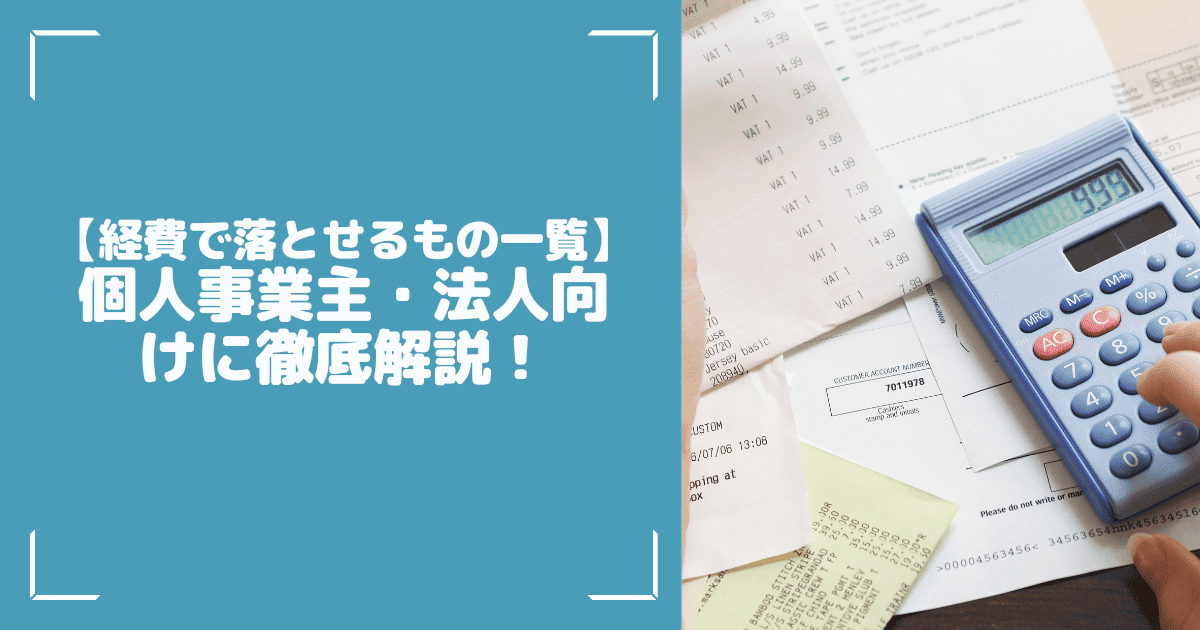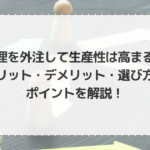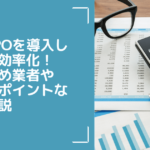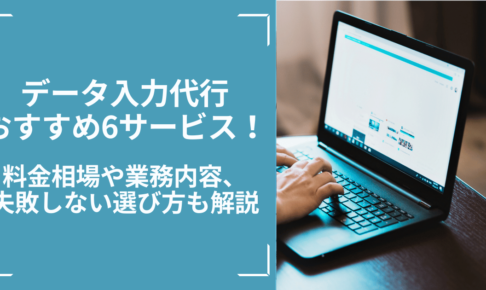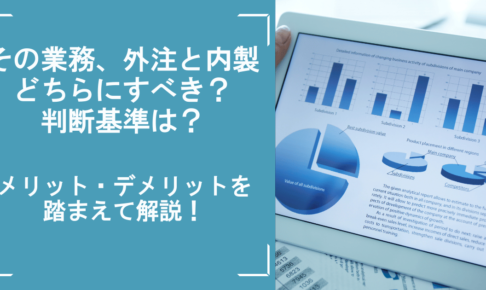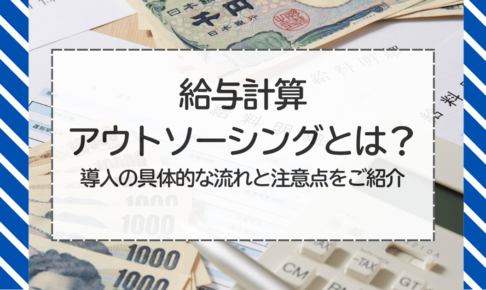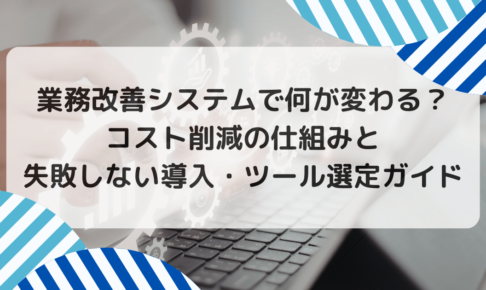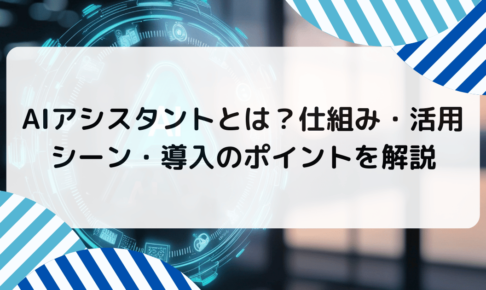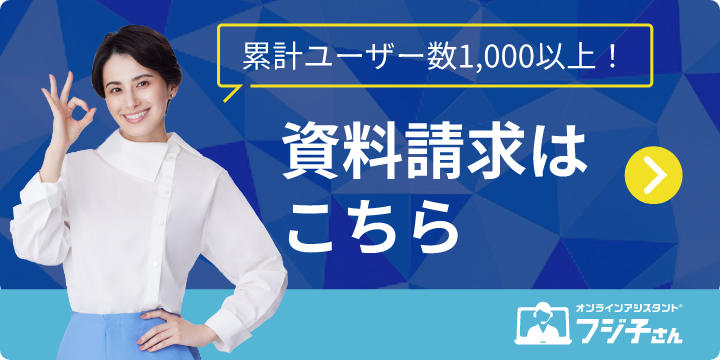事業を営むうえで欠かせない「経費」の知識。正しく経費を計上すれば、無駄な税金を減らし、健全な経営につながります。
しかし、「何が経費になるのか」「どこまでがOKなのか」は、個人事業主と法人とで違いがあり、あいまいな部分もあって判断に迷うものです。
本記事では、経費の基本から具体的な勘定科目一覧、よくあるNG例までを徹底解説。初めて確定申告に挑むフリーランスから、経費精算に悩む法人経営者まで、知っておきたい実践的な情報をわかりやすくお届けします。
目次
そもそも経費とは?

ビジネスをしているとよく耳にする「経費」という言葉。個人事業主やフリーランスの方はもちろん、会社員も知っておくべき大切な概念です。ここでは、経費の基本的な意味や、なぜ経費を正しく計上することが重要なのかをご説明します。
経費の定義
経費とは、仕事や事業を進めるために必要な支出のことです。例えば、仕事で使うパソコンの購入費用や、出張の交通費、事務所の家賃、仕事に使う文房具代などが経費にあたります。
逆に、プライベートで使ったお金(例えば家族での外食や趣味のための買い物)は経費にはなりません。
なぜ経費計上が重要なのか
経費をきちんと計上することには、主に2つの大きな目的があります。
1. 正しい利益を計算できる
会社や個人事業主は、売上から経費を差し引いた金額が「利益」になります。経費を正しく計上しないと、本当の利益が分からなくなってしまいます。
例えば、経費を計上し忘れると、実際よりも利益が多いように見えてしまい、経営の判断を間違える原因になります。
2. 税金を正しく計算できる
日本では、会社や個人事業主は利益に対して税金を払う仕組みになっています。経費をしっかり計上すれば、無駄な税金を払わずに済みます。
逆に、経費を計上し忘れると、本来より多く税金を払うことになってしまいます。
経費を正しく計上することで、会社や事業の本当の利益が分かり、税金も正しく計算できます。ビジネスをするうえで、経費の考え方はとても大切ですので、しっかり理解しておきましょう。
「経費で落とす」とはどういう意味?
「経費で落とす」とは、仕事や事業をする中で使ったお金を、経費として会計帳簿に記録することを指します。例えば、会社の会議のために使った飲食代や、仕事のために乗ったタクシー代などがこれにあたります。
この「経費で落とす」という処理をすることで、その支出は「仕事に必要だったお金」として扱われます。つまり、売上などの収入から経費を差し引いた残りが「利益」となり、その利益に対して税金がかかります。
例えば、会社で3万円の売上をあげ、そのために2,000円の交通費と、人件費10,000円の合計12,000円の経費を使ったとします。この12,000円を「経費で落とす」と、利益は18,000円になります。税金はこの18,000円に対してかかるので、経費で落とした分だけ税金を減らせます。
【重要】経費にできる?できない?判断するための3つの基準
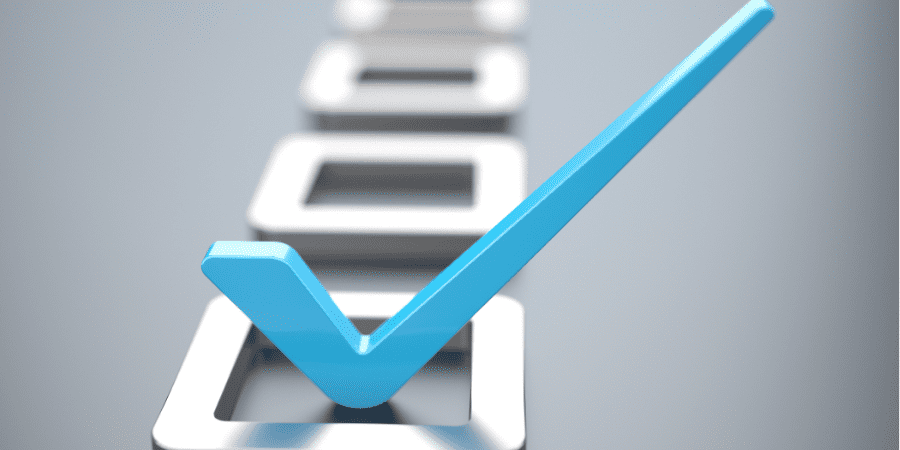
経費は、正しく使えば税金を減らす助けになりますが、もちろんなんでも経費にしてよいわけではありません。「これは経費になるのかな?」と迷ったときには、いくつかの判断基準があります。
ここでは、経費にできるかどうかを判断するための大切な3つの基準をご紹介します。
基準1:事業との関連性があるか
もっとも大切なのが、その支出が事業と関係していることです。
例えば、お客様との打ち合わせで使ったカフェ代や、営業のための交通費などは、仕事と関係があるので経費にできます。逆に、家族との外食や、自分の趣味で買った本などは仕事と関係がないので、経費にはなりません。
「この支出は、仕事をするために本当に必要だったか?」という視点で考えるとよいでしょう。
基準2:客観的に証明できる証拠があるか
次に大切なのは、その支出をきちんと証明できることです。
例えば、レシートや領収書があると、「いつ・どこで・何にお金を使ったのか」が分かるので、証拠になります。また、クレジットカードの明細や、出張の記録なども証拠として役立ちます。
ただ口頭で「これは仕事に使った」と言うだけでは、税務署に認めてもらえないこともあるため、記録をしっかり残しておくことが重要です。
基準3:社会通念上、妥当な金額であるか
3つ目の基準は、社会通念上、妥当な金額であることです。
例えば、打ち合わせのコーヒー代が1,000円くらいなら妥当ですが、1杯1万円の高級なコーヒーとなると、仕事の経費としては不自然に思われるかもしれません。
「この金額は、誰が見ても納得できるだろうか?」という視点を持つことが大切です。
【一覧】これは経費にできる!代表的な勘定科目と具体例
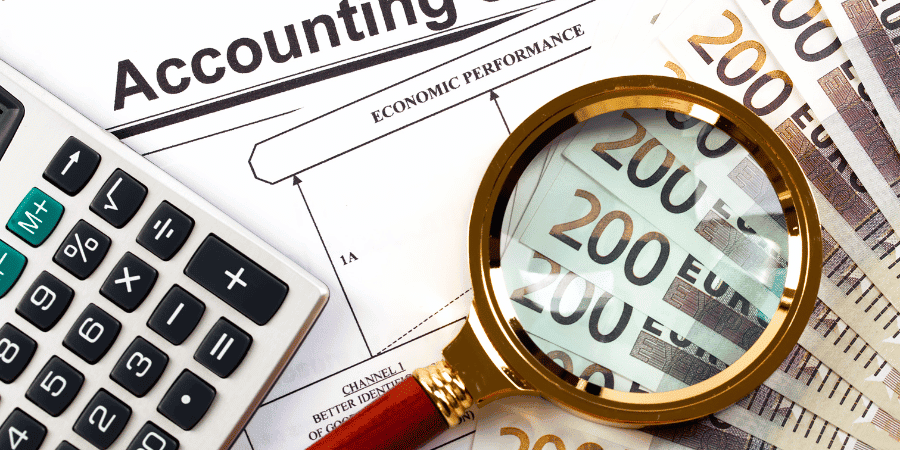
事業を行う上で発生するさまざまな費用は、正しく勘定科目に分けて経費計上することが重要です。ここでは、代表的な勘定科目とその具体的な例を一覧でご紹介します。
| 勘定科目 | 概要 | 概要 |
|---|---|---|
| 旅券交通費 | 仕事のなかで発生する移動や宿泊にかかる費用 | タクシー代、電車代、宿代、駐車場代など |
| 出張費 | 出張時に発生する費用。どこまでを経費として認めるかは、会社の規則に準ずる | 新幹線、飛行機代などの交通費や宿泊費、社員の慰労のための出張日当など |
| 接待交際費 | 取引先など、企業と関係のある人物に対して、接待・謝礼をする際にかかる費用 | 取引先との会食代、取引先に送るお中元の費用など |
| 会議費 | 会議を実施するための費用 | 会議のための場所代、印刷代、機材代など |
| 通信費 | 業務で使用する電話や郵便などの通信にかかる費用。ただし、個人事業主の場合は、スマホをプライベートと業務で併用するため、家事按分により一部のみを経費として計上する | 業務で使用するインターネット料金、電話代、郵便料金など |
| 水道光熱費 | 仕事中に使用した水道光熱費。ただし、自宅で仕事をしている場合、家事按分により一部のみを経費として計上できる | 水道代、電気代、ガス代など |
| 地代家賃 | 仕事をしている建物と土地の賃料。ただし、自宅を事務所としている場合、家事按分により一部のみを経費として計上できる | 家賃、管理費、共益費、礼金、敷金、駐車場代など |
| 消耗品費 | 業務上必要な備品のなかでも、比較的安価で、短期間で使い切れるものにかかる費用 | トイレットペーパー、名刺、文房具など |
| 新聞図書費 | 事業に関する知識や情報を集めるための図書にかかる費用。ただし、経営ノウハウ本など、業務と直接関連のない本は計上されない | 書籍、雑誌、新聞、電子書籍、メールマガジンなど |
| 車両運搬具 | 業務で使用する車両にかかる費用 | 業務で使用する自動車、オートバイ、トラック、バス、台車、電車車両など |
| 広告宣伝費 | 商品・サービスを宣伝する際に発生する費用 | ホームページの作成費用、広告掲載費用、チラシ作成費用など |
| 仕入 | 仕入れにかかった費用 | 原材料、商品製造に必要な機会にかかる費用など |
| 荷造運賃 | 商品の発送にかかる費用 | 段ボール箱、ガムテープ、ひもなどにかかる荷造費。宅配便、ゆうパック、航空費などにかかる運賃 |
| 給与 | 従業員に支払う給与 | 基本給、賞与、各種手当など |
| 福利厚生費 | 従業員のために使用される費用 | 社員旅行、社宅費用、忘年会費用、健康診断費用など |
| 法定福利費 | 事業主が負担する保険料 | 健康保険料、社会保険料、雇用保険、労災保険など |
| 保険料 | 事業に必要な保険にかかる費用 | 自動車保険料、火災保険料、地震保険料など |
| リース料 | 業務上必要でリースしているものに対してかかる費用 | 機械、車、エアコン、防犯カメラなど |
| 外注費 | 外部に依頼してかかった費用 | 外部業者に依頼したデザイン費、システム開発費など |
| 租税公課 | 税金の支払にかかった費用 | 消費税、個人事業税、固定資産税、事業で使用する車にかかる自動車税など |
| 減価償却費 | 購入した固定資産の価値の低下を事前に予測し、会計期ごとに分けて計上する費用のこと | 車両、建物、ソフトウェアなど |
| 支払手数料 | 事業のなかで発生する手数料や報酬などの支払にかかる費用 | 振込手数料、報酬・相談料、仲介手数料、解約手数料など |
| 支払利息 | 借入金の返済時に支払う利息にかかる費用のこと。例えば、借入金の10,000円は計上できないが、利息である1,000円は経費として計上できる | 借入金の返済時に発生する利息 |
| 修繕費 | 事業に必要な固定資産の修繕にかかる費用 | 機器のメンテナンス費用、排水管の修繕、外壁の塗り替えなど |
| 諸会費 | 業務に関連する団体への会費にかかる費用 | 業務に関連のある組合や法人会、商工会議所などに支払った会費 |
| 寄付金 | 国又は地方公共団体に対する寄付金、指定寄附金は全額経費として計上できる。一方、特定公益増進法人等に対する寄附金・一般の寄附金には限度額があり、限度額を超えると計上できない | 国や地方の公共団体に対する寄付金、通常の寄付金よりも公益性があると政府が判断した「赤い羽根募金」「日本赤十字社」など |
| 雑費 | 当てはまる勘定科目がない経費は、雑費に計上される | 引っ越し代、ゴミ処理代、キャンセル費用、クリーニング代など |
【要注意】これは経費にできない!間違いやすい費用の具体例
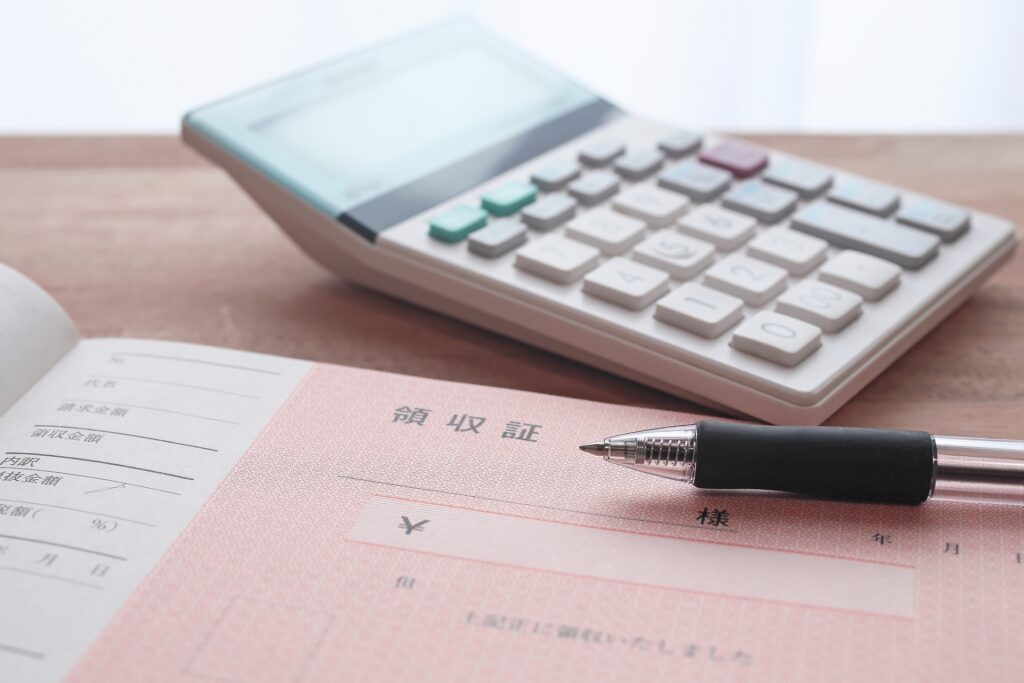
経費として認められない支出を誤って計上してしまうと、税務署から指摘を受ける可能性があります。以下に、特に注意が必要な費用の具体例を挙げて解説いたします。
個人的な支出(生活費、趣味の費用など)
事業とは関係のない個人的な支出は、経費として認められません。例えば、日常の食費や衣服代、趣味のための費用などが該当します。これらは事業の遂行に直接関係しないため、経費には計上できません。
罰金・科料・過料など
法律違反などにより科せられる罰金や科料、過料などの支出は、経費として認められません。これらは事業の遂行に必要な費用ではなく、社会的な制裁としての性質を持つため、経費には計上できません。
家族への給与(個人事業主の場合)
個人事業主が自分自身や生計を共にする家族に支払う給与は、原則として経費にできません。ただし、青色申告をしており、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、一定の条件を満たす場合には、家族への給与を経費として計上することが可能です。
過度に高額な費用
事業に関連する支出であっても、社会通念上妥当と認められないほど高額な費用は、経費として認められない可能性があります。
例えば、取引先との会食で極端に高額な飲食費を計上した場合などが該当します。経費として計上する際は、支出が事業の遂行に必要であり、かつ常識的な範囲内であることを意識することが重要です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 個人的な支出 | 日常の食費、衣服代、趣味の費用など、事業に関係ない支出。 |
| 罰金・科料・過料など | 法律違反等による社会的制裁としての支出は事業の必要経費と認められない |
| 事業主家族への給与(個人事業主の場合) | 生計を一にする家族への給与は原則として認められない。※青色申告+青色専従者給与に関する届出をしていれば経費として認められる。 |
| 過度に高額な費用 | 社会通念上妥当でない高額支出(例:極端に高額な会食)事業関連でも常識的な範囲が必要。 |
法人と個人事業主で異なる経費の取り扱い

法人と個人事業主とで、経費の取り扱いが異なります。
| 項目 | 個人事業主の取り扱い | 法人の取り扱い |
|---|---|---|
| 給与・賞与 | 事業主本人への支払いは経費にできない | 役員報酬・賞与は一定の条件を満たせば経費にできる |
| 退職金 | 事業主本人への退職金は経費にできない | 役員や従業員への退職金は条件を満たせば経費にできる |
| 家賃(住居費) | 自宅の一部を事業に使用する場合、使用割合に応じて経費計上可能(家事按分) | 法人名義で契約し社宅として提供することで経費計上可能(社宅に住む従業員などから家賃の徴収が必要) |
| 交際費 | 上限なし。ただし、事業との関連性を明確にする必要がある | 全額は経費にできない。 資本金1億円以下の中小企業は、年間800万円まで、または交際費総額の50%までが経費として認められる |
| 保険料 | 事業に関連する保険料のみ経費として計上可能 | 法人契約の保険料を経費に計上可能。ただし、契約内容によっては一部のみが対象となる場合がある |
| 福利厚生費 | 従業員がいない場合、福利厚生費として計上できる項目は限られる | 従業員への福利厚生費(例:健康診断費用、社員旅行費用など)を経費として計上可能 |
| 赤字の繰越控除 | 青色申告の場合、赤字を3年間繰越可能 | 赤字を最大10年間繰越可能 |
| 社会保険の負担 | 従業員が5人未満であれば社会保険への加入義務なし | 役員報酬がある場合、社会保険への加入義務が生じ、法人が半額を負担 |
| 経費の範囲 | 経費の金額に上限はないが、経費扱いにできる範囲が狭い | 経費の上限はあるが、経費にできる範囲が広い |
個人事業主が知っておくべき経費処理の重要ポイント:家事按分と減価償却

個人事業主として、経費を正しく計上することは、税金を適正に納めるために非常に重要です。特に、自宅を事務所として使用している場合や、高額な資産を購入した場合には、「家事按分」や「減価償却」をよく理解しておきましょう。以下に、それぞれのポイントを解説します。
家事按分とは?自宅兼事務所の費用を分ける方法
「家事按分(かじあんぶん)」とは、事業と私生活で共用している費用を、使用割合に応じて分けることを指します。例えば、自宅の一部を事務所として使用している場合、家賃や光熱費などを事業用と私用に分け、事業用の部分のみを経費として計上します。
家賃、水道光熱費、通信費などの按分計算例
按分の方法には、使用面積や使用時間に基づく計算があります。
例えば、1日24時間のうち、事業に使用する時間が6時間であれば、6時間 ÷ 24時間 = 0.25(25%)となり、家賃の25%を経費として計上できます。
同様に、自宅で事業を行っており、事業での使用面積が全体の30%であれば、家賃の30%を経費とすることが可能です。水道光熱費や通信費も同様に、使用割合に応じて按分します。
なお、按分の割合は、合理的かつ客観的に説明できる基準に基づいて設定することが求められます。
【関連記事】
自営業・個人事業主は経理を自分でやるべき?やり方、おすすめの会計ソフトや代行などを紹介
減価償却とは?高額な資産を数年に分けて経費化する仕組み

「減価償却」とは、高額な資産を購入した際に、その費用を一度に全額経費とせず、資産の耐用年数に応じて数年に分けて経費として計上する方法です。
減価償却によって資産の価値の減少を適切に反映し、税務上の利益を正確に計算できます。
減価償却の対象となる資産(パソコン、車両運搬具など)
減価償却の対象となる資産には、パソコン、車両運搬具、事務所の設備などがあります。
例えば、10万円以上のパソコンを購入した場合、耐用年数(通常は4年)に基づいて、毎年一定額を経費として計上します。
※30万円未満の資産については、一定の条件を満たす場合に一括で経費計上できる特例もあります。
参考:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁)
定額法と定率法の違い
減価償却の計算方法には、「定額法」と「定率法」の2種類があります。
- 定額法:毎年同じ金額を減価償却費として計上する方法です。個人事業主の場合、原則として定額法を使用します。
- 定率法:毎年、残りの資産価値に一定の割合をかけて減価償却費を計上する方法です。初年度の減価償却費が最も大きく、年々減少していきます。定率法を適用する場合は、事前に税務署への届け出が必要です。
これらの方法を適切に選択し、正確に減価償却を行うことで、税務上のリスクを回避し、適正な経理処理が可能になります。
経費計上の必須知識!必要な証拠書類と7年間の保存義務

経費を正しく計上するためには、適切な証拠書類の保管が欠かせません。税務調査の際には、これらの書類が必要となるため、日頃からの管理が重要です。
なぜ領収書やレシートが必要なのか?
領収書やレシートは、実際に支出があったことを証明するための書類です。これらがないと、経費として認められない可能性があります。また、税務調査の際には、支出の内容や金額を確認するために提出を求められることがあります。
領収書・レシートの正しいもらい方とチェックポイント
領収書やレシートを受け取る際には、以下の点を確認しましょう。
- 日付:取引が行われた日付が記載されているか。
- 金額:支払った金額が正確に記載されているか。
- 宛名:自社名や事業主名が記載されているか(レシートは宛名がなくても経費計上できる場合もある)
- 但し書き:具体的な取引内容が記載されているか。
- 発行者名:住所、電話番号が記載されているか。
- 担当者印や社印:特に手書きの領収書の場合は必要
- 収入印紙:5万円を超える現金取引の場合、収入印紙が必要
これらの情報が記載されていない場合は、再発行を依頼するか、追記してもらうようにしましょう。
領収書がない場合の対処法(出金伝票、招待状なども活用)
やむを得ず領収書やレシートが入手できなかった場合は、以下の方法で対応できます。
- 出金伝票の作成:支出の内容や金額、日付などを記録した出金伝票を作成します。
- 関連書類の保存:招待状や案内状、メールのやり取りなど、支出の事実を証明できる書類を保存します。
- メモの作成:支出の目的や内容を詳細に記載したメモを作成し、保存します。
これらの対応を行うことで、税務調査の際に支出の正当性を説明しやすくなります。
その他の重要な証拠書類(請求書、契約書、納品書など)
経費計上においては、領収書やレシート以外にも、以下の書類が重要です。
- 請求書:取引先からの請求内容を確認できます。
- 契約書:取引の内容や条件を明確にするため│必要です。
- 納品書:商品やサービスの納品を確認するための書類です。
これらの書類も、経費計上の際には保管しておくことが求められます。
書類の保存期間と方法│電子帳簿保存法にも対応が必要
経費に関する書類の保存期間は、以下の通りです。
- 法人:原則として7年間の保存が義務付けられています。
- 個人事業主(青色申告):7年間の保存が必要です。
- 個人事業主(白色申告):5年間の保存が求められます。
保存方法については、紙媒体での保管だけでなく、電子帳簿保存法に基づき、電子データでの保存も可能です。ただし、電子保存を行う場合は、改ざん防止のための措置や、検索機能の確保など、一定の要件を満たす必要があります。
適切な保存を行うことで、税務調査の際にもスムーズに対応でき、経費計上の信頼性を高められます。
経費で落とせるもの・落とせないものを正しく理解して正しく申告を
経費の取り扱いは、事業者としての適正な納税義務を果たすうえで非常に重要なポイントです。
業務に必要な支出であっても、税法上「経費」として認められるかどうかはケースによって異なり、判断が難しい場面も多くあります。
特に、プライベートとの境界があいまいな支出や高額な費用を計上する際には注意が必要です。
こうした煩雑な経理処理や判断に悩む時間を減らしたい場合は、経理業務のアウトソーシングも有効な選択肢です。専門知識を持つプロが日々の記帳や経費処理をサポートしてくれるため、本業に集中しながら、正確かつ効率的に経理を進めることができます。
本ブログを運営しているフジ子さんでは、経理の実務経験が豊富なスタッフが経理業務のサポートをさせていただきます。
経理業務のアウトソーシングに興味がおありでしたら、ぜひ一度お問い合わせください。
【関連記事】