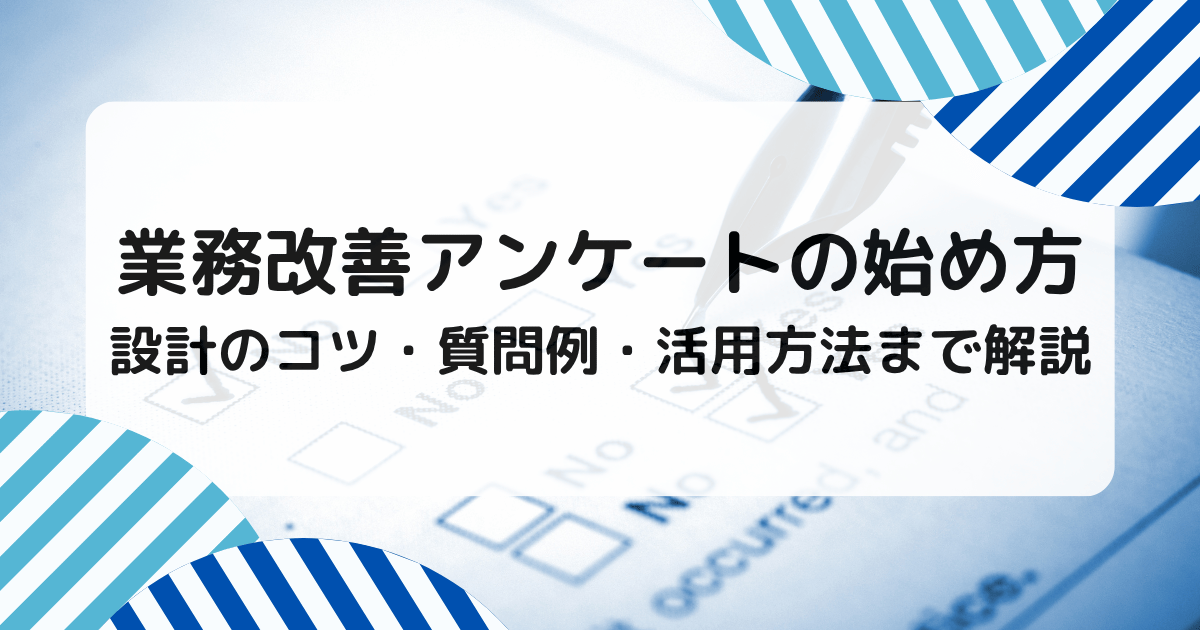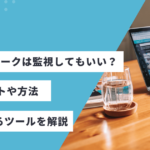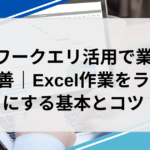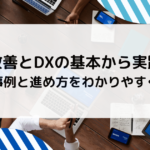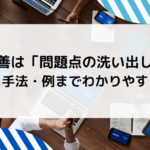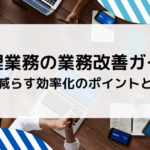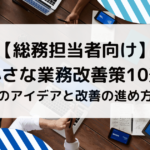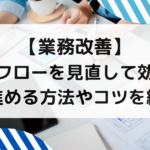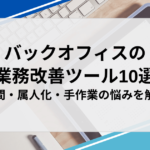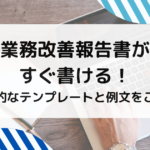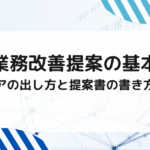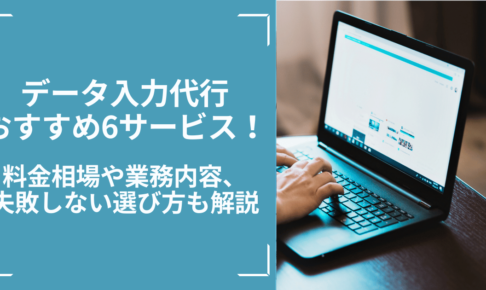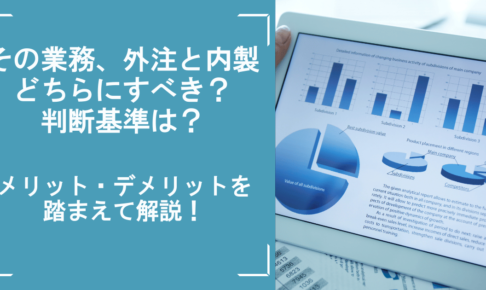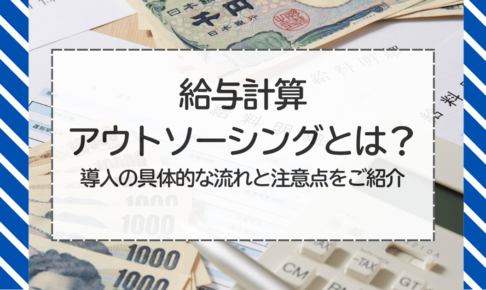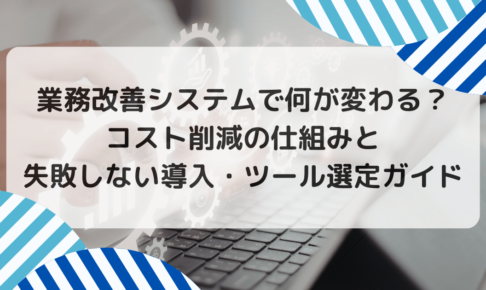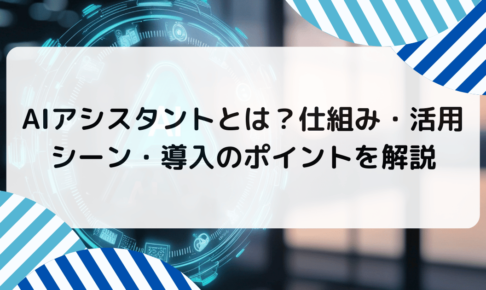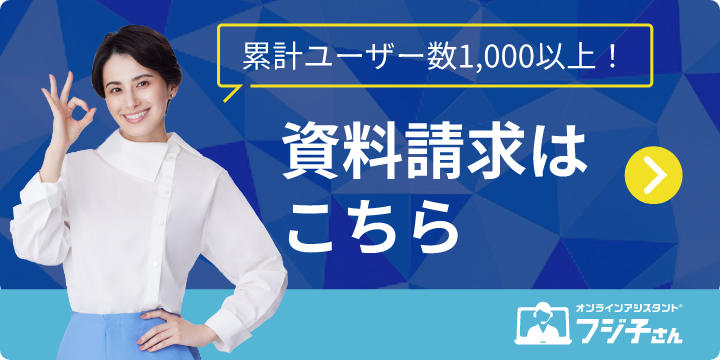業務のムダや非効率を見直し、働きやすい職場環境をつくるには、現場で働く従業員の声に耳を傾けることが欠かせないものです。しかし、誰もが率直な意見を口にしてくれるとは限らず、表に出にくい課題が埋もれてしまうことも少なくありません。
そうした現場の本音を引き出し、業務改善につなげる手段として注目されているのが「社内アンケート」です。匿名で実施できるアンケートであれば、普段は言いづらい不満や気づきを拾い上げやすく、ボトルネックの可視化にもつながります。
とはいえ、「どんな質問を用意すればよいのか」「どう設計すれば効果的なのか」といった点で悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、業務改善を目的としたアンケートの作り方や設問例、実施後の活用方法までをわかりやすくご紹介します。初めて取り組む方でも安心して進められるよう、基本ステップに沿って解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
業務改善は“現場の声”から始まる
業務改善を進めるうえで最初に必要なのは、「何が問題となっているのか」を正しく把握することです。効率が悪い、ムダが多いといった感覚があっても、具体的にどこに課題があるのかが見えていなければ、適切な改善策は打てません。
そこで重要になるのが、現場で働く従業員の声です。実際の業務を担っているからこそ気づける課題や、日々の中で感じているストレス、不満など、表には出にくい本音のなかにこそ、改善のヒントが隠れています。
とはいえ、そうした声を自然に拾うのは簡単ではありません。上司や人事に直接伝えるのは気が引ける、職場の空気を乱したくないといった心理的ハードルがあるからです。
そこで活用したいのが社内アンケートです。匿名性を確保した形で意見を募ることで、普段は見えにくい課題や意見を可視化できます。
【関連記事】
業務改善にアンケートが有効な理由

社内アンケートは、業務改善を効果的に進めるための手段として、多くの企業で活用されています。ここでは、アンケートが業務改善に有効である理由を3つに分けてご紹介します。
現場の課題を可視化できるから
業務の中に潜む非効率やストレスの多くは、現場で働く従業員にしか気づけないことがあります。アンケートを通じてそのような声を拾うことで、普段は表面化しにくい問題点を“見える化”できます。
例えば、「○○の申請に時間がかかる」「上司に相談しづらい」といった細かな不満も、集まれば重要な改善ポイントになります。気づきにくい業務のボトルネックを明らかにするために、アンケートは非常に有効です。
従業員の納得感と参加意識を高められるから
アンケートで自分の意見が求められることは、従業員にとって「改善に参加している」という実感につながります。また、アンケート結果が実際の改善施策に反映されれば、会社への信頼感も高まるでしょう。
このように、従業員の声を尊重する姿勢は、職場の雰囲気を良くし、改善活動の定着にもつながります。組織全体を巻き込む土台づくりとしても、アンケートは有効なツールといえるのです。
データに基づく改善施策を立てやすくなるから
感覚や印象に頼った改善では、施策が的外れになることもあります。アンケートの結果をもとにすれば、数値や傾向から課題を把握できるため、客観的な根拠に基づいた改善が可能です。
例えば、「○○に不満を感じている人が全体の◯割いる」といった定量データがあれば、上層部への説明や予算確保も行いやすくなります。業務改善を継続的に進めるための判断材料としても、アンケートの存在は重要です。
アンケート設計の基本3ステップ
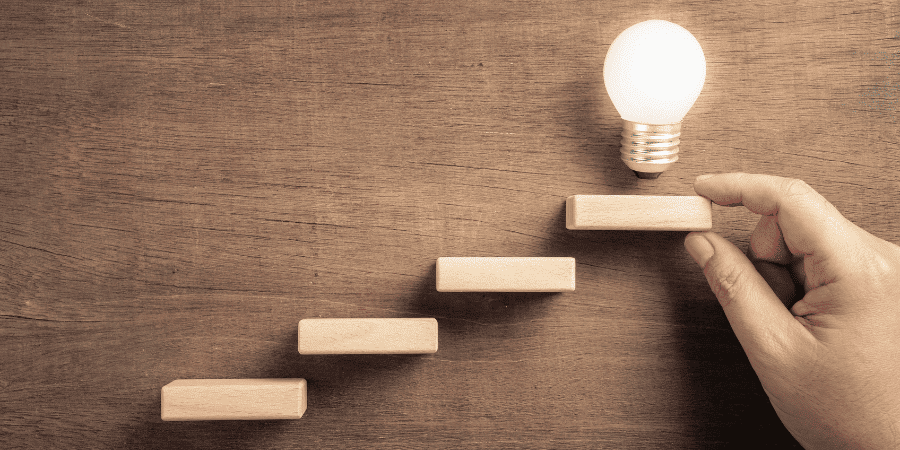
業務改善につながる社内アンケートを行うためには、感覚的に質問を並べるだけでは不十分です。目的を明確にし、対象や設問を丁寧に設計することで、初めて意味のあるデータが集まります。
ここでは、アンケートを設計する際に押さえておきたい3つの基本ステップをご紹介します。
ステップ1:目的を明確にする
まず最初にすべきことは、「なぜアンケートを実施するのか」という目的をはっきりさせることです。業務改善と一口に言っても、目的によって聞くべき内容は大きく変わります。
例えば、「業務フローの効率化」が目的であれば、作業手順や時間のかかっている業務について尋ねる設問が必要です。一方で、「職場環境の改善」が目的であれば、人間関係や設備、制度に関する質問が中心になるでしょう。
目的が不明確なままアンケートを作ると、質問の焦点が定まらず、集めた回答が改善に結びつかない恐れがあります。設計の第一歩として、目的をしっかり定めておきましょう。
ステップ2:設問形式を選ぶ(定量・定性のバランス)
次に検討すべきは、どのような形式の設問を用意するかという点です。アンケートの設問には、数値で評価する「定量的」なものと、自由に記述してもらう「定性的」なものがあります。
例えば、「業務に無駄があると感じますか?」という質問に対して、5段階評価で答えてもらうのが定量的な設問です。一方で、「業務の中で改善したい点があれば教えてください」というような自由記述は定性的な設問です。
定量データは集計・比較がしやすく、傾向を把握するのに適しています。一方、定性データは具体的な課題や背景を深掘りするのに有効です。両方をバランスよく組み合わせることで、より実用的なアンケートになります。
ステップ3:実施対象とタイミングを決める
設問が固まったら、誰にいつアンケートを実施するかを決めましょう。全社的に実施するのか、あるいは特定の部署や職種に絞るのかによって、設問の内容や表現も調整が必要です。
また、アンケートを実施するタイミングも重要です。繁忙期を避ける、一定期間継続して実施するなど、回答しやすい環境を整えることで、回収率や回答の質が高まります。
アンケートはあくまで「聞くための仕組み」です。届けたい人に適切な方法とタイミングで実施することが、よい結果につながります。
業務改善に直結する質問例をカテゴリ別にご紹介
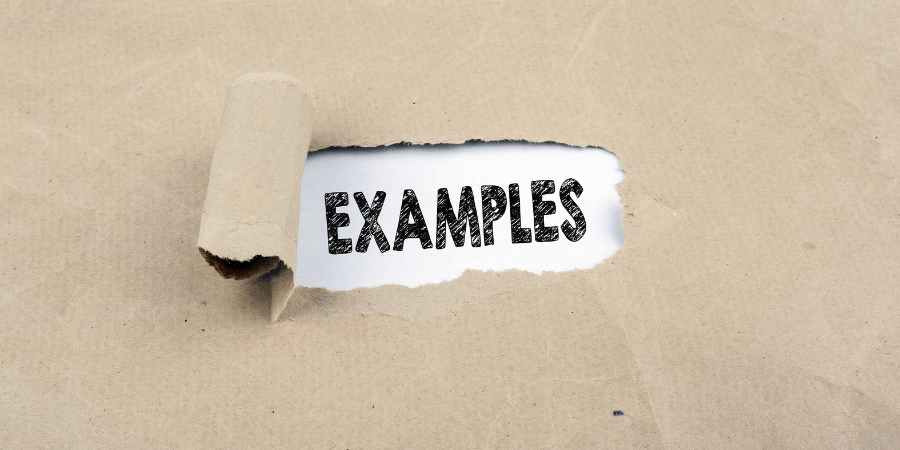
社内アンケートを作成する際、「どんな質問をすればよいのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。目的に合った質問を設定することで、より具体的で実用的な情報を引き出せます。
ここでは、業務改善につながりやすい質問例をカテゴリ別にご紹介します。アンケート設計時の参考にしてみてください。
業務効率に関する質問例
業務のムダや手間を把握するには、現場で実際に作業している従業員の声が欠かせません。普段の業務の中で非効率だと感じていることや、改善したいと考えている点を尋ねることで、見直すべき作業フローや仕組みが明らかになります。
例えば、以下のような質問が考えられます。
- 業務の中で無駄だと感じる作業はありますか?
- 時間を多く取られている業務はどれですか?
- 自動化・簡素化できそうな作業はありますか?
このような質問を通じて、業務改善の優先度や具体的な見直しポイントを見つけられます。
人間関係・コミュニケーションに関する質問例
業務効率と同じくらい、職場の人間関係や情報共有のしやすさも、働きやすさや改善のヒントに大きく関わります。伝達ミスや相談のしづらさが業務の停滞につながることもあるため、こうした面もアンケートで把握しておくことが重要です。
以下のような質問が活用できます。
- 困ったときに相談しやすい職場だと感じますか?
- チーム内や他部署との情報共有で不便を感じることはありますか?
- 業務上のコミュニケーションにおいて、改善したい点があれば教えてください。
こうした設問を通じて、コミュニケーションに関する課題を可視化し、連携の改善や心理的安全性の向上につなげられます。
職場環境・制度に関する質問例
業務そのものだけでなく、働く環境や制度への満足度も、従業員のモチベーションや生産性に直結します。アンケートでは、設備や勤務体制、評価制度などに対する意見を聞くことで、見落とされがちな改善ポイントを発見できます。
例えば、次のような設問が有効です。
- 業務に集中しやすい職場環境が整っていると感じますか?
- 勤務時間や休暇制度に対して、不満に感じている点はありますか?
- 評価やフィードバックの仕組みに納得感はありますか?
- 働きやすさを高めるために、あったほうがよいと感じる制度はありますか?
こうした質問から、制度や環境に対する従業員のリアルな声を拾い、より快適で生産性の高い職場づくりにつなげることができます。
アンケートの結果を活かすためにやるべきこと4つ
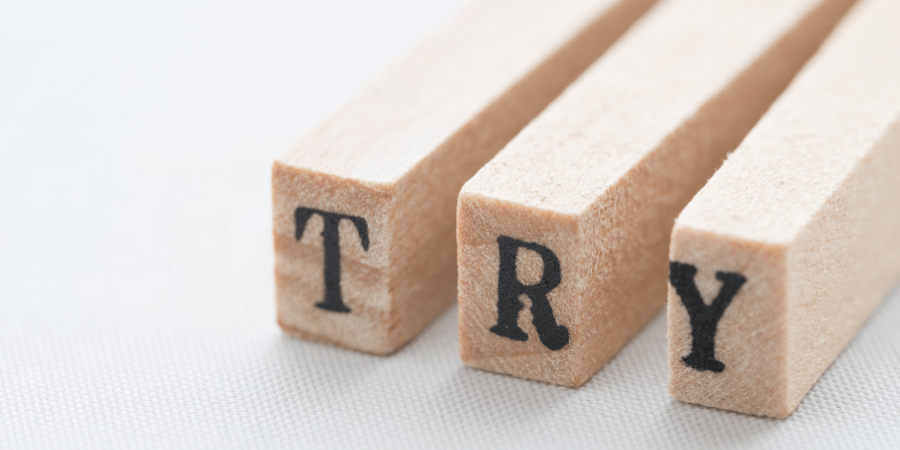
アンケートは実施しただけでは意味がありません。集まった声をどのように整理し、どのように改善に活かしていくかが、業務改善の成否を左右します。ここでは、アンケート結果を無駄にしないために必要な4つのポイントをご紹介します。
匿名性と信頼を担保する
アンケートを通じて本音を引き出すためには、従業員が「安心して答えられる」環境を整えることが欠かせません。特に社内アンケートでは「誰が何を言ったか特定されるのでは」といった不安があると、回答を控えたり、無難な内容にとどめてしまったりするケースが少なくありません。
そのため、アンケートの設計段階で匿名性を担保することが大前提となります。記名欄を設けないのはもちろん、部署や役職などの属性を過剰に聞きすぎないこともポイントです。
また、システム上のアクセス履歴やIPアドレスが記録される可能性がある場合は、その扱いについても明記しておくと安心感が増します。
さらに、「アンケートは業務改善のために活用する」という目的を、実施前にしっかり説明しておくことも重要です。何のために行うのか、どのように集計され、どのように使われるのかを透明にすることで、回答者との信頼関係が築かれやすくなります。
回答結果を分析しやすい形で整理する
アンケートの価値は、集まった回答をどう整理・分析し、改善に活かせる形にできるかで決まります。設問ごとの傾向を把握するだけで終わってしまうと、具体的なアクションにつなげにくく、形だけのアンケートになってしまうことも。
まずは、定量的なデータ(例:5段階評価など)については、集計結果をグラフ化したり平均値・割合を算出したりすることで、全体傾向が見えやすくなります。部署別・役職別などに集計を分ければ、課題が偏っているポイントも明確になるでしょう。
一方で、自由記述のような定性的な回答は、回答内容を分類・タグ付けすることで、意見の傾向を整理しやすくなります。例えば「人間関係」「業務フロー」「制度への不満」といったカテゴリに分類し、頻出するキーワードを抽出するだけでも、重点的に検討すべきテーマが見えてきます。
こうした整理を通じて、「声」を「改善の材料」に変換することが、アンケート活用の出発点となります。
課題の背景を読み取り、改善提案に落とし込む
アンケート結果から得られた意見や不満を、ただ並べるだけでは業務改善にはつながりません。大切なのは、その背後にある「なぜそう感じているのか」という背景や根本原因を読み取ることです。
例えば「○○の手続きが面倒」という回答があった場合、その業務フローが複雑すぎるのか、説明が不十分なのか、それとも関係者の調整に時間がかかっているのか──背景によって対処すべき内容はまったく異なります。
こうした原因を探る際には、現場の担当者にヒアリングを行ったり、業務フローを可視化して確認したりするのも有効。アンケートはあくまで入り口であり、そこから一歩踏み込んだ検討が必要です。
そのうえで、現実的に実行可能な改善策を提案としてまとめることが求められます。リソースやコスト、社内の合意形成なども考慮しつつ、「実現できる範囲で、効果が見込める施策」を形にすることが、アンケートを活かす鍵となります。
結果と対応を現場にフィードバックする
アンケートに協力してくれた従業員に対して、「集めた声をどう扱ったのか」を伝えることは、改善活動を継続するうえで非常に重要です。せっかく率直な意見を寄せても、それが共有されず、何の変化も起きなければ、「どうせ言っても無駄だ」と感じてしまう原因になります。
そのため、アンケートの結果を集計・分析したあとは、全体傾向や寄せられた声の要約を共有し、どのような改善を行う予定か、あるいは今後どう検討していくかを、できる範囲で伝えることが望ましいです。すべての意見に対応できなくても、「この声にはこう応えた」「これは今後の検討課題にしている」と示すだけでも、信頼感につながります。
また、フィードバックをきちんと行うことで、次回以降のアンケートでも本音が集まりやすくなり、改善サイクルが回りやすくなります。アンケートは“聞く”だけでなく、“応える”ことによって、はじめて意味を持つものだといえるでしょう。
【関連記事】
これで伝わる!業務改善提案書をパワーポイントで作る方法【無料テンプレートプレゼント】
社内リソースに限界を感じたら、フジ子さんという選択肢も

アンケートの設計、実施、集計、分析、そして改善提案やフィードバックまで。こうした一連の流れを社内だけで完結させるのは、実際には容易ではありません。特に、通常業務と並行してこれらのタスクを進めなければならない人事・総務担当者にとっては、時間的・人的な負担が大きくなりがちです。
「やりたいことは明確だけど、そこまで手が回らない」「課題の整理や提案にもう少し客観的な視点がほしい」——そんなときに、外部の支援を検討してみるのも一つの手です。
例えば、オンラインアシスタントサービス「フジ子さん」では、アンケートの設計支援や集計作業、資料作成など、業務改善の周辺業務を柔軟にサポートすることが可能です。必要なところだけを任せられるので、限られたリソースでも効率的に改善活動を進めることができます。
社内に蓄積された声を、きちんと形にしていくために。必要に応じて、外部の力も活用しながら、無理なく前向きな業務改善を目指していきましょう。
まとめ|まずは小さな一歩から始めよう
業務改善において、従業員の声を集めることは決して難しいことではありません。しかし、それを形にしていくには、丁寧な設計と継続的な運用が必要です。社内アンケートは、その第一歩として非常に有効な手段です。
本記事では、アンケートの目的設定から設問設計、質問例、実施後の活用方法までをご紹介してきました。すべてを一度に完璧に行う必要はありません。まずは目的を明確にし、数問からでもアンケートを始めてみることで、社内に「声を聞く文化」を育てていくことができます。
大切なのは、集めた声を改善につなげ、行動で応えていくこと。その積み重ねが、従業員との信頼関係を築き、業務の質を着実に高めていきます。
できることから、少しずつ。まずは小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。