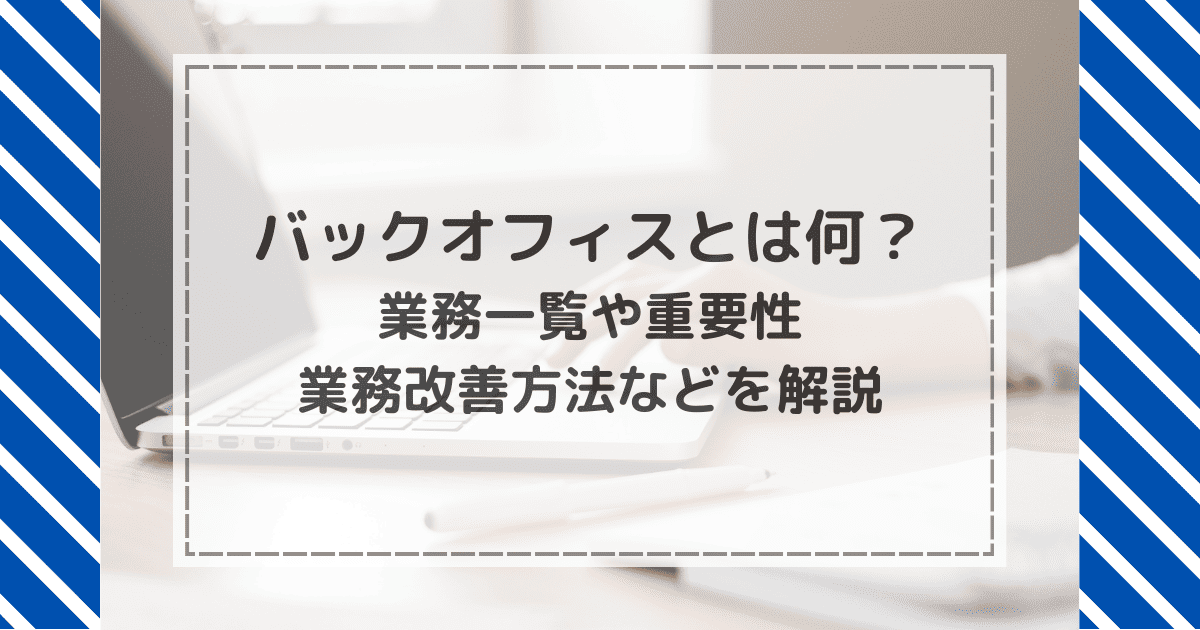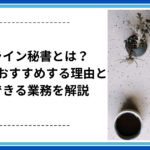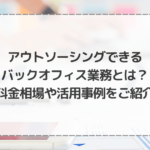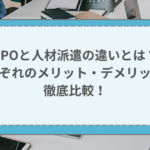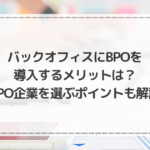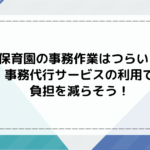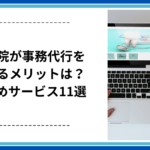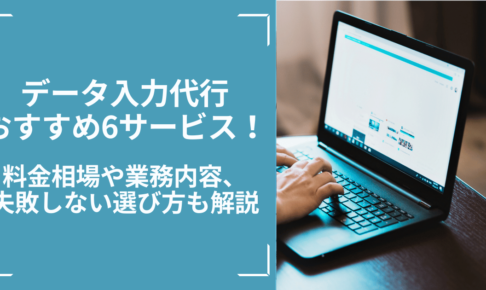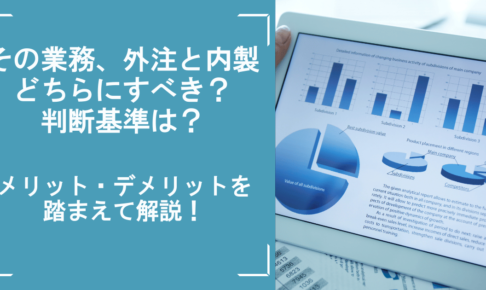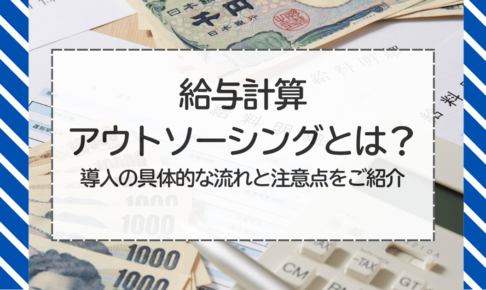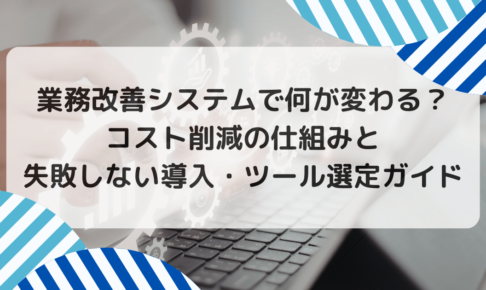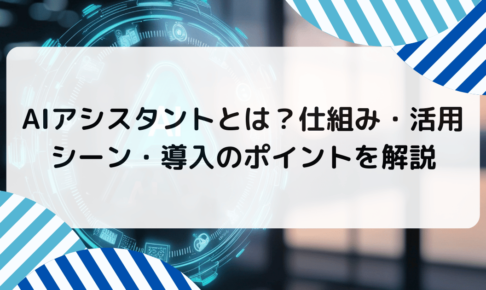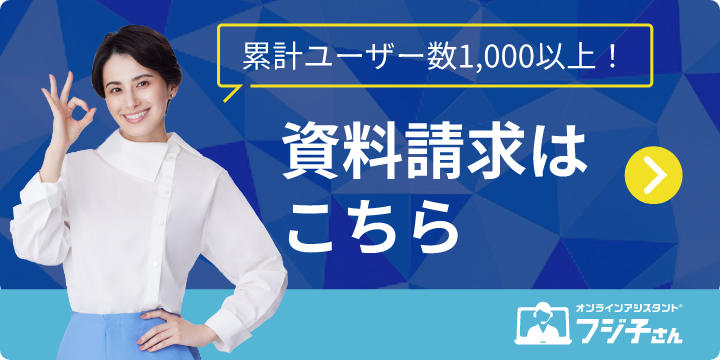企業運営における業務は、フロントオフィスとバックオフィスに大別されます。
「フロント」の文字が示すように、フロントオフィスは前に出る、つまり顧客と直接関わる部署のことです。逆にバックオフィスは、顧客と直接関わらない部署です。フロントオフィスを正常に機能させて利益を生み出すには、バックオフィスの下支えが欠かせません。
本記事では、会社運営で重要なバックオフィスの意味や役割について解説していきます。
目次
バックオフィスとは?その役割とフロントオフィスや一般事務との違い

冒頭で述べたとおり、バックオフィスとはお客様と直接関わらない仕事です。具体的には、一般事務、人事、総務、経理、法務などが挙げられます。
その役割はフロントオフィスと呼ばれる、営業やマーケティング、カスタマーセンターといった顧客と直接関わる部署のサポートです。
会社運営におけるバックオフィスの重要性
どんなにフロントオフィスが優秀でも、バックオフィス業務が滞ると企業活動は成り立ちません。その理由は、バックオフィスは企業の4大経営資源「ヒト・モノ・カネ・情報」を管理する部門だからです。
例えば、お金の管理なしには営業もマーケティングもできません。有給休暇や福利厚生などの管理も、従業員満足度に直結するバックオフィス業務のひとつです。
このようにバックオフィスは、企業活動をうまく進めるための縁の下の力持ちの役割を担います。フロントオフィスに比べて軽視されがちですが、企業運営において不可欠な存在です。
フロントオフィスとの違い
バックオフィスとフロントオフィスとの違いは、
- 顧客と直接関わるかどうか
- 直接の利益を生み出すかどうか
にあります。
フロントオフィスは、顧客と直接コミュニケーションをとり、直接利益を生み出す部門です。例えば営業、コールセンター、マーケティング部門などが挙げられます。
一方バックオフィスでは、顧客と直接関わることはなく、直接の利益は発生しません。利益を出すのはフロントオフィスの役割ですが、それを可能にするにはバックオフィスの存在が必要不可欠です。経理や人事なしに営業はできません。
一般事務との違い
バックオフィスと一般事務は混同されやすいですが、位置づけが異なります。
バックオフィスは企業活動を支える幅広い業務領域で、人事・総務・経理・財務・法務・情報システムなど、経営に関わるさまざまな役割を担っています。
一方、一般事務はその一部にあたり、主にデータ入力や書類作成といった日常的な事務処理や管理業務を担当する職種です。
つまり、一般事務はバックオフィス業務の中に含まれる役割であり、バックオフィス全体はそれを含めた広範な業務を指す概念です。
どちらも直接利益には結びつきにくいものの、企業活動には欠かせない存在といえます。
バックオフィスの言い換えと対義語

バックオフィスの言い換えと対義語は以下のとおりです。
バックオフィスの言い換え
- 間接部門(利益創出へ間接的に関わることから)
- 管理部門(業務管理にまつわる仕事が中心なことから)
- 事務部門(事務がメインなことから)
バックオフィスの対義語
- フロントオフィス(「バック」に対することから)
- 直接部門(間接部門に対することから)
- 営業部門、顧客部門(顧客と直接関わることから)
バックオフィスの仕事・業務一覧

企業によって多少の違いはありますが、バックオフィスに該当する部門と主な仕事内容は以下のとおりです。
部門 | 仕事内容 |
|---|---|
|
一般事務 | データ入力、ファイリング、メールチェック、電話応対、来客応対、その他雑務など |
|
人事・労務 | 社員の採用や研修、部署異動、給与計算、労働管理など人材に関わる業務全般 |
|
総務 | 消耗品・備品の管理、社員の健康診断管理、社内・社外報作成、就業規則管理、イベントの企画・立案・実行など |
|
経理 | 会社のお金の流れに関する業務全般(売掛金、買掛金の管理、経費精算、その他帳簿管理、給与計算など) |
|
財務 | 資金繰りや予算管理、資金調達、余裕資金の運用など |
|
法務 | 企業においての法律に関する業務全般(登記や商取引など) |
|
広報 | プレスリリース配信、広報誌・Webサイト・ソーシャルメディアでの情報発信、社内広報による情報共有など |
|
営業事務 | 営業マンの補佐(見積書や契約書の作成・顧客情報管理・プレゼン資料の作成など) |
|
情報システム | ネットワークの構築・運用、セキュリティ対策など |
バックオフィス業務でありがちな課題

このように重要性の高いバックオフィス業務ですが、だからこそ課題も多いものです。ここでは、バックオフィス業務でありがちな課題を3つご紹介します。
業務が属人化しやすい
1つめは、業務が属人化しやすいことです。
経理や法務など、バックオフィスには専門性の高い業務が多くあります。これらを担当できるのは、相応のノウハウを持つ人材だけです。よって、仕事が特定の担当者に集中してしまう傾向にあります。
その担当者が病欠したり仕事を辞めたりすると、バックオフィス業務が回らず、フロントオフィス業務にも影響が出る可能性があります。
人手不足だと後回しになりやすい
2つめは、人手不足だと後回しになりやすいことです。
人手不足の会社では、どうしてもフロントオフィスへリソースを集中させざるを得ず、バックオフィス業務が後回しになるケースが珍しくありません。期日が迫ってから残業をして事務仕事を終わらせる、といったこともよくあるでしょう。
また、バックオフィスの中でも人事と経理を兼任させている会社もあるでしょう。その場合、業務量によっては手が回らない仕事も出てきてしまいます。
さらに、期末や採用シーズンなど、バックオフィスは忙しい時期と余裕がある時期の業務量に大きな差があります。とはいえ、時期に合わせて一時的に人員を増減するのは現実的ではありません。そのため、人員の配置が難しく、毎年人員不足に頭を抱えつつも解消できていない企業が多くあります。
働き方改革とテレワークの影響
3つめは、働き方改革とテレワークの影響です。
働き方改革により、業務効率化が求められるようになりました。バックオフィスの効率化を図るには、定型業務のシステム化やアウトソーシングが重要です。
しかし日頃の業務に追われ、「分かっているけれど、忙しくて導入できない」という会社は少なくありません。
まだまだ紙文化が根強く残っている企業では、文書の印刷、回覧、ハンコの押印、郵送など、オフィスでしか対応できない作業があります。そのため、バックオフィス業務をテレワーク化しにくいこともあるでしょう。このような時流への対応という点も、バックオフィスの大きな課題といえます。
バックオフィス業務を効率化するメリット

バックオフィス業務を効率化することで、これらの課題を解決できるなど、多くのメリットがあります。そのメリットを7つご紹介します。
コストを削減できる
定型作業を自動化することで、バックオフィス業務に割く人件費を削減できます。また、文書を電子化することでペーパーレス化が実現できれば、紙・インク・印刷代や郵送費などのコスト削減にもつながるでしょう。
ヒューマンエラーを防止できる
バックオフィス業務では、データの入力・集計・照合といった作業が行われます。これらの業務を手作業で行なっていると、入力ミスやチェック漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性は避けられません。これらを自動化・電子化・システム化することで、正確に処理できるようになり、ヒューマンエラーの防止につながります。
また、経理や労務上のミスによってコンプライアンス違反やセキュリティ事故が発生するリスクを抑えられ、業績や企業の信用が損なわれる事態を回避できます。
生産性を向上できる
定型作業の自動化や文書の電子化を行うことで、バックオフィス業務にかける作業工数を削減できます。その結果、フロントオフィス業務やマネジメント業務など、より付加価値の高い業務に注力できるようになり、組織全体の生産性向上にもつながるでしょう。
業務の属人化から脱却できる
デジタルツールや外部委託をうまく活用したり、業務マニュアルを整備したりすることで、特定の従業員でなくても一定のクオリティで業務を回せるようになります。そのため、退職や人事異動の際も、スムーズに業務の引き継ぎを行えるようになるでしょう。
アクシデント時に対応しやすい
自然災害や感染症の流行などの非常事態が起こった際でも、業務を続けなければならない場合もあるでしょう。データを電子化・クラウド化しておくことで、そういったアクシデントが起こっても、大事なデータの消失を防げます。また、業務の一部を外部委託することも、業務を停止せずに経済活動を続けることにつながります。
競争力が強化される
これまで煩雑な作業に費やしていた時間やリソースを、データの整理・活用といった付加価値の高い業務に振り向けられるようになります。適切に分析することで、企業は自社の課題や市場の動きにいち早く気づき、現場レベルから経営戦略にいたるまで迅速かつ精度の高い判断が可能になります。その結果、リスクへの対応力や成長機会の創出力が向上し、持続的な競争優位性を築く可能性が高まるでしょう。
人材関係が円滑になる
バックオフィス業務を効率化することで、職場に余裕が生まれ、ストレスや摩擦が減少し、人間関係が良好になります。さらに、円滑なコミュニケーションが取れる環境では、立場や役職に関係なく意見を出しやすくなり、モチベーション向上や離職率低下にもつながります。企業方針やビジョンも自然と浸透し、従業員同士が協力して業務に取り組めるようになるため、職場全体で生産性や業務品質が向上する好循環が生まれるでしょう。
バックオフィスの業務改善方法
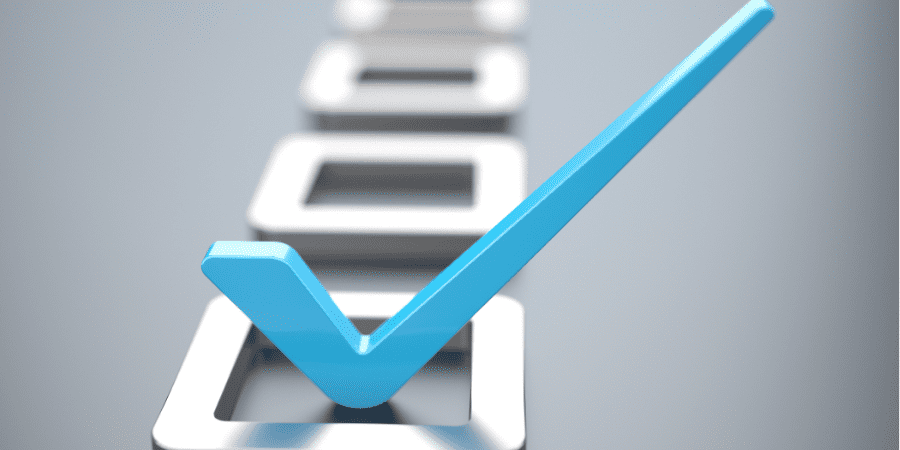
バックオフィス業務における課題を解決できると、企業運営が効率アップします。では、具体的に何をすればよいのでしょうか。ここでは例を6つご紹介します。
クラウドサービスを利用する
クラウドサービスとは、アプリやソフトウェアを、インターネット経由で利用できるサービスです。インターネット環境があればいつでも操作でき、情報の共有も容易にできます。比較的手軽に導入できるため、なるべく手間をかけたくない場合におすすめです。会計や備品管理、書類作成など、さまざまな分野のサービスが出されています。
例えば会計ソフトでは、経費の仕訳を自動で行なったり、レシートをスマホで読み込んだりできる機能が付いており、作業効率を大幅に高められるでしょう。
また、会社にある1台1台のPCへソフトをインストールする必要がなく、使用人数に合わせてプラン変更可能な点もメリットです。
【関連記事】
経費精算システムはクラウド型がおすすめ!主要6製品を比較
備品管理システムのおすすめ5つを比較!サービスの選び方や注意点なども
ワークフローシステムを利用する
ワークフローシステムとは、業務の流れ(ワークフロー)を電子的に管理・監視するためのシステムです。従来紙ベースで行われていた、稟議書や報告書、各種申請書などの申請・確認・承認・決裁・報告といった業務を電子化することで、業務の大幅なスピードアップと効率化を実現できます。
また、ヒューマンエラーの防止、コンプライアンスの強化、業務の流れの可視化といったメリットもあります。
【関連記事】
ワークフローシステムとは?機能や特徴、おすすめ製品比較などを交えて解説
社内向けチャットボットを利用する
チャットボットとは、「チャット」と「ボット」を組み合わせた言葉で、AI(人工知能)を活用して自動的に会話を行うプログラムのことです。
社員の質問に自動で回答する社内向けチャットボットを活用することで、社内でのコミュニケーションが円滑になり、社内部署間での情報共有や問い合わせ対応の負担を減らせます。
【関連記事】
バックオフィス業務を自動化するには?効率化の課題や成功のポイントをわかりやすく解説!
【中小企業向け】業務改善×AIでコスト削減と生産性アップ!業務別活用シーンと成功事例6選
オンラインアシスタントに外注する
人手不足だったり、担当者1人あたりの業務量が多すぎたりする場合は、オンラインアシスタントに外注するのも手です。
オンラインアシスタントとは、インターネット上でのやりとりを通じてクライアントの業務を代行するサービスのことで、バックオフィス業務全般に対応可能です。
- 経験豊富なワーカーさんが迅速かつ確実な対応をしてくれる
- 正社員を雇用するより人的コストを抑えられる
- 繁忙期のみの利用もできる
こういったメリットにより、利用する企業が近年増えています。
【関連記事】
オンラインアシスタントとは?料金相場やメリット、デメリットなどを徹底比較
安いオンラインアシスタントのおすすめ5選!【比較表つき】
業務を標準化しマニュアルを作成する
バックオフィス業務を標準化することで、属人化が解消され、新入社員や担当者以外の従業員でも、スムーズに作業ができるようになります。
その後、それらの業務手順を誰でも再現できるよう文書化し、マニュアルを作成しましょう。
これにより業務負担が分散され、引き継ぎが円滑になるだけでなく、業務品質も一定に保たれるようになります。
ペーパーレス化する
紙の書類を電子データに変換し、電子文書管理システムに格納することで、書類の検索や共有、保存が容易になります。さらに、デジタル署名を導入することで印鑑や手書き署名を廃止でき、承認プロセスの効率化が可能です。
これらを組み合わせることでバックオフィス業務全体の生産性が向上し、業務プロセスがよりスムーズになります。
オンラインアシスタントはフジ子さんがおすすめ

オンラインアシスタントサービス「フジ子さん」では、経理・秘書/総務・人事・Webサイトの運用など、幅広いバックオフィス業務をサポートしています。これまで、官公庁を含めた累計2000以上のユーザーにご利用いただいています。
フジ子さんには、次のようなメリットがあります。
- ハイレベルなアシスタントに、パート社員並のコストで仕事を頼める
- 業務量に応じて、柔軟なプラン変更や翌月解約もできる
- 無料トライアルで、実務能力の事前チェックができる
フジ子さんを利用することで、バックオフィス業務の効率を大幅にアップできるでしょう。
まとめ
今回はバックオフィスについて、仕事内容や重要性、効率化のポイントなどを解説してきました。
バックオフィスは、企業にとってなくてはならない業務です。繰り返しになりますが、バックオフィスが滞ると企業運営が立ち行かなくなります。
軽視されることも多い部門ですが、その重要性をあらためて認識した上で、効率化にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。本記事が参考になれば幸いです。